「判断推理の問題が全然解けない…」 「考え方がわからなくて、いつも時間だけが過ぎていく」
そんな風に悩んでいませんか?
公務員試験を目指す多くの受験生にとって、判断推理は“壁”になりやすい科目です。
特に独学の方や、文系出身の方の中には、「もう判断推理は捨てようかな…」とあきらめかけている人も少なくありません。
しかし実は判断推理は、「慣れ」と「パターン理解」で誰でも点を取れるようになる分野です。
本記事では、判断推理に苦手意識を持っているあなたのために、
- 判断推理とはどんな問題なのか?
- なぜ苦手に感じるのか?
- どんな解き方・コツで克服できるのか?
といった内容を、具体例や対策法も交えてわかりやすく解説していきます。
記事を読み終えるころには、判断推理に対する不安が薄れ、「これなら自分でもできるかも」と思えるようになるはずです。
\数的塾の限定講義&合格ガイド無料配布中/
そもそも判断推理とは?試験内での位置づけと重要性を解説
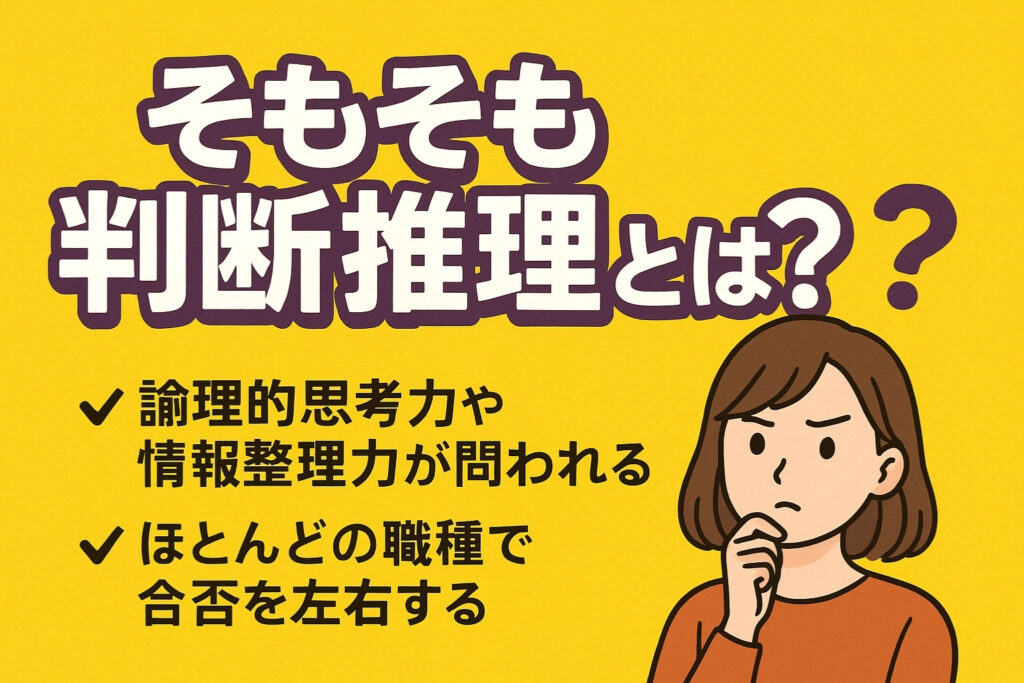
判断推理は、公務員試験の「数的処理」に含まれる分野の1つです。
与えられた条件をもとに論理的に答えを導く力を問う問題が多く、計算ではなく思考力が中心となるため、暗記では対応できません。
判断推理ははほとんどの職種で出題数が多く、合否に直結する科目なため、対策は非常に重要です。
配点も高く、苦手なままだと教養全体の得点が伸びにくくなりますので、まずはこの科目の性質を理解し、戦略的に対策することが、得点アップの第一歩になります。
数的処理の他の科目との違いについて
公務員試験の「数的処理」には、判断推理のほかに数的推理・資料解釈・空間把握といった分野があります。
これらは一見似ているように見えますが、出題形式や求められる力は異なります。
判断推理は、計算よりも論理的思考力や情報整理力が問われるのが特徴です。
文章中の条件を正しく読み取り、矛盾なく組み立てる力が求められるため、「頭の中で考えるパズル」に近いとも言えるでしょう。
一方で、他の数的処理の科目は次のような特徴があります。
- 数的推理:中学〜高校レベルの数学の知識や計算力を使って解く問題が中心
- 資料解釈:グラフや表からデータを読み取り、計算・判断するスキルが必要
- 空間把握:立体図の展開・回転といった空間認識能力が問われる問題が中心
このように、判断推理は「考える力」、数的推理は「計算力」、資料解釈は「読み取り力」、空間把握は「空間認識能力」と、それぞれ異なるスキルが求められます。
中でも判断推理は、パターンに慣れることで大きく点が伸びやすい分野なので、早めに基礎を押さえておくと、他の分野にも時間を回しやすくなります。
 ミキサック
ミキサック試験対策を判断推理から始めることで、読解力や論理力も身に付くため、他の科目を対策するときにも役立ちますよ!
職種による判断推理の出題傾向と配点について
判断推理は、公務員試験の中でも出題頻度が高く、ほとんどの職種で合否を左右する重要な分野となります。
そもそも教養試験全体の中で数的処理が占める割合は大きく、その中でも判断推理は毎年安定して5~8問前後出題されています。
以下は主な職種における出題の目安です。
- 国家一般職(大卒程度):数的処理 約15問中、判断推理 約6~7問
- 地方上級(都道府県・政令市):約14問中、判断推理 約5~6問
- 特別区(東京23区):約12問中、判断推理 約5~6問
上記のように、判断推理はどの試験区分でも安定して出題されるため、「捨て科目」にせず、最低限の得点を確保しておくことが必須です。
しっかりと対策すれば数的処理の中でも比較的得点しやすい分野でもあるため、対策の優先度は高いと言えます。



判断推理は得点力が付くまでに時間がかかる分野なので、じっくり時間をかけましょう!
判断推理が苦手と感じる理由について
判断推理を苦手に感じる受験生は非常に多く、その原因は「問題の形式に慣れていない」ことにあります。
判断推理では、複数の条件を読み取り、矛盾のないように整理して答えを導く必要がありますが、学校教育ではあまり触れる機会のないタイプの問題が多く出題されるのが特徴です。
特に初学者にとっては、どこから手をつけていいのかがわからず、問題を前にして固まってしまうことも少なくありません。
判断推理が苦手と感じやすい理由として、次のような特徴が挙げられます。
- 問題文が長く、条件の整理に時間がかかる
- 正しい解法の型を知らず、毎回ゼロから考えてしまう
- 図や表を使わず、頭の中だけで処理しようとして混乱する
上記のように悩んでしまいがちですが、パターンに慣れ、型を覚え、手を動かす習慣をつけることで、誰でも着実に克服できる分野です。
苦手意識は「経験不足」から来ているケースがほとんどなので、早い段階で対策を始めることがポイントになります。



判断推理は実は誰でも得意分野になり得る分野です!今は苦手かもしれませんが、とにかく頑張って対策しましょう!
判断推理の主な出題パターンと特徴を紹介


判断推理の問題は、出題形式こそ毎回異なるように見えますが、実は一定のジャンルごとにパターン化されており、特徴的な解き方が存在します。
このパターンを把握し、型を覚えることで、解答スピードと正答率が大きく向上します。
たとえば「順序関係」「対応関係」「命題」「位置関係」などは毎年のように出題される頻出テーマであり、どの職種の試験でも見かける定番ジャンルです。
ここからは、判断推理で出題される代表的なジャンルと、それぞれの特徴について1つずつ見ていきましょう。
集合・命題
集合・命題の問題では、「AのうちBに当てはまるものはいくつか?」「Aであり、かつBであるのはどれか?」などの条件を読み解きながら、正しい命題を選ぶ力が求められます。
まずは文章の意味を正確に理解することが出発点です。
たとえば「AならばB」という表現は、「Aが真のときは、必ずBも真になる」というルールに従っていますが、逆は必ずしも成り立ちません。
この論理のクセを理解していないと、真偽の判断を間違えてしまいます。
- 例題
-
ある会社では、社員A・B・Cの3人が以下の3つの資格のいずれか、または複数を保有しています。
- 資格X(簿記)
- 資格Y(英検)
- 資格Z(TOEIC)
次の条件がすべて満たされているとき、正しい選択肢を1つ選びなさい。
- Aは資格Xを持っている。
- 資格Xを持っている人は必ず資格Yも持っている。
- Cは資格Xを持っていないが、資格Zは持っている。
- Bは資格Yを持っていない。
- 選択肢
-
- A:Bは資格Zを持っている。
- B:Aは資格Yを持っていない。
- C:Cは資格Yを持っていない。
- D:Bは資格Xを持っていない。
- E:Aは資格Zを持っている。
正解
答え:D
このような集合・命題の問題は、「AならばB」「Bではない ⇒ Aではない」といった命題の正しい読み替えと逆推理が鍵となります。
問題文をそのまま読むのではなく、論理関係を丁寧に整理する癖をつけることが重要です。



「対偶」「否定」「逆・裏」などの概念も問われるので、高校で習う数学Aのような問題ですね!
順序関係
順序関係の問題では、人物や物の「順番」「順位」「時間的な前後関係」に注目して、条件をもとに1つの正解を導き出す力が試されます。
条件が複雑に絡み合う場合が多いため、図やメモを活用して整理することが重要です。
- 例題
-
あるカフェにA〜Dの4人がそれぞれ別の時間に来店し、しばらく滞在してから退店しました。以下はその来店・退店に関する情報です。このとき、矛盾なく成立する来店・退店の順序を考えましょう。
- AはBよりも先に来店し、Cよりも後に退店した。
- Cは4人の中で最も早く退店した。
- Dは最後に来店したが、退店は一番早くなかった。
- Bの来店はCよりも前だったが、退店はAより後だった。
- 選択肢
-
- A:Dは、来店も退店も最も遅かった。
- B:Cの退店後、Dが最初に退店した。
- C:Aは、来店も退店も2番目だった。
- D:Bは、来店も退店も3番目だった。
- E:Bの来店はAよりも後だった。
正解
答え:C
このような条件は、正しい順序が1つでも固定されていないとイメージしづらく、混乱しがちです。
今回の問題では、以下のような表を作りましょう。
| 人物 | 来店順 | 退店順 |
|---|---|---|
| A | 2 | 3 |
| B | 1 | 4 |
| C | 3 | 1 |
| D | 4 | 2 |
表を作るときのポイントは以下のとおりです。
- 確定情報から埋めていく
- 「より前」「より後」といったあいまいな情報は複数パターンを検討する
- 結果的に矛盾しない並びを見つける
問題数をこなすことで条件の整理に慣れ、パズルを解くような感覚で取り組めるようになります。



1番大事なのは、矛盾しない解答かどうかです。条件をすべて満たせるようになるまで考えましょう。
対応関係
対応関係の問題は、複数の人物やモノの属性(たとえば「名前」「年齢」「職業」など)が、どのように組み合わさっているかを特定するタイプの問題です。
公務員試験では非常に定番の形式で、出題頻度も高く、しっかりと得点源にしておきたいジャンルです。
この問題を解くカギは、与えられた条件をマトリクス(対応表)にして視覚的に整理すること。
文章で把握するのが難しい情報も、表にして並べることで一気に見通しがよくなり、条件の重なりや矛盾に気づきやすくなります。
- 例題
-
3人の人物(A、B、C)は、それぞれ異なる趣味(映画鑑賞・読書・音楽鑑賞)を1つずつ持っています。 また、彼らは休日の過ごし方として、「家で過ごす」「カフェで過ごす」「公園で過ごす」のいずれかを好みます(重複なし)。
以下の条件から、各人物の趣味と休日の過ごし方を特定してください。
- 映画鑑賞をしている人物は、休日はカフェで過ごしている。
- Aさんの趣味は読書ではない。
- 音楽鑑賞をしている人物は、公園では過ごしていない。
- Cさんはカフェでは過ごさない。
- Bさんは映画鑑賞が趣味ではなく、家では過ごさない。
- 選択肢
-
- A:A. 映画鑑賞・カフェ
B. 読書・公園
C. 音楽鑑賞・家 - B:A. 音楽鑑賞・カフェ
B. 映画鑑賞・家
C. 読書・公園 - C:A. 映画鑑賞・家
B. 音楽鑑賞・カフェ
C. 読書・公園 - D:A. 読書・カフェ
B. 映画鑑賞・公園
C. 音楽鑑賞・家
- A:A. 映画鑑賞・カフェ
正解
答え:A
少々むずかしい問題を作りましたが、上記のような問題は次のような対応表を作って解きましょう。
| 映画鑑賞 | 読書 | 音楽鑑賞 | |
| A | ● | × | × |
| B | × | ● | × |
| C | × | × | ● |
| カフェ | 公園 | 家 | |
| A | ● | × | × |
| B | × | ● | × |
| C | × | × | ● |
このように、情報を表に落とし込めば「残っているのは1つだけ」という状態を視覚的に判断できるため、消去法が非常に有効に機能します。
すべてを記憶で処理しようとせず、情報を可視化する習慣が攻略の鍵になります。



ほとんどの問題は対応表を1つ作れば解ける問題ばかりなので、この問題が解ければもう試験でも通用するレベルです!
位置関係
位置関係の問題では、「東西南北」「上下左右」などの空間的な情報をもとに人物や物の位置を整理する能力が求められます。
- 例題
-
6人の学生A~Fが横一列に並んでいます。次の条件をもとに、正しい並び順を導いてください。
- AはBの左隣にいる
- CはFよりも左側にいる
- DはEの右隣ではない
- EはAより左側にいる
- Fは一番右にいる
- 選択肢
-
- A:E → C → A → B → D → F
- B:C → E → A → B → D → F
- C:E → A → C → B → D → F
- D:E → C → B → A → D → F
正解
答え:A
図を描きながら条件を整理すれば、1つ1つ確実に配置できるようになります。
位置関係の問題に苦手意識がある人ほど、まずは右端や隣接関係など確定情報を起点に組み立てていく習慣をつけることが重要です。



不確定な情報は一旦保留にして、新しく確定情報が出たら再評価して、矛盾のない解答を導き出しましょう!
試合
判断推理の「試合」分野では、登場人物同士の勝敗関係や順位をもとに、全体の構図を論理的に整理する力が求められます。
特徴的なのは、「誰が誰に勝ったか」「試合のルール」など、試合の性質に基づいた情報をもとに、正しい勝敗結果を導き出す点です。
- 例題
-
A〜Dの4人が1対1の総当たり戦(引き分けなし)を行ったところ、以下のことがわかっている。これらの情報をもとに、この試合で最も勝利数が多い人物は誰か答えなさい。
- AはBとCに勝ち、Dに負けた。
- BはCに勝った。
- CはDに勝った。
- 同点の場合は、同点者同士の勝負で勝っている方を優位とする。
- 選択肢
-
- A:A
- B:B
- C:C
- D:D
正解
答え:D
この問題を解くときは、以下のような表を作りましょう。
| A | B | C | D | 勝数 | |
| A | – | ○ | ○ | × | 2 |
| B | × | – | ○ | × | 1 |
| C | × | × | – | ○ | 1 |
| D | ○ | ○ | × | – | 2 |
勝敗ジャンルの問題を解くためには、次のような手順が効果的です。
- 勝敗関係や得点のルールを表に整理する
- 条件が示す相対関係を「強さの序列」や「勝数」として可視化する
- 一部が分かれば、残りの関係性を補完するように消去法で推理する
このように、「直接の勝敗」だけでなく、「〇〇より強い△△に勝った」などの間接的な情報をもとに論理的に積み上げていく力が問われるため、序列を正確に把握する訓練がカギとなります。



実際のスポーツの試合で行われるリーグ戦のような表ですね!
記号・暗号系
記号・暗号系の問題は、一見ランダムに見える記号や数字の列に隠されたルールや規則を読み解く問題です。
パズルやIQテストのような要素が強く、法則の発見力と検証力が求められます。
- 例題
-
次の単語は、ある規則に従って暗号化されています。この規則に従って、「MATH」を暗号化したときの正しいものを選びなさい。
- NOTE → OQWI
- SEND → TGQH
- CARD → DCUH
- 選択肢
-
- A:NBWL
- B:NCWL
- C:NDWL
- D:NCXM
正解
答え:B
一度法則に気付けばすぐに答えが導けますが、法則を見抜けないと延々と悩んでしまう分野でもあります。
複数のパターンを検証する「柔軟な思考」がカギとなります。



捨てるのはもったいないですが、本当に難しい問題もたまにあるため、できそうになければ後回しにしましょう!
推理・真偽
推理・真偽の問題は、複数の人物の発言をもとに「誰が本当のことを言っていて、誰がウソをついているのか」を見極める、高度な論理パズル系問題です。
一人の発言から他の発言と照らし合わせ、矛盾の有無をもとに真実を導く力が問われます。
- 例題
-
あるクラスで、A〜Dの4人が1人ずつ並んで座っています。このとき、次の発言がありました。ただし、「正しいことを言っているのはちょうど1人だけ」です。このとき、4人の並び順として正しいものはどれかを選びなさい。
- A「BはDの隣に座っている」
- B「Cは私(B)の右に座っている」
- C「私はDの左隣に座っている」
- D「Aは一番左に座っている」
- 選択肢
-
- A:A → B → D → C
- B:A → D → B → C
- C:D → A → B → C
- D:C → A → B → D
- E:B → A → D → C
正解
答え:A
推理・真偽の問題は、以下のように解くのが基本です。
- 誰か1人を「本当のことを言っている」と仮定する
- 他の発言と整合性がとれるか確認
- 矛盾があれば仮定を変更して再度検証
仮定 → 検証 → 矛盾発見 or 合致の繰り返しに慣れれば、思考の筋道が見えてきます。



最初は苦手意識を持ちやすいジャンルですが、1つ1つ丁寧に検証するところから始めてみると、意外と理解しやすいことに気付けるはず!
操作手順
「操作手順」は、条件やルールに基づいて対象を変化させた結果を求める問題です。
暗記だけでは太刀打ちできず、論理的思考力と正確な読解力、そして丁寧な試行錯誤が求められます。
複雑なように見えても、ルールを整理し1つ1つの操作を順番に追っていけば、着実に正解にたどり着けるのがこのジャンルの特徴です。
- 例題
-
以下のルールに従って、3桁の数字を変換する操作を繰り返したとき、「初期値が428である場合、2回操作したあとの数字はどれか?」
・1の位と10の位の数字を入れ替える
・その後、すべての桁の数字を2ずつ加える(ただし、9を超えた場合は1に戻る)
・この操作を2回繰り返す - 選択肢
-
- A:641
- B:734
- C:863
- D:285
- E:176
正解
答え:C
操作手順の問題は、以下のような力が必要です。
- 手順を1つずつ丁寧に追う力
- 桁の操作や数値の変化を正確に処理する力
- 「繰り返し処理」や「例外条件」に対する柔軟な対応力
このジャンルは一見複雑に見えますが、慣れてくるとルールに沿った単純作業の繰り返しであることに気付きます。
過去問やパターン演習を通じて、頭で処理するより紙に書き出す習慣をつけておくと得点源に変えやすい分野です。



紙に書くと、本当に一気に簡単になります!パターンはないため、どの問題が来ても焦らず1から解いていきましょう。
判断推理の苦手を克服する解き方のコツを紹介


判断推理を苦手に感じる多くの受験生がつまずく原因は、「解き方の型」を知らず、毎回ゼロから思考をスタートさせているからです。
結論として、判断推理は「型」を知り、「視覚化」と「時間管理」を意識することで、苦手を克服し得点源に変えることができます。
本章では、判断推理をスムーズに解くための実践的な3つのコツを紹介します。
この3つのコツを意識して学習すれば、今まで難しく感じていた判断推理の問題もスムーズに処理できるようになり、確実に点数を伸ばせるようになるでしょう。
解法パターンを「型」として身につける
判断推理を解く際、もっとも効果的な方法は「型」を覚えることです。
毎回違う問題が出ているように見えても、出題されるパターンにはある程度の傾向があり、問題を見た瞬間に解法を思い出せるようになることが得点アップへの第一歩となります。
代表的な型を以下にまとめました。
- 条件整理型:表に落とし込むと解きやすい
- 論理対比型:矛盾を見つけることで真偽を見抜く
- 並び替え型:条件を図解して並びを特定する
上記のように型を自分の中にストックしておけば、初見の問題でも「あ、これはあのタイプだ」と判断でき、思考が止まらなくなります。
ただ漫然と問題を解くのではなく、「どの型か」を意識しながら解くことで、知識が定着しやすくなるでしょう。



それぞれの型に正確な呼び名はありませんが、わかりやすいように名前を付けてみました!
図や表を作って情報を視覚化する
判断推理では、文章中の情報をそのまま頭の中で処理するのは非常に困難です。
特に条件が多くなると混乱しやすく、正確な判断ができなくなってしまいます。
そこで重要になるのが「図や表に情報を落とし込み視覚化すること」です。
たとえば、以下のような問題が出たとします。
A〜Fの6人が左から右に1列に並んでいます。
次の条件をすべて満たすように並んでいるとき、左から3番目にいるのは誰ですか?
- CはAよりも左にいる。
- DはFのすぐ右にいる。
- BはAのすぐ隣にはいない。
- EはCのすぐ左にいる。
このような情報をそのまま読んで判断するのではなく、以下のように並び順を紙に書いて整理することで、答えがすぐに見えてきます。
左 ← E C B F D A → 右
この視覚化の習慣があるかどうかで、問題処理のスピードと正確さに大きな差が出ます。
「読んで考える」のではなく、「書いて見る」ことをクセづけましょう。



それぞれの問題パターンで解答に必要な図や表は異なります。全パターンを網羅できるようにしましょう!
解答時間を意識した演習をする
判断推理は、ただ正答するだけでは不十分で、「時間内に解けるかどうか」も合格を左右する重要なポイントになります。
いくら理解できていても、試験本番で1問に10分かかっていては間に合いません。
そこで大切なのが、「演習時から時間を測る習慣」です。
- 1問ごとにストップウォッチで測る
- 自分の平均時間を把握する
- 解けない問題に時間をかけすぎず切り替える判断力を養う
判断推理では、問題ごとに「秒で答えを出せる型」と「考察が必要な型」に分かれます。
これを把握した上で、得点すべき問題に時間をかけ、難問は後回しにする判断力を育てておくことが合格への近道です。



時間を意識するのは、本番から1〜2ヶ月前でOKです!最初はとにかく理解すること・正しく解くことに重点を置きましょう。
判断推理を解くときの3ステップを紹介
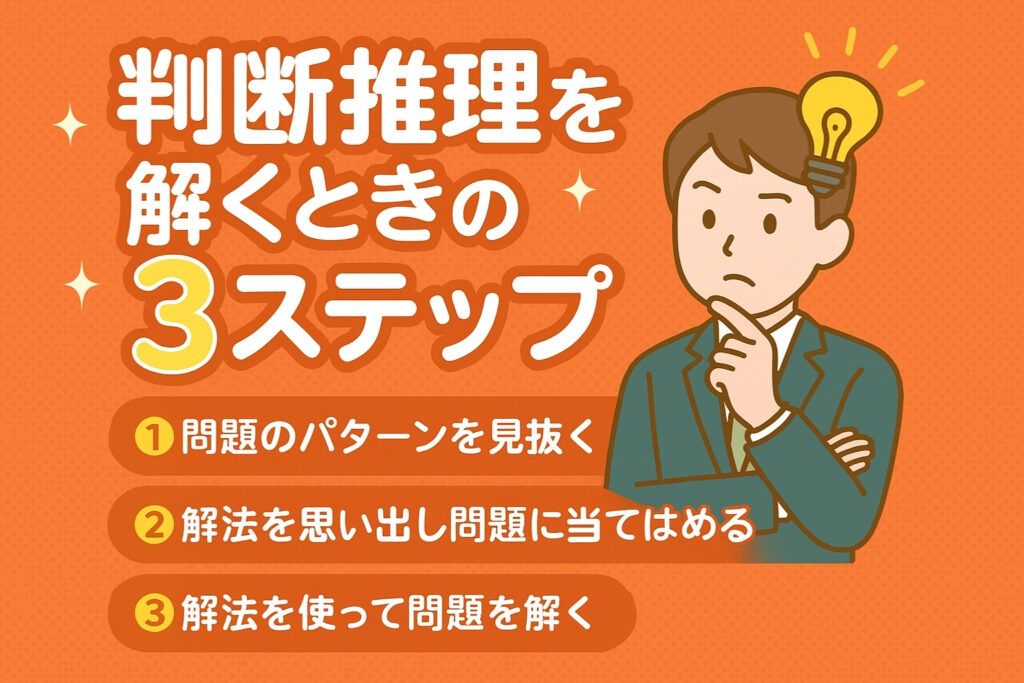
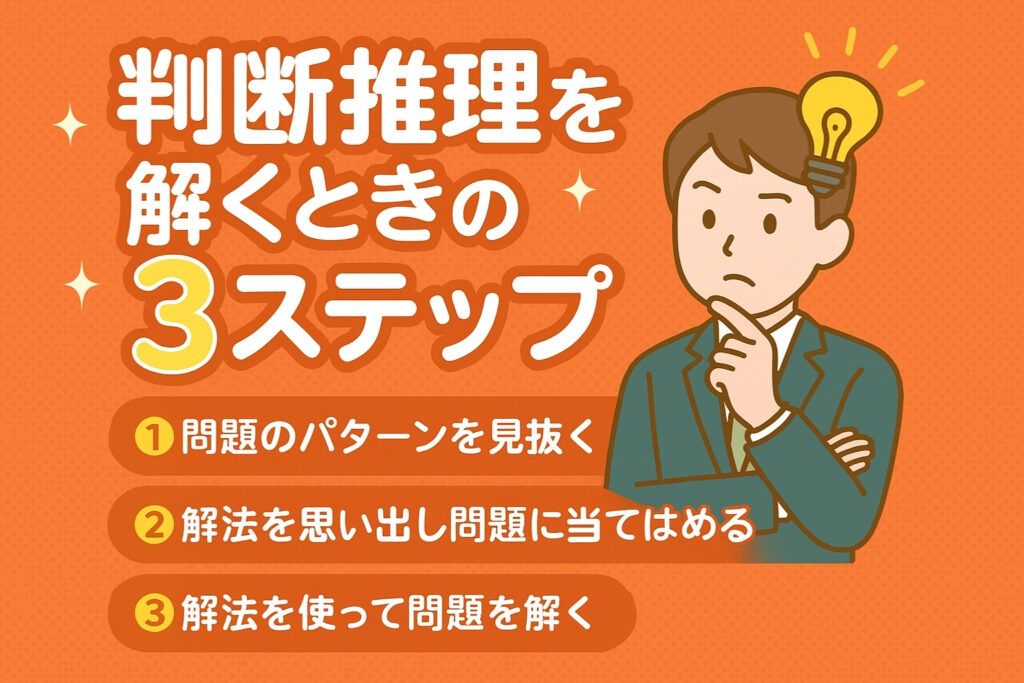
判断推理を効率よく解くためには、「何となく解く」のではなく、一定のプロセス(手順)に沿って考える習慣を身につけることが重要です。
思考が整理され、迷う時間を減らせるだけでなく、正答率の向上にもつながります。
そこで本章では、初学者でも実践できる「判断推理を解くための3ステップ」を紹介します。
実際の演習や過去問でもこの手順を繰り返すことで、解答までの流れが自然に身につき、試験本番でも落ち着いて対応できるようになるでしょう。
①問題のパターンを見抜く
最初のステップは、出題されている問題がどのパターンに属するのかを見極めることです。
判断推理は、命題・順序・位置・論理パズルなど、いくつかの定番パターンに分類されるため、それを見抜くことで最適な解法の選択がしやすくなります。
- 条件が複数あり、それをもとに位置を判断する →「位置関係」
- 勝ち負けの情報がある →「試合系」
- 特定の条件に合う選択肢を探す →「集合・命題」
問題の冒頭や設問形式を見るだけでどのパターンか判断できるようになると、解法の選択スピードが上がります。
最初に「型」を見抜く力を育てることが、スムーズな解答への土台となるはずです。



最終的な理想としては、問題を見た瞬間にパターンがわかるところまで持っていきたいですね!
②使う解法を思い出し問題に当てはめる
次に行うべきことは、そのパターンに適した「型(解法)」を思い出し、問題に当てはめることです。
ここで重要なのは、ただ知識として覚えているだけでなく、実際に「この問題ならこの手順でいける」と判断できる経験値です。
- 順序関係:空欄の図(座席表やタイムテーブルなど)を使い、左右や上下の配置を視覚的に整理する
- 集合・命題:「すべて〜」「〜でない」などの命題は、ベン図や対偶を使って論理的に判断する
- 対応関係:人物×属性の表(マトリクス)を作り、条件に応じて◯✕で埋めていく
- 位置関係:「すぐ右」「間に1人」などの条件を図に描き、相対的な位置を明確にする
- 試合・勝敗:勝敗の情報を対戦表にまとめ、◯✕や勝ち数で順位を割り出す
上記のように、ストックされた解法を引き出す作業は「解答の時短」に直結します。
「あの問題と似ている」とすぐに気づくことで、選択肢の取捨選択もスムーズになるはずです。



今までに見たことのない問題は基本的には出題されませんので、落ち着いて解きましょう!
③解法を使って問題を解く
最後のステップは、実際に思い出した解法を使って手を動かし、正確に解答を導き出す作業です。
ここで注意すべきは、「正確さ」と「スピード」の両立です。
具体的には以下のことを意識しましょう。
- 書き出した図や表に矛盾がないかをチェック
- 一度導いた答えを、逆から検証してみる
- 試験本番では「確信がある場合は即答」「迷うなら一旦飛ばす」の判断力も重要
このステップは反復練習で磨かれます。
同じ解法を何度も使いながら「使えるようになる」まで手を動かすことが成功の秘訣です。



解法が合っていても、結局解答が間違えていたら意味がありません。もし時間が余ったら、必ず再確認しましょう。
判断推理のよくあるQ&A
判断推理を勉強するときによくある質問と、その解答をまとめました。
まとめ
判断推理は、公務員試験の中でも苦手とする受験生が多い科目ですが、「型」と「慣れ」で得点源に変えられる分野です。
本記事では、判断推理の基本から出題パターン、克服法、学習ステップまでを丁寧に解説してきました。
重要なポイントを改めて整理すると、以下の通りです。
- 判断推理は出題比率が高く、捨てるにはリスクが大きい科目
- 出題パターンはおおよそ決まっており、「型」を覚えれば初見でも対応できる
- 視覚化・解法パターンのストック・時間管理が得点アップのカギ
- 「センス」より「慣れ」が重要。苦手意識は練習で克服できる
苦手なまま試験本番を迎えるのではなく、今から少しずつでも演習を重ねることで、確実に得点力は上がります。
判断推理を得点源にできれば、合格はぐっと近づきます。
もし「自分1人では限界を感じる」「何をどう勉強すればいいのか迷ってしまう」という方におすすめなのが、公務員試験合格に特化したオンラインスクール「数的塾」です。
- 出題傾向に基づいた各科目の徹底解説講義
- 忙しくても続けられる短時間・高効率のカリキュラム
- わからないところはすぐに聞けるサポート付き
独学では得られない、「正しい勉強法」と「挫折しない学習環境」が、あなたの合格を力強くサポートします。



気になる方は、以下のリンクからLINEを友だち追加してみましょう。今なら無料で試験対策ガイドが付いてきます!
\数的塾の限定講義&合格ガイド無料配布中/
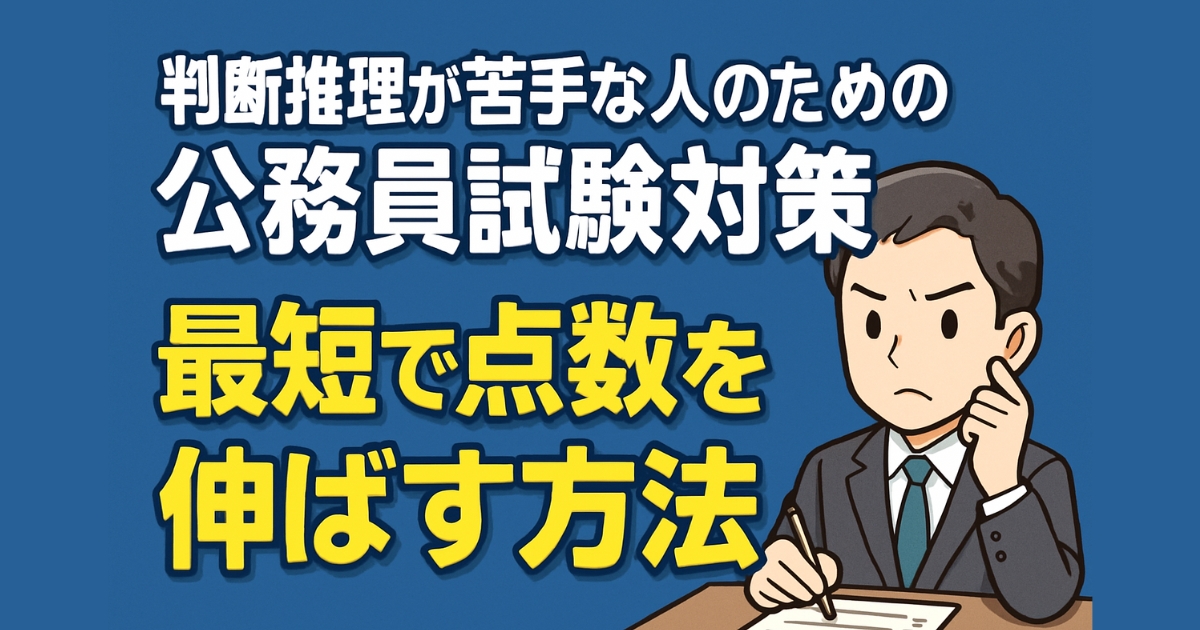
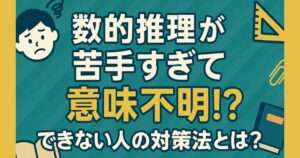
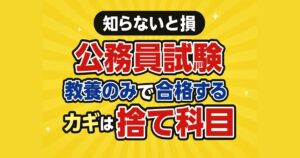

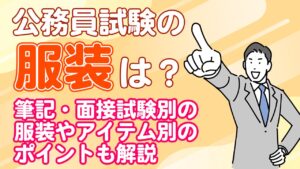

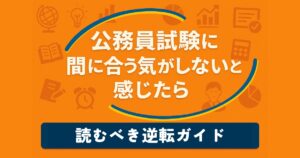
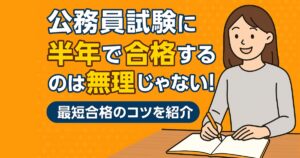

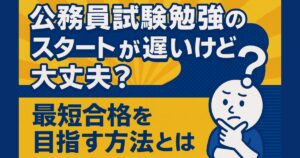
コメント