公務員試験の教養試験に向けて勉強を始めたものの、範囲が広すぎて「どの科目に手を付ければいいのかわからない」と不安になっていませんか?
全科目を完璧に対策しようとすると、効率が落ちて逆に合格が遠のきます。
そこで本記事では、限られた時間の中で合格を勝ち取るための「捨て科目」の作り方や「絶対に外せない科目」について詳しく解説します。
効率的に勉強し、最短ルートで公務員になるためにも、ぜひ最後までご覧ください。
\数的塾の限定講義&合格ガイド無料配布中/
公務員試験に効率よく合格するなら捨て科目は絶対に作るべき
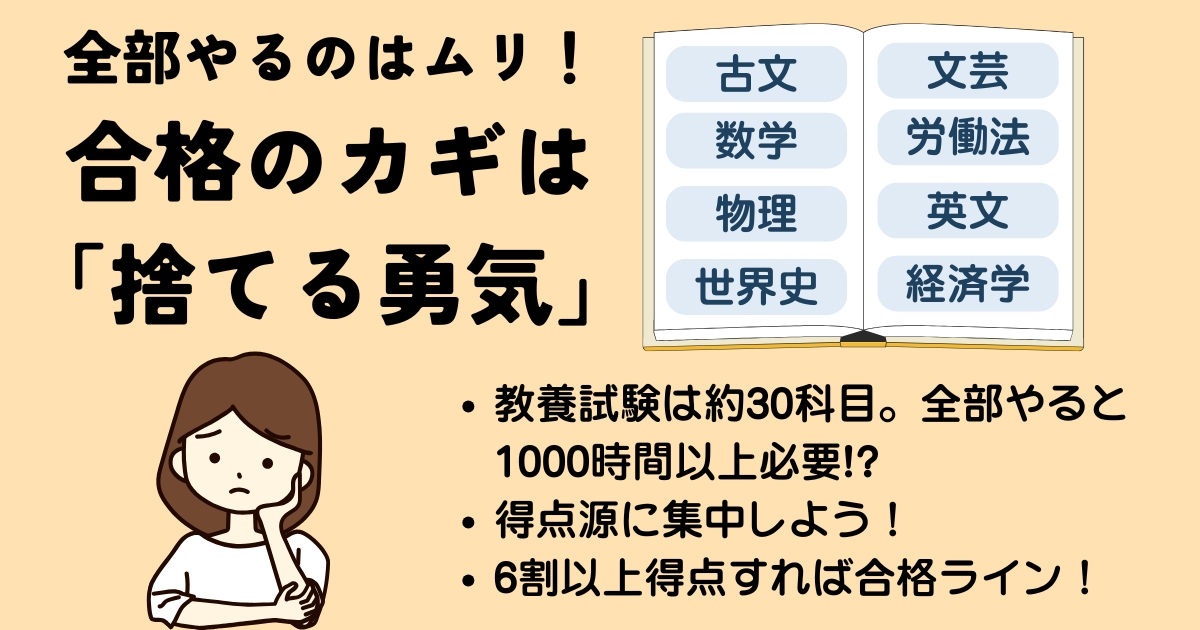
1年以上かけてじっくり勉強する人は別ですが、ほとんどの人は捨て科目を作るべきです。
教養試験の科目数と、それぞれの出題範囲は非常に広大で、すべて対策するのは非現実的。
むしろ、得点源となる主要科目にリソースを集中し、効率の悪い科目は思い切って切り捨てるほうが合格は近づきます。
捨て科目を作るべき理由について、より詳しく見ていきましょう。
全科目を網羅していたら時間が足りないから
公務員試験の教養試験では、約30科目の中から出題されます。
学生時代に習っていない分野においては、1から勉強することになるため、対策には膨大な時間が必要です。
もし全科目を網羅しようものなら、1000時間勉強しても全然足りません。
そこで捨て科目を作ることで、合格に必要な勉強時間を大幅に減らせます。
科目ごとに出題数の偏りがあるから
教養試験の科目ごとの出題数には偏りがあります。
10問以上出題される科目もあれば、1〜2問しか出題されない科目もあり、差が歴然です。
そのため、出題数の少ない科目に多くの勉強時間を割いたとしても、点数に直結しません。
一点注意すべきこととして、受験する職種によって、出題数や出題範囲に違いがあることが挙げられます。
そのため、誤って出題数の多い科目を捨て科目にしないように気をつけましょう。
満点を狙うよりも合格することが重要だから
公務員試験は満点を狙わなくても、合格ラインより上にいれば合格できます。
そのため、すべての科目に手を付けて全体の5割しか得点できないよりも、捨て科目を作って7割得点するほうが合理的です。
およそ全体の6割以上取れていれば合格ラインに乗るため、効率を重視するなら捨て科目を作ることは必須です。
公務員教養試験の捨て科目候補を紹介
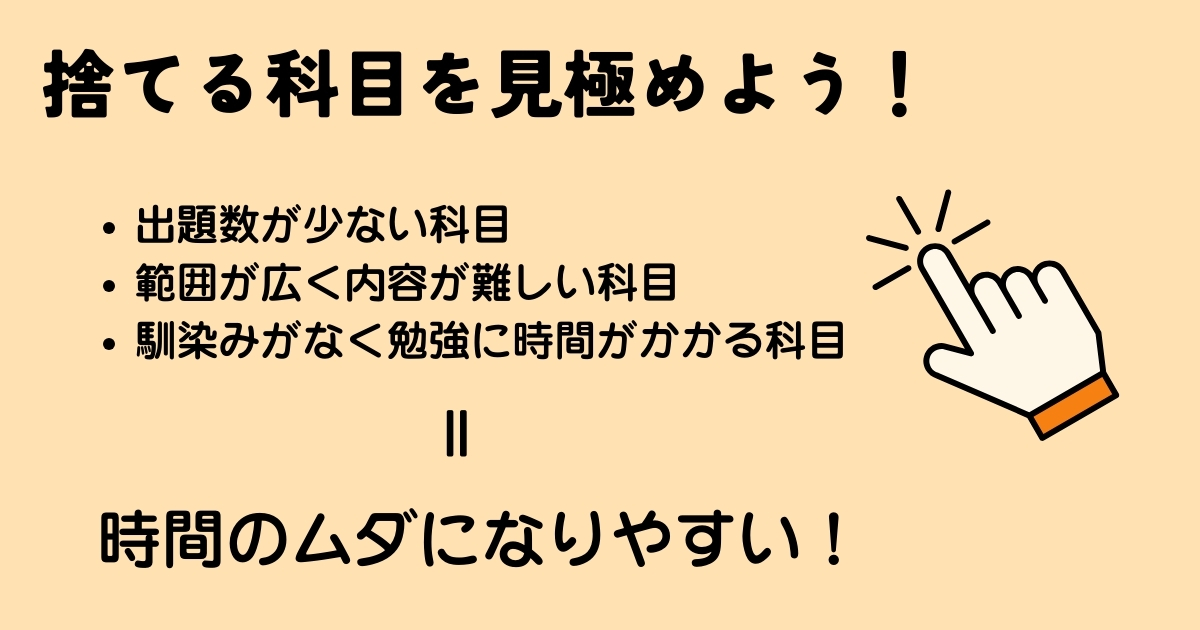
教養試験内でどの科目を捨てるかを見極めることは、合否を分けるうえで非常に重要です。
- 出題数が少ない科目
- 範囲が広く内容が難しい科目
- 馴染みがなく勉強に時間がかかる科目
上記のように、時間ばかりかかって得点に直結しづらい科目は、捨て科目の候補になります。
具体的にどの科目が捨て科目の候補になり得るか、詳しく解説していきます。
古文
古文は出題数の多い文章理解の中の1分野ですが、現代文や英文と違い、1問程度しか出題されない、もしくは出題すらされない分野です。
時間対効果が薄いため、完全に捨てたとしても合格できます。
他の科目の対策が終わり、学問として興味がある場合のみ対策すればよいでしょう。
文学・芸術
文学・芸術は、いずれも人文科学の中の出題分野です。
職種によって1問程度出題されますが、まったく出題のない職種も存在します。
暗記する範囲が意外と広く、得点にもつながりづらいため、完全に捨てても大きなリスクになりません。
数学・物理・地学
数学・物理・地学は自然科学の中の出題分野です。
地方上級を目指す場合や、理系専攻した方は対策しておきたいところですが、基本的には出題数が少ないため、苦手意識を持つ方は捨て科目の候補になります。
数学に関しては基本的に数Ⅰ・数Aの範囲からの出題となるため、文系の方でも余裕があれば対策しましょう。
物理・地学にいたっては、一度も専攻したことのない方は捨ててもリスクは少なめです。
国際関係・社会政策
国際関係・社会政策は、専門科目内の行政系科目に属する分野です。
特に国際関係は範囲が膨大で、的を絞りづらく、対策するのに多大な時間がかかります。
社会政策は地方上級を目指す場合は捨てるべきではありませんが、他の職種では出題がありません。
刑法・商法・労働法
刑法・商法・労働法は、専門科目内の法律系科目に属する分野です。
刑法は、裁判所事務官や労働基準監督官Aを目指す人は捨てるべきではありませんが、国家一般職や特別区にいたっては出題がありません。
2問出題される地方上級においても、やや時間対効果が薄いため、捨て科目の候補になります。
商法は範囲が膨大で得点につなげづらいため、多くの人が捨て科目にしてもリスクは少ないでしょう。
労働法は地方上級で2問出題がありますが、こちらも時間を割く意義が薄いため、余裕があったら対策する程度で問題ありません。
公務員教養試験の絶対外せない科目候補を紹介
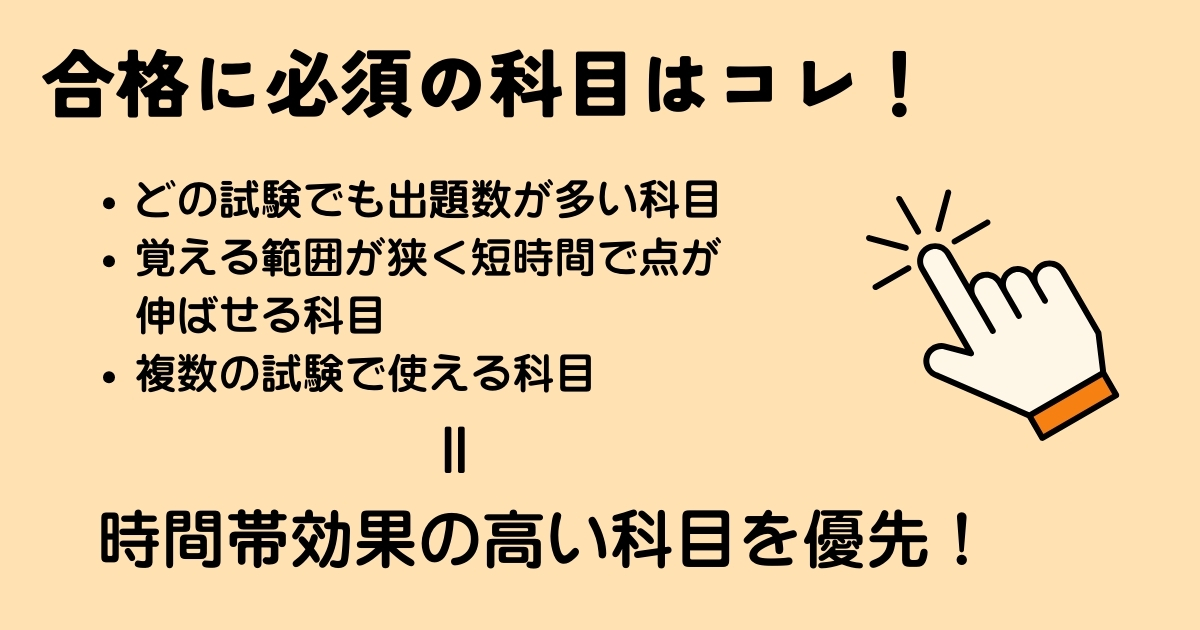
合格のために捨て科目を選ぶ一方で、「絶対に落とせない科目」を明確にしておくことも極めて重要です。
- どの試験でも出題数が多い科目
- 覚える範囲が狭く短時間で点が伸ばせる科目
- 複数の試験で使える科目
上記のように、時間対効果が高い科目は、積極的に対策することで合格ラインに乗りやすくなります。
具体的にどの科目を優先して対策するべきか、詳しく見ていきましょう。
数的推理・判断推理
出題数の多い数的処理の中でも、数的推理と判断推理は特に配点の高い科目です。
どの職種においても1番出題数が多いため、必ず1番最初に対策しましょう。
苦手意識を持つ人も少なくない分野ですが、解法のパターンを知っておけば解ける問題が多いため、一度しっかりと対策すれば怖くありません。
何度も演習を行い、出題の8割以上は得点しておきたいところです。
現代文・英文
配点の多い文章理解の中でも、現代文と英文は絶対に外せません。
対策にやや時間がかかりますが、数的処理に次いで出題数が多いため、ここを対策できるかどうかが合否を分けます。
現代文は長文の内容を把握する能力を身につけるためにも、選択肢と本文の関係性をいち早く理解できるように何度も問題に取り組みましょう。
英文は文章の内容がわからないとスタートラインにすら立てないため、英単語や文法は最低限勉強するべきです。
過去問を何度も解き、語彙力や文法知識を確実に増やしていきましょう。
社会科学
社会科学は、法律・政治・経済・社会(時事問題)の4分野からなります。
どの職種でも出題数が多いですし、専門科目と内容が被る部分もあるため、対策にかける時間以上に得点を伸ばしやすい科目です。
とにかく暗記が必要で難しい内容もありますが、歴史的な背景などストーリーを作って覚えることで覚えやすくなります。
時事問題の知識は面接や論文試験にも活きてくるため、必ず毎日ニュースアプリ等で情報を得ましょう。
憲法・民法・行政法
憲法・民法・行政法は、専門科目の中でも法律系科目に属する分野です。
どの職種でも使えますし、出題数も多め。
民法はやや範囲が広く難易度も高めですが、国家一般職では特に配点が高いため、対策は必須です。
優先順位として、憲法→民法→行政法の順に勉強することで、理解しやすくなります。
ミクロ経済学・マクロ経済学
ミクロ経済学・マクロ経済学は、専門科目の中でも経済系科目に属する分野です。
難易度はそこそこ高めですが、出題数が多いため、必ず対策しましょう。
グラフや数式の基礎を固めたうえで、「なぜそうなるのか」という経済学的な思考法を身につけることが得点のカギとなります。
インプットよりもアウトプットを重視して、問題形式や解き方に慣れていきましょう。
捨て科目を作るのはリスクもあるため注意
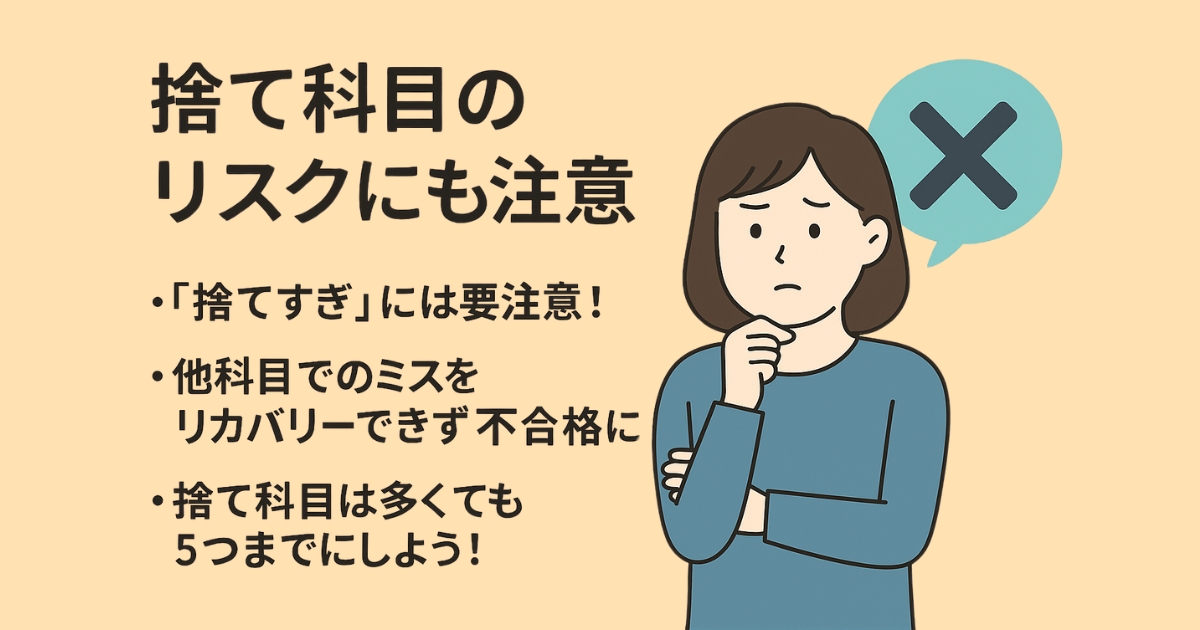
捨て科目を作ることで勉強の効率が上がる反面、リスクも存在します。
特に「捨てすぎ」は注意が必要です。
多くの科目を切り捨てすぎてしまうと、当日他の科目でミスをした場合にリカバリーできず、不合格に直結することがあります。
捨て科目を作る場合は、多くても5科目までに抑えましょう。
まとめ
公務員教養試験に合格するには、すべての科目を完璧に対策する必要はありません。
むしろ、「得点効率の高い科目に集中し、出題数の少ない科目を戦略的に捨てること」が最短合格のカギとなります。
当然ながら受験する職種によって捨てるべき科目とそうでない科目に違いが出るため、自分にはどの科目が重要なのかをしっかりと確認したうえで、効率よく勉強しましょう。
\数的塾の限定講義&合格ガイド無料配布中/
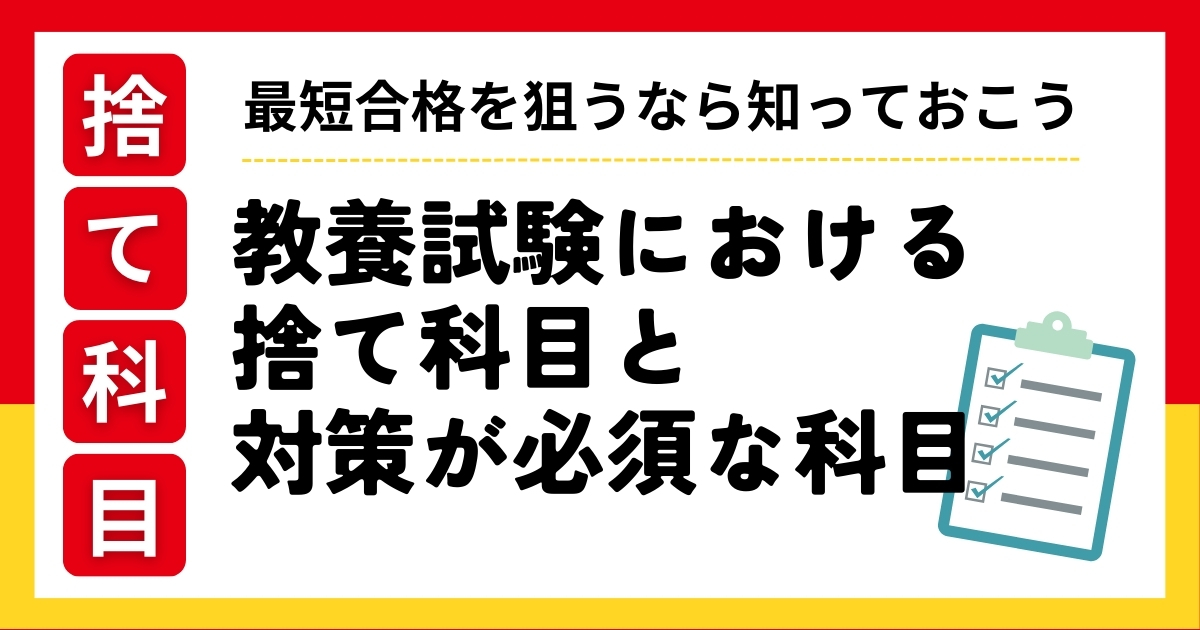
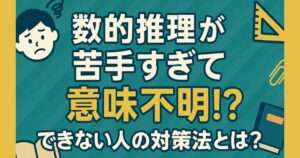
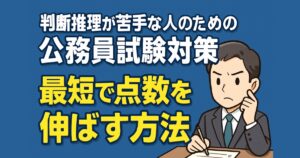

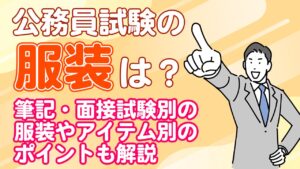

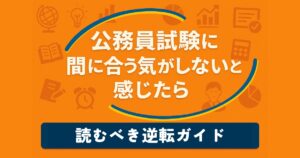
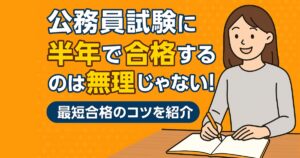

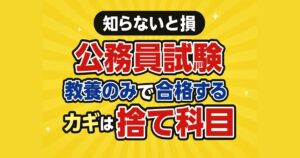
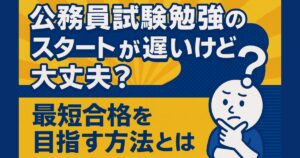
コメント