本記事をご覧になっている方は、勉強がうまくいかずに焦りや不安を抱え、「公務員試験って無理ゲーすぎる…」と感じているのではないでしょうか。
しかし、公務員試験は正しい戦略のもと対策をすれば、誰でも合格できる可能性があります。
そこで今回の記事では、公務員試験に合格するために必要な考えや、実際に合格する人に共通する特徴、具体的な対策法をご紹介。
記事を読み終える頃には、不安に襲われているところから脱却し、今やるべきことが見えてくるはずです。
\数的塾の限定講義&合格ガイド無料配布中/
公務員試験が無理ゲーだといわれる理由5選
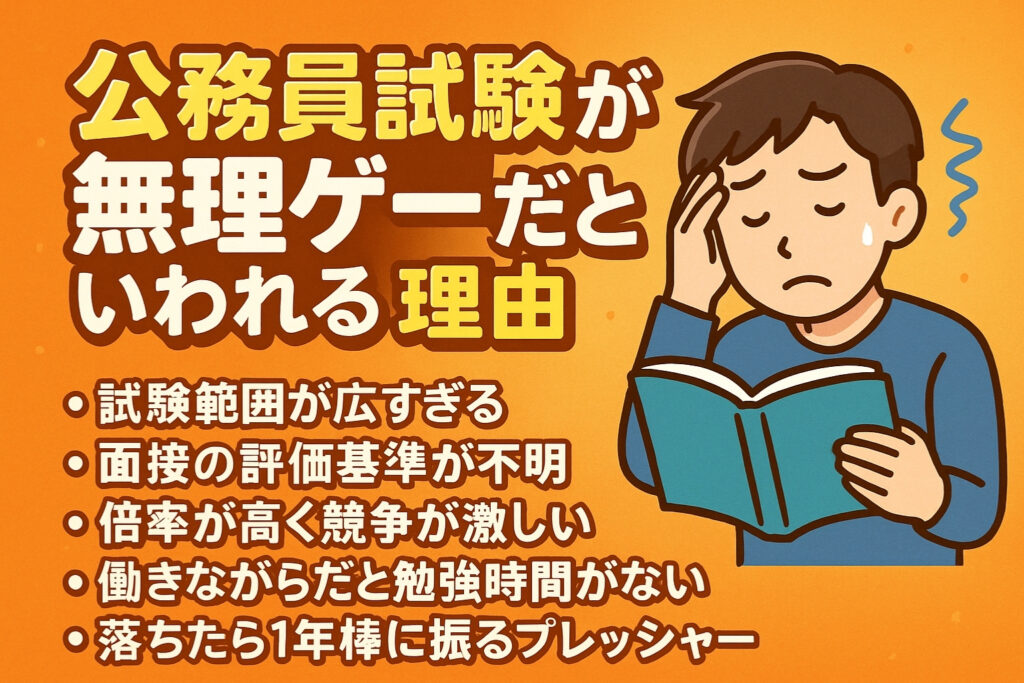
公務員試験が無理ゲーだといわれるのには、それなりの理由があります。
- 試験範囲が広すぎる
- 面接の評価基準が不明
- 倍率が高く競争が激しい
- 働きながら勉強時間が確保できない
- 落ちたら1年間棒に振るという強いプレッシャー
上記のような無理ゲーだといわれる理由をしっかりと理解しておけば、不安とどう向き合うべきかも見えてくるはずです。
試験範囲が広くて勉強が大変すぎるから
公務員試験の難易度が高く感じる大きな理由の1つは、試験範囲が非常に広いことです。
公務員試験で出題される内容を以下にまとめました。
| 文章理解 | 現代文 英文 古文 |
|---|---|
| 数的処理 | 判断推理 数的推理 資料解釈 空間把握 |
| 社会科学 | 政治 経済 法律 時事 |
| 自然科学 | 数学 物理 化学 生物 地学 |
| 人文科学 | 日本史 世界史 地理 文芸 思想 |
| 行政 | 政治学 行政学 社会学 国際関係 |
|---|---|
| 法律 | 憲法 行政法 民法 労働法 刑法 商法 |
| 経済 | ミクロ経済学 マクロ経済学 財政学 経営学 会計学 統計学 |
| 心理・福祉 | 心理学 社会福祉 教育学 |
| 技術 | 土木 建築 機械 電気 |
出題範囲や内容は選ぶ職種や試験によって異なり、全範囲を勉強する必要はありません。
しかしそれでも膨大な範囲をカバーしなければならないことは確かで、限られた時間で対策するのは困難を極めます。
闇雲にすべての範囲を網羅するのではなく、頻出部分に絞り、重要度の高い分野から優先的に手を付けることが、筆記試験攻略の第一歩となるでしょう。
 ミキサック
ミキサックちなみに、教養科目のみで受験できる「教養のみ」という受験区分もあります。詳しくは以下の記事で解説していますので、併せて読んでみてください。
面接の評価基準がわからないから
公務員試験の2次試験では面接が控えていますが、面接試験は多くの受験生が落とされる大きな関門です。
合格・不合格の基準がわからず、点数も公表されていないため、準備しても落ちてしまう人が後を絶ちません。
とはいえ、受験先の過去の質問傾向や合格者の体験談を分析することで、ある程度の予測と準備は可能です。
記事の後半に詳しく記載しますが、予備校やオンラインスクールの受講者であれば過去の受験生のデータを閲覧できたり、プロからの模擬面接が受けられるため、評価の見えない壁を乗り越えやすくなります。



とはいえ今はオンラインサービスが発達しているため、独学でも模擬面接だけ受けられるサービスも探せばあります。
倍率が高く競争が激しすぎるから
公務員試験が無理ゲーだと認知されるのは、受験生の数に対して合格する人数が少なすぎる(倍率が高すぎる)からです。
たとえば、2025年における大卒程度の皇宮護衛官は15.3倍、東京消防庁のⅠ類2回目は11.2倍など、10倍以上の倍率になる職種も多く存在します。
多くの受験者は、少なくともだいたい5〜8倍程度の倍率で競い合うという認識を持って試験に臨んだほうがよいでしょう。
しかし、倍率に怯えるよりも「自分ができることをどこまでやり切れるか」に意識を集中することで、他の受験生との差を広げられます。



倍率が高くても低くても、落ちる人は落ちます。倍率にとらわれず、合格に必要なことをやり切りましょう。
働きながらだと勉強時間が確保できないから
現在正社員で働いている人が転職で公務員試験を受けようとする場合、時間の壁は非常に高く感じられます。
1日8時間以上拘束されたあとに勉強時間を確保するのは物理的に難しく、疲れから集中力が持たないという人が多いのが現実です。
しかし、働きながらでも合格する人は存在しており、その人達はスキマ時間をうまく活用したり、疲れていても自分を奮い立たせて勉強したりと、間違いなく努力しています。
無理をして身体を壊しては元も子もありませんが、限られた時間をどう配分するかを見直し、無理のない計画を立てることで、時間の制約を言い訳にせずに対策を進められるでしょう。



社会人でも効率よく勉強する方法や、合格する方法を知りたい人は、以下の記事も参考にしてみてください。
落ちたら1年間棒に振るというプレッシャーが強いから
公務員試験は年に1回の採用が基本のため、一度落ちたら1年間は無職か、別の仕事に就いて過ごすことになります。
この強いプレッシャーが無理ゲーだと感じさせる大きな要因となっており、勉強中のメンタルにも大きく影響します。
しかし、試験日が被らないという前提になりますが、複数の自治体や職種を併願することで合格のチャンスを広げることも可能です。
視野を広げ、失敗しても軌道修正できる選択肢を事前に確保しておくことで、過度な不安を和らげることができるでしょう。



絶対に落ちたくない人は、ぜひ弊社のサービス「数的塾」の利用も視野に入れてみてください!
公務員試験に合格する人に共通する4つの特徴
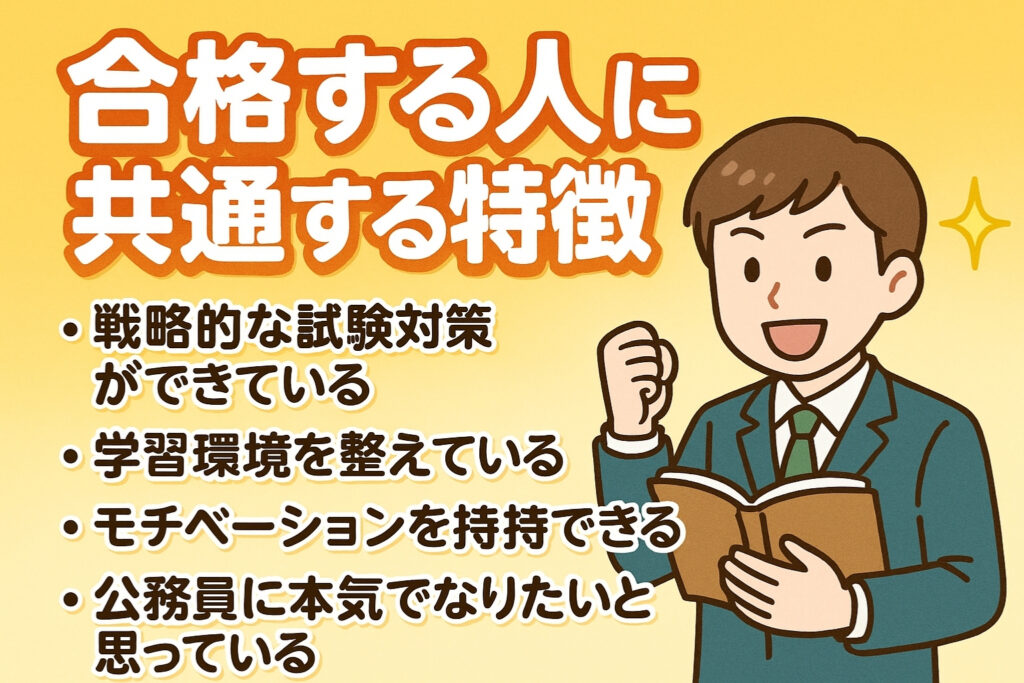
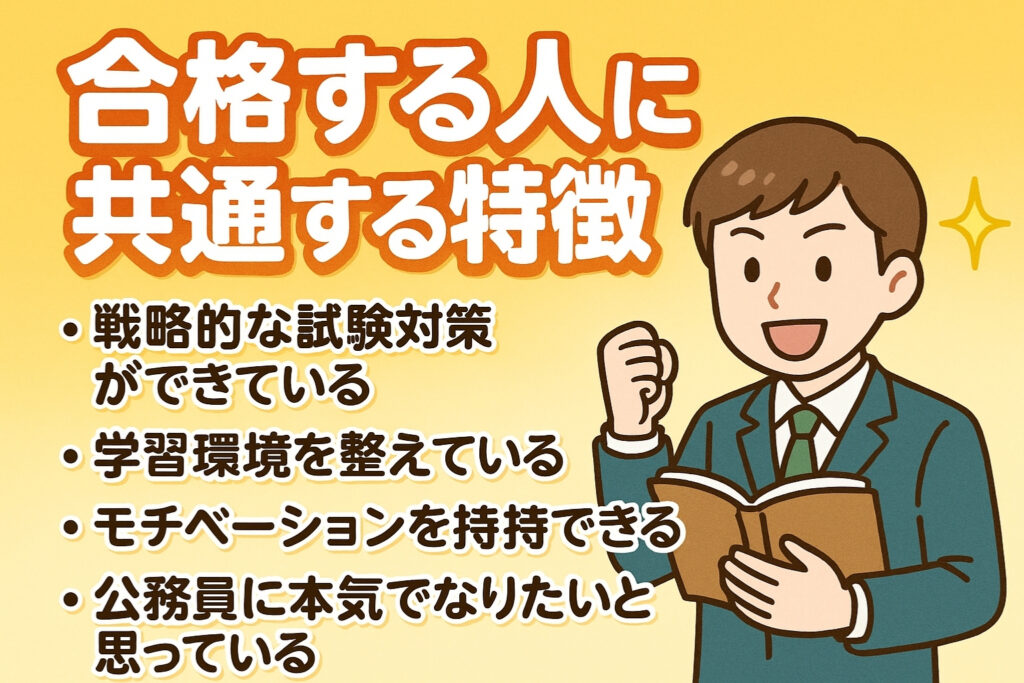
無理ゲーともいわれる公務員試験に合格する人には、共通点があります。
- 戦略的な試験対策ができている
- 学習環境を整えている
- モチベーションを維持できる
- 公務員に本気でなりたいと思っている
決して運が良かったわけではなく、上記のような要因が積み重なり、初めて合格という結果が生まれています。
自分に足りないものが何かを確認するためにも、それぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。
戦略的な試験対策ができている
公務員試験に受かる人は、例外なく戦略的に勉強しています。
以下に、戦略的に試験対策をしている人が心がけていることをまとめました。
- 出題頻度の高い科目を優先する
- 得点源になりやすい分野に集中する
- 得点効率を考えて捨て科目を作る
戦略的な試験対策をするには、まずは過去問でどの科目のどの部分が頻出なのかを理解することが不可欠です。
膨大な試験範囲を有効的に狭めて学習することで、合格するために必要な勉強時間を大幅にカットしています。
戦略的・効率的に対策するためにも、まずは出題傾向を知ることが重要です。



捨て科目の作り方や、効率的な勉強方法を知りたい人は、以下の記事も参考にしてみましょう。
学習環境を整えている
合格者の多くは、集中できる学習環境を意識的に作っています。
家で勉強に集中できないなら、図書館や自習室、カフェなどを活用するなど、場所に工夫を凝らしている人が多いでしょう。
また、スマートフォンの通知を切ったり、使う教材を厳選したり、勉強時間や学習内容を記録したりなど、できることはたくさんあります。
勉強そのものの内容ばかりに気を取られがちですが、1番重要なのは集中力をいかに維持するかです。
集中力がなければ勉強した内容が頭に入りませんし、記憶の定着にも悪影響を及ぼします。
学習内容と同じかそれ以上に、学習環境は合否に関わる大きな要因になります。



机の上を掃除したり、アロマを炊いたりと、部屋内の環境を変えるだけでも勉強のしやすさはガラッと変わりますよ!
モチベーションを長期間維持できる
公務員試験対策は、半年から1年と長期にわたる戦いです。
合格者はその期間において自分のやる気をどう維持するかの重要性に気づいている人が多く、さまざまな工夫を凝らしてモチベーションの維持を図っています。
モチベーションを維持する方法が思いつかない場合は、以下のことを試してみましょう。
- 週ごとに小さな目標を設定し、手帳やアプリに達成度合いを記録する
- 目標を達成するごとに自分にご褒美を与える
- SNS等を通じて他の受験生と進捗を共有する
1人で試験対策をしていると、さまざまな誘惑に飲まれてしまい、つい勉強をサボってしまいがちです。
自分が日々成長していることを実感したり、仲間と切磋琢磨したりすれば、自ずとモチベーションは湧いてきます。



試験日までの長期戦を戦い抜くためにも、モチベーションを維持する方法はいくつか持っておきましょう。
公務員になりたいという思いが強い
合格する人に共通するもっとも大きな要素は、「絶対に公務員になりたい」という強い意志です。
動機の強さは面接でも評価されますし、前述したモチベーションの維持にもつながります。
強い思いは、勉強がツラくなったときに自分を支える、精神的な柱になるでしょう。
逆に「なんとなく安定していそうだから」という中途半端な思いでは、途中で頑張る意味を見いだせなくなって挫折してしまったり、面接で熱意が見えずに落とされてしまったりします。
筆記試験の点数が良かったとしても、最終的には「この人と働いてみたい」と思わせられなければ落ちてしまうため、人間力が大きく現れる「思いの強さ」が、自分のどの部分にあるのかを今一度確認してみましょう。



面接官の立場で考えても、本当に熱意を持って仕事をしてくれる人と一緒に働きたいですよね!
比較的合格しやすい?倍率が低めの公務員試験を紹介
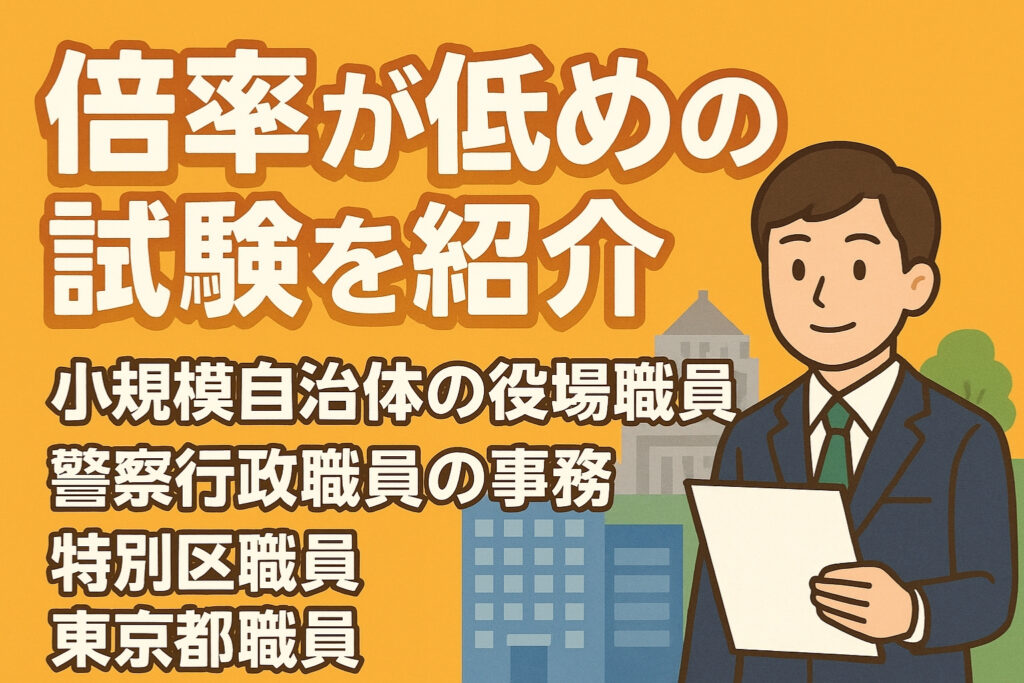
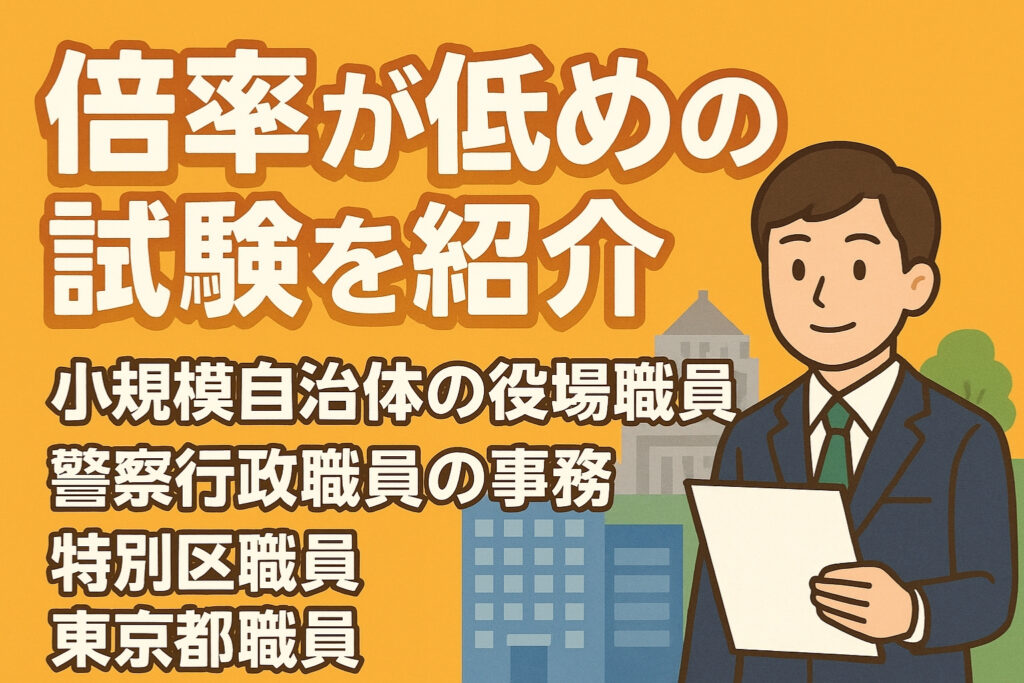
公務員試験はどれも難しすぎると感じている人にとって、少しでも合格の可能性を上げるために、倍率の低い試験を狙うことは有効な戦略の1つです。
本章では、比較的倍率が低い職種をご紹介します。
受験先に迷っている人は、ぜひ参考にしてみてください。
小規模な自治体の市町村役場職員
小規模な自治体の役場職員は、都市部に比べて志望者が少なく、倍率が低くなる傾向にあります。
当然採用予定人数も少ない可能性があるため、必ず過去の試験結果を確認しておきましょう。
主な仕事内容を以下にまとめました。
- 住民票・戸籍・印鑑証明などの窓口対応業務
- 国民健康保険や介護保険、年金などの手続き案内・受付
- 地域住民からの相談対応(福祉・税・生活全般など)
- 公共施設の管理・運営(体育館、図書館、集会所など)
- 地域イベントやお祭りの企画・運営(夏祭り、防災訓練など)
- 税務業務(町民税、固定資産税などの徴収・案内)
- 広報誌の作成やホームページの更新
- 道路・河川などのインフラに関する簡易な維持管理・住民対応
- 議会対応や会議資料の作成、議事録作成
小規模な自治体の役場職員は、少人数で幅広い業務を担当することが多く、何でも屋的な役割を求められるケースが多々あります。



ジェネラリストとしての対応力や、地域との信頼関係を築く力が求められるでしょう。
警察行政職員の事務
警察官ではなく、警察の行政職員の採用試験も、比較的倍率が低くて狙い目の1つです。
配属先は警察本部や警察署になりますが、通常の警察官と違って体力試験がなく、一般的な公務員試験と内容は変わりません。
主な業務を以下にまとめました。
- 人事・給与関連の事務(人事異動、勤務管理、俸給計算など)
- 予算編成・執行・経理処理(物品購入、旅費精算、決算業務など)
- 物品や装備品の管理(制服、無線機、備品の発注・管理など)
- 住民からの各種届出の受付・案内(遺失物、拾得物など)
- 運転免許に関する書類整理・窓口対応(※一部都道府県)
- 交通事故統計や犯罪データの入力・集計・報告
- 防犯広報資料の作成やイベント準備
- 会議資料の作成・ファイリング・報告書作成
- 庁舎の維持管理や庶務業務(清掃業者の手配、電気・水道の管理など)
- 警察署内での電話・窓口応対(警察官への取次など)
日本で1番大きな警察組織の1つでもある警視庁の倍率を見ても、令和6年度試験のⅠ類で2.8倍と、倍率は低くなっています。



ただし、Ⅲ類は倍率が高かったり、年によってはどの区分でも高倍率になることがあったりと、難易度のばらつきはあるため注意は必要です。
特別区職員
東京都の23区職員として勤める特別区職員は、毎年採用人数が多いため、意外にも倍率は低くなりがちな試験です。
一般事務だけでなく、ICT(情報通信技術)事務、土木や建築などの技術系、心理・福祉系など、あらゆる職種で倍率が低く、およそどの年の倍率も1.5〜3倍程度となっています。
主な業務内容を以下にまとめました。
- 国民年金、健康保険の相談・手続き
- 高齢者・障害者・ひとり親家庭への支援
- 住民票、戸籍、印鑑証明などの交付
- 住民からの各種届出の受付・案内(遺失物、拾得物など)
- マイナンバーカードの交付・更新
- 生活保護の申請・ケースワーク
- 引越しや転入・転出届の受付
- 道路、公園、公共施設の整備・維持管理
- 補助金・助成金の処理
- 保育園・幼稚園の入園申請対応、待機児童対策
- 選挙管理(投票所運営、広報など)
職場は区役所本庁舎をはじめ、保健所や子ども家庭支援センター、高齢者施設など、選ぶ職種によってさまざまです。



近年ではDX化を推進していることもあり、ICTの募集が特に多くなっています。
東京都職員
東京都職員も、受験者は多いのですが採用人数が多いため、倍率が低くなりがちな試験の1つです。
事務を含めた一般行政職はもちろん、土木などの技術系職員も、倍率が低くなっています。
年によってはⅢ類試験の事務職の倍率が高めのことがあるため、不安な人はチェックしておきましょう。
主な仕事内容を以下にまとめました。
- 高齢者福祉、障害者支援、生活困窮者支援、児童福祉政策の企画と実施
- 都立福祉施設・児童養護施設の運営
- 保健所・精神保健センターの管理
- 都市計画、再開発、交通政策(例:地下鉄・環状道路整備)
- 公共インフラ(道路・河川・港湾・下水道など)の整備・管理
- 地球温暖化対策(カーボンゼロ東京戦略など)
- 廃棄物・リサイクル政策の推進
- 自然保護、緑化推進、公園管理
勤務地は東京都庁をはじめ、23区内の出先機関や、都立の学校施設など、職種によってさまざまです。
公務員試験を「無理ゲー」から「勝てる試験」に変える方法
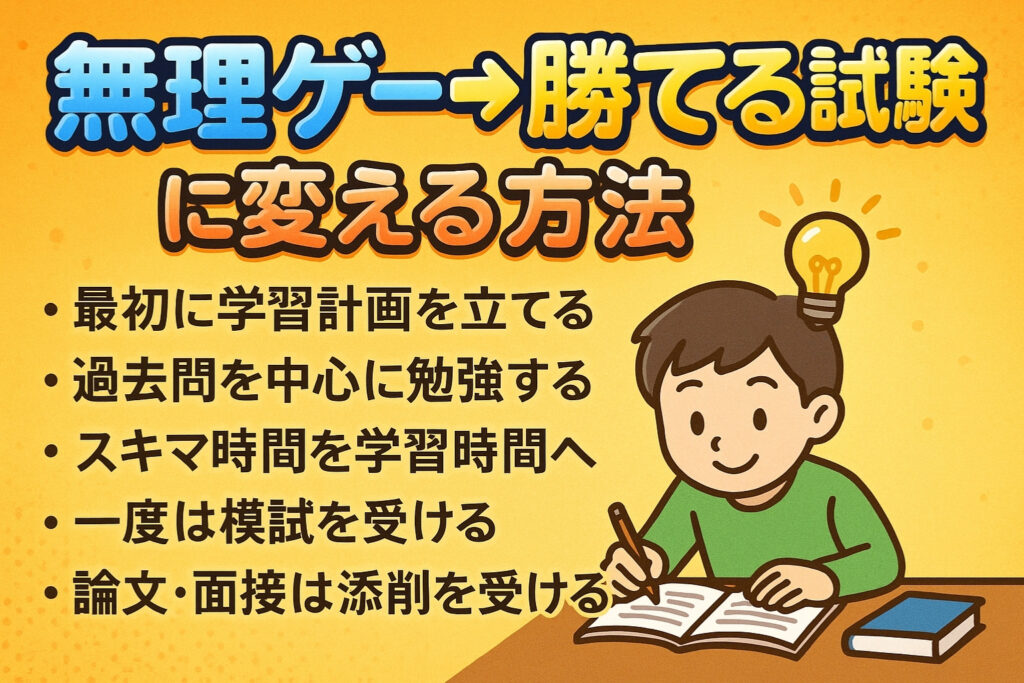
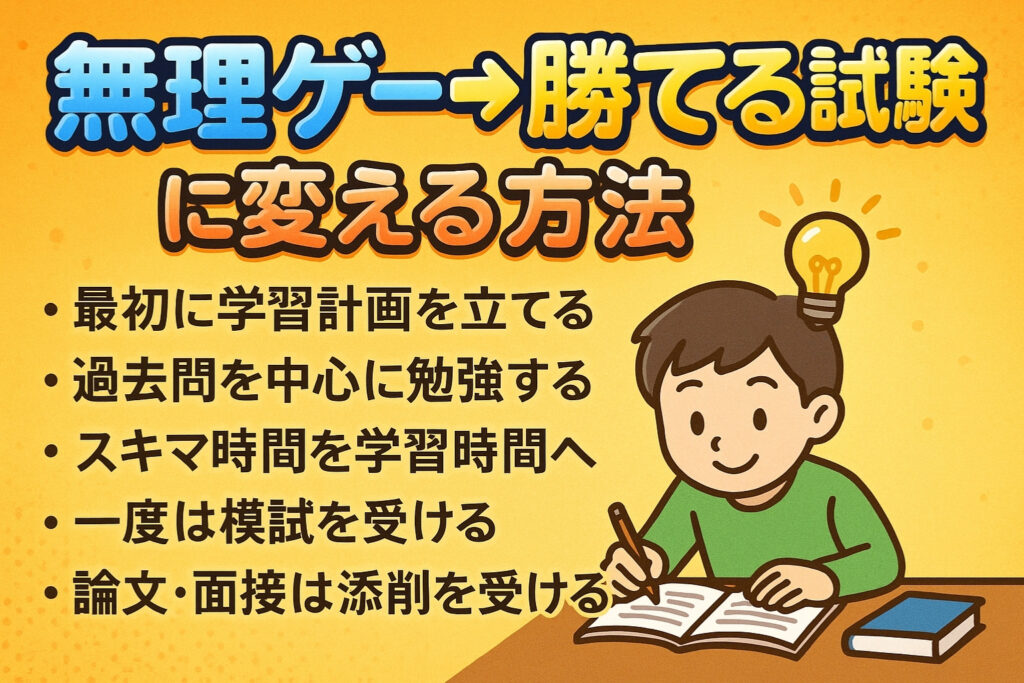
公務員試験は、確かに無理ゲーだと感じてしまう要素がいくつもありますが、正しい方法で取り組めば「勝てる試験」に変えることができます。
多くの合格者は、決してもとからある能力で運良く突破しているわけではなく、再現性のある勉強法と行動を積み重ねているのです。
- 最初に学習計画を立てる
- 過去問を中心に勉強する
- スキマ時間を学習時間に充てる
- 一度は模試を受ける
- 論文・面接対策は第三者からの添削を受ける
上記のような当たり前のようで見落としがちなポイントを実践することが、合格への大きな一歩となります。
具体的な実践方法を見ていきましょう。
必ず最初に学習計画を立てる
公務員試験対策を始める際には、まず全体の学習計画を立てることが最も重要です。
範囲が膨大なため、無計画に取り組むと途中で挫折してしまいかねません。
具体的には、試験日から逆算し、月単位・週単位で「何を・いつ・どのくらい」学習するかを明確にします。
最初の1ヶ月は数的処理や文章理解、社会科学など頻出部分に集中し、その後は全体の得点を伸ばすために専門科目や苦手分野に取り組むなど、進捗に応じた柔軟な計画を立てるのが理想です。
また、計画を可視化することで、自分が今どこまで進んでいるのか、何が足りないのかがわかり、モチベーションの維持にもつながります。
いきなり勉強を始めるのではなく、まずは全体の指針を決めてから試験対策に取り組みましょう。



予備校やオンラインスクールも、カリキュラムが組まれていますよね。学習計画を立てるというのは、カリキュラムを組むことと同じです。
過去問を中心に勉強する
公務員試験対策において、もっとも効率的かつ効果的な勉強法は、過去問を中心に勉強することです。
なぜなら、毎年出題傾向に一定のパターンがあり、似たような問題が繰り返し出る傾向が強いからです。
過去問を繰り返すことで、出題意図や問題の形式になれることができます。
当然、過去問だけやっていても学力は伸びませんから、わからない部分を参考書で確認し、応用力を付けるために問題集を解く、という順番で学習しましょう。
不合格になる受験者の多くが、参考書で知識を付けるところから始めてしまい、合格のために必要ない知識を付けがちです。
必ず「過去問→参考書→問題集」の順番で勉強しましょう。



過去問は最低でも過去5年分を解いておきたいところです。
スキマ時間を学習時間に変える
勉強時間が足りないと感じる人ほど、スキマ時間の活用ができていません。
スキマ時間を学習時間に充てられれば、1日で多くて2時間程度も学習時間が増やせます。
- 朝早く起きて通勤・通学前に30分
- 電車やバス内に15分(往復)
- 昼休みのうちに30分
- 就寝前に30分
まとまった時間でなくても、アプリを使って時事問題を確認したり、単語帳などで暗記をしたり、Youtubeで解説動画を見たりと、できることはたくさんあります。
スキマ時間は積み重ねれば大きな差となりますので、時間の使い方を見直し、効率よく学習しましょう。



スキマ時間をダラダラと娯楽に費やすのはNGです!公務員試験合格に必要な勉強時間は約800〜1,000時間。少しでも勉強時間を確保しましょう。
一度は必ず模試を受ける
筆記試験でちゃんと点数を取りたいなら、一度は模試を受けるべきです。
自分の現在地を客観的に把握できますし、本番さながらの環境で緊張感や適切な解答速度を掴むことができます。
どれだけ家で過去問・問題集を解いていても、自宅環境では本番のような集中や制限時間による緊張感は得られません。
模試では時間配分・問題の取捨選択・集中力の持続といった技術的な部分が試されるため、事前に体験しておくことは大きなアドバンテージになるでしょう。
模試の結果をもとに弱点を把握し、改善していく過程をたどることで、合格に向けたより高精度の対策ができるようになります。



模試は独学の人でも受けられるサービスがあります。気になる人は自分で探してみましょう。ちなみに、「数的塾」でも受講者向けに実施しています。
論文・面接試験対策は第三者の添削を受ける
論文対策や面接対策は、1人で行うには限界があります。
というのも、自分では意識していないクセや論理の飛躍など、評価に直結する部分に気付きづらいからです。
論文では文章の書き方1つ、面接では伝え方1つで、与える印象が大きく変わります。
そこで、指導者や経験者による正しいフィードバックを受けられれば、客観性を高めつつ自分の強みを伸ばしていけるようになるでしょう。



もし本気で合格したいと思うなら、手軽に受講できて講師陣のサポートも手厚い「数的塾」の入会も視野に入れてみてはいかがでしょうか。
どの学習方法にするか迷っている人のためのチェックポイント
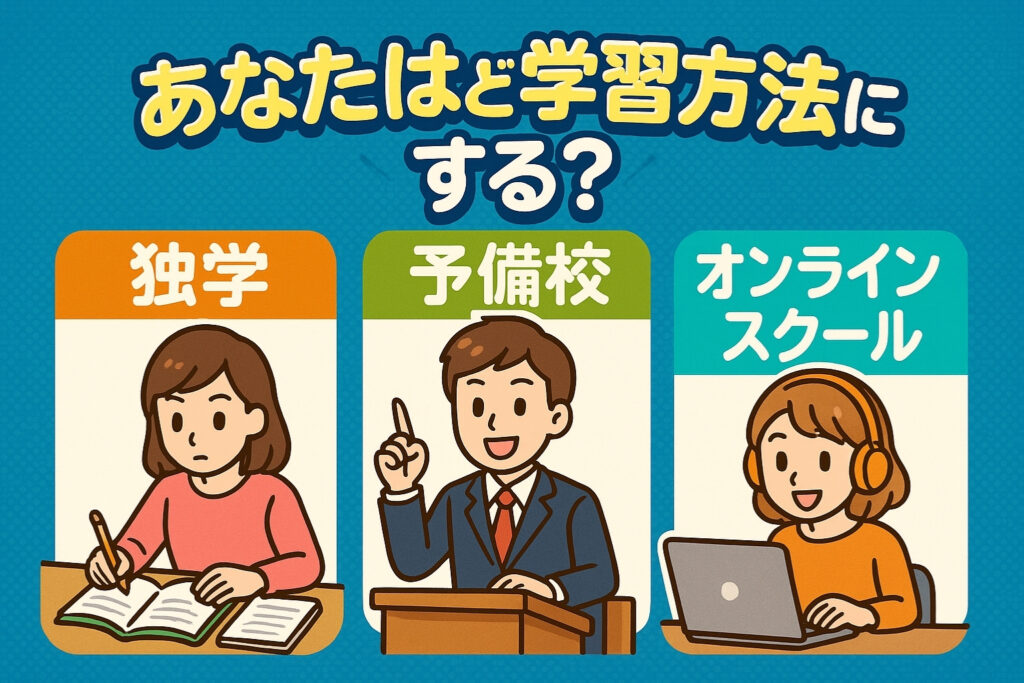
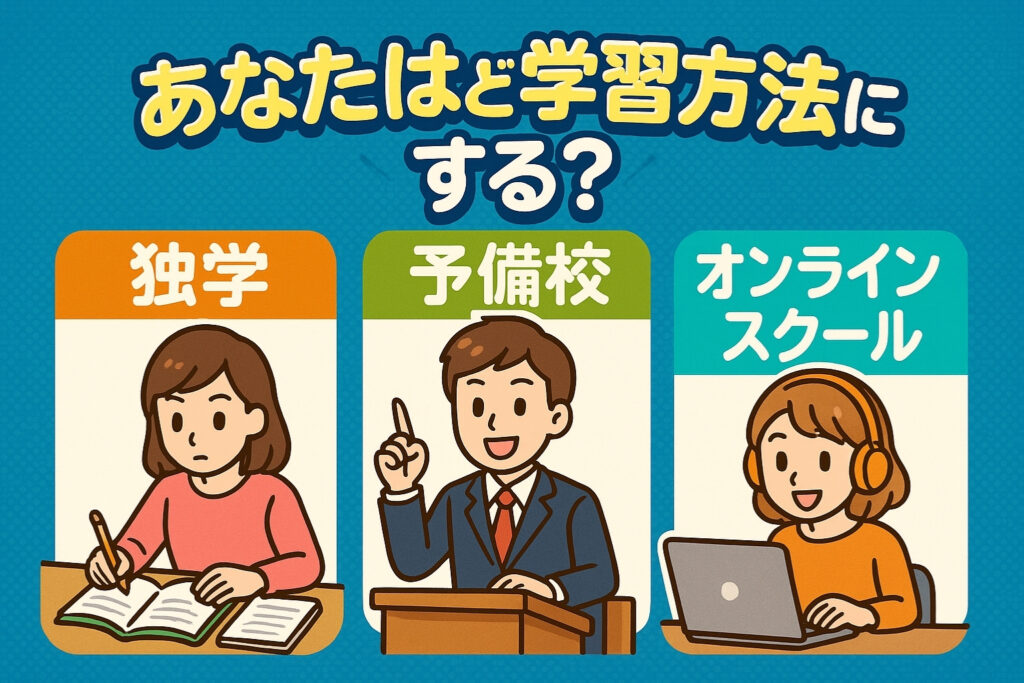
公務員試験の勉強方法は、大きく分けて「独学」「予備校」「オンラインスクール」の3種類があります。
自分に合ったスタイルを選べないと、途中で挫折してしまったり、自分の選択を後悔してしまったりすることも。
どれが正解というわけではなく、それぞれにメリット・デメリットがあり、受験者の性格や生活環境によって最適解は異なります。
それぞれの学習方法がどのような人におすすめなのか、具体的に見ていきましょう。
独学がおすすめの人
独学が向いているのは、自分で徹底したスケジュール管理ができ、学習内容を取捨選択できる人です。
金銭的な負担が少なく、自分のペースで勉強できるというメリットはありますが、モチベーションの維持や進捗管理、情報収集などをすべて自分自身で行わなければならず、孤独との戦いになります。
甘えずに1人でも粘り強く進められる人、すでにある程度の受験知識がある人、時間的余裕がある人には適した方法と言えるでしょう。



独学でも合格は十分可能ですが、サボると一気に不合格真っしぐらとなるので注意しましょう!
予備校がおすすめの人
予備校は、公務員試験合格に特化したカリキュラムが組まれており、勉強のペースを自動的に作ってくれる点が魅力です。
講師に直接質問できる環境や、模擬面接・論文添削などのサポートも充実しており、初学者でも安心して学習を進められます。
同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨できるため、モチベーションも維持しやすいでしょう。
一方で費用が高額で、通学時間が必要等のデメリットもあります。
「絶対に合格したい」「強制力のもと勉強を管理してほしい」という人には最適ですが、予算や生活スタイルとのバランスを考慮しましょう。



予備校は効率と時間を買う手段ですね!大きな安心感を得たい人には強くおすすめします!
オンラインスクールがおすすめの人
オンラインスクールは、独学の良さを持ちつつも、試験対策のサポートを受けつつ効率的な学習がしやすいことが最大のメリットです。
通学不要で、社会人や地方在住者でも続けやすく、費用も予備校と比べて安価に抑えられます。
一方で学習がある程度自己責任になるため、自主学習が苦手な人には向かない場合も。
独学よりもサポートが欲しいけれど、通学は厳しいという人には、1番バランスの良い選択肢となるでしょう。



オンラインスクール選びに迷ったら「数的塾」がおすすめです!オンラインスクールのデメリットでもある学習管理のしづらさや、疑問点の解消のしづらさを感じさせないサポートが付いています。まずは無料相談をしつつ、今だけ無料の試験対策ガイドも受け取ってみましょう!
\数的塾の限定講義&合格ガイド無料配布中/
まとめ
公務員試験は無理ゲーだといわれることも多いですが、実際には戦略的に対策を進めることで、確実に勝てる試験へと変えることが可能です。
今回の記事で紹介した、合格のために必要なポイントをまとめました。
- 合格者に共通する特徴は、戦略的な対策法を行っているか、学習環境の整備をしているか、モチベーション維持を工夫できるか、公務員になる強い熱意があるかどうか
- 比較的倍率の低い試験には、小規模自治体の市町村役場、警察事務、特別区職員、東京都町職員などがある
- 勝てる試験に変えるポイントは、学習計画を立て、過去問から勉強を始め、スキマ時間を活用し、模試を受けつつ、添削指導を受けること
- 自分に合った学習スタイルを選ぶこと
もし現在「勉強のやり方が合っているか不安」「何から手を付ければいいのかわからない」という悩みを抱えている場合は、以下のリンクから「数的塾」をLINEで友だち登録してみましょう。
今なら無料で効率的な勉強方法が記されたガイドブックがもらえます。
まずは無料相談から受け付けていますので、気になった方はぜひ利用してみてはいかがでしょうか。
\数的塾の限定講義&合格ガイド無料配布中/

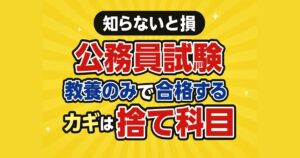
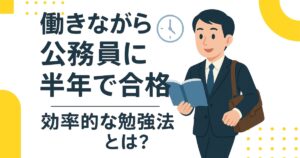
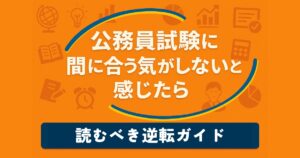

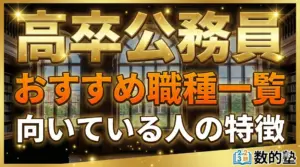
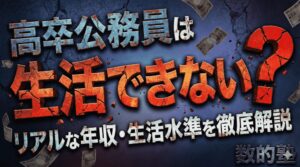


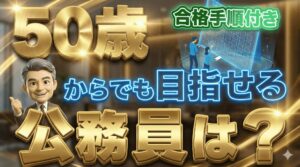
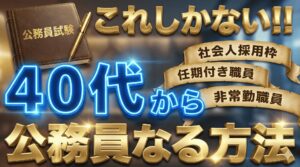


コメント