 ミキサック
ミキサックオンライン×最短で公務員試験合格を目指せる「数的塾」を運営しているミキサックです!
「地方公務員は安定している」とよくいわれますが、実際には生活が苦しいのではないかと不安に感じている人も多いでしょう。
実際に若手の給与水準は決して高くなく、住宅費や車の維持費を支払うと、なかなか貯金ができないケースもあります。
そこで今回の記事では、実際に地方公務員がどのくらい稼げるのか、初任給や年収について、他業種との比較もしながら解説していきます。
給与についての不安をなくし、気持ちよく試験に臨みたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
\数的塾の限定講義&合格ガイド無料配布中/
地方公務員の初任給と年収はいくら?


総務省が令和5年に発表した「地方公務員給与実態調査」によると、地方公務員(一般行政職)の平均初任給(地域手当等を除く本給)は以下のとおりです。
| 団体区分 | 大卒平均初任給 | 高卒平均初任給 |
|---|---|---|
| 都道府県 | 190,966円 | 158,332円 |
| 政令指定都市 | 186,699円 | 154,980円 |
| 市 | 187,673円 | 156,993円 |
| 町村 | 185,609円 | 155,554円 |
上記の金額から、地域手当等の諸手当が付くため、実際の額面はもっと高めになります。
続いて、年齢別の推定平均年収を以下の表にまとめました。
- 20代前半:約300万〜350万円
- 20代後半:約350万〜430万円
- 30代:約430万〜530万円
- 40代:約530万〜640万円
- 50代:約650万円前後
以上でご紹介した初任給や推定年収をもとに、昇給や手当の種類についてより詳しく知り、他業種との比較もしていきましょう。
昇給の仕方やペースについて
地方公務員の給与は、地方公務員法に基づき、各自治体の条例によって定められており、「級」と「号」と呼ばれる仕組みによって決まります。
- 級:職務のレベル(昇格の対象)
- 号:同じ級の中での段階(昇給の対象)
採用時は1級から始まるのですが、年に一度、勤務成績や勤続年数に応じて号が上がり、それに伴って月給が少しずつ増えていく流れです。
昇給幅は月数千円から1万円程度と緩やかで、正直なところ、20代から30代にかけてはそこまで裕福な生活はできないでしょう。
しかし、40代以降になると役職手当や勤続加算によって収入も増え、安定した生活ができるはずです。



ちなみに、号は20号まであるので、役職を上げなくても給与はある程度伸ばせます!
もらえる手当について
地方公務員は、基本給に加えて様々な手当を受け取れる点が特徴です。
代表的な手当を以下にまとめました。
- 地域手当:勤務地の物価・生計費等を踏まえて補正する手当。特別区など都市部では支給割合が高めに設定される
- 扶養手当:配偶者・子などの扶養親族がいる職員に支給
- 住居手当:賃貸等で住居費を負担している場合に支給
- 通勤手当:公共交通機関や自家用車での通勤費用を補填
- 時間外勤務手当(超過勤務手当):所定労働時間外の勤務に対する手当。関連して休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当などもある
- 期末手当・勤勉手当(ボーナス):期末・勤務成績等に応じ、年2回等で支給する賞与的手当
- 管理職手当:課長級以上など管理職の職責に応じて支給
- 寒冷地手当:寒冷地での燃料等の季節的負担を補う手当(対象地域の条例に規定)
もらえる給与額のうち、手当が占める割合は数万円にものぼるため、生活を支える大きな要因となります。
前述した「地方公務員の初任給」だけ見ると、生活が苦しくなりそうな気がしてしまいますが、手当によって実際の額面はさらに増えるのが実態です。



特に地域手当の存在は大きく、特別区(東京23区)では基本給の20%が支給されます!一方で、地方の小規模都市では4%、地域手当の支給がそもそもない地域もあるため、勤務地によって生まれる給与差は大きいですね。
国家公務員や民間企業との差について
総務省や人事院、国税庁が発表する資料をもとに、地方公務員と国家公務員、民間企業の平均推定年収を以下にまとめました。
- 地方公務員:約600万円
- 国家公務員:約670万円
- 民間企業平均:約530万円
全年齢層のデータではありますが、民間企業と比べると、地方公務員でも十分に高い年収が得られるという結果でした。
基本的に国家公務員よりも給与は低めですが、一部の特別区(千代田区、中央区、大田区)や、一部の政令指定都市(北九州市、福岡市、川崎市、神戸市)では、国家公務員よりも平均給与が高くなっています。
給与の高い自治体で働けば、生活が苦しいと感じてしまうことはないでしょう。



大雑把なイメージとして、地方公務員の給与は、大企業や国家公務員よりかは少なく、中小企業よりは高いというイメージをもっていただければ大丈夫です!
地方公務員の生活が苦しいといわれる理由を解説


地方公務員の生活が苦しいといわれる理由は、主に以下の4つの要素が原因です。
- 若手のうちは給与が少なめだから
- 部署によっては残業代がつきにくいから
- 働く自治体によってもらえる給与が大きく異なるから
- 副業の制限があって自由に収入を増やせないから
それぞれの原因について、詳しく見ていきましょう。
若手のうちは給与が少なめだから
地方公務員の給与体系は年功序列が基本であるため、20代のうちは手取りが20〜25万円程度になる場合が少なくありません。
家賃7万円、食費2.5万円、光熱費1.5万円、交際費2万円、雑費3万円を毎月負担するとしたら、貯金できるのは毎月多くても5万円程度でしょう。
20代後半から30代にかけては年収も伸びてきて少し余裕が出てきますが、それまでは「安定してはいるが余裕はない」という現実に直面してしまいます。



所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などが差し引かれるため、額面はけっこうもらっていても、実際の手取りはかなり少なく感じると思います…
部署によっては残業代がつきにくいから
公務員の収入は、残業の有無によっても大きく左右されます。
ほぼ定時に仕事が終わる部署では残業代がほとんど付かない一方、福祉や各種手続き、建設関連、子育て関連の窓口業務は、繁忙期に残業することが多く、年収が数十万円単位で変わることも。
残業代の計算方法を以下にまとめました。
超過勤務手当 =「勤務1時間当たりの給与額」×「支給割合」×「超過時間」
1時間当たりの給与額 =(給料月額 + 地域手当 ほか基礎手当)× 12 ÷(週の所定勤務時間 × 52)
支給割合:平日残業1.25倍、休日1.35倍、深夜はプラス0.25倍、月60時間超は1.5倍(深夜1.75倍)
※ただし、細部は自治体ごとの条例・規則で少しずつ異なる
残業代には基本的に上限が設けられており、月45時間・年360時間となっています。



残業は決して多くないため、残業が嫌で早く帰宅したい方にとってはメリットですが、少しでも稼ぎたい方にとってはデメリットに映ってしまうかもしれませんね。
働く自治体によってもらえる給与が大きく異なるから
本記事の前半部分でも軽く触れましたが、働く自治体によって地域手当の多寡に大きく差があったり、規定の給与も都市部の方が高く設定されていたりするため、どうしても勤務地によって給与に差が生まれてしまいます。
特別区や政令指定都市で働く方は給与が多くなりますが、地方の町村で働く方は都市部と比べて月額給与が数万円低くなるケースがほとんどです。
当然、都市部は生活費のコストが高いというデメリットはありますが、それでも給与面で言えば都市部で働いた方が苦しさを感じづらい可能性があります。



都市部でも食費を抑えたり、交際費を抑えたりすれば、家賃以外はいくらでも負担を少なくできますからね。
副業の制限があって自由に収入を増やせないから
地方公務員は、地方公務員法によって副業に規制がかけられており、民間企業で働く方と比べて副収入を得られないため、生活が苦しいと感じてしまう方もいるでしょう。
しかし、不動産収入や、株式・投資信託などの資産運用、さらに許可制ではありますが、執筆や講演活動など、一部例外的に副収入を得られる方法はあります。
とはいえ、民間企業に勤めながら新たなスキルを得て、個人事業も行うという稼ぎ方はできませんので、日々の生活を節制するか、資産運用で対応するしかありません。



安定している反面、自由度が低い点は公務員の大きな制約ですね…
地方公務員として働くメリット4選


地方公務員は「給料が安くて生活が苦しい」と言われがちですが、その一方で、働くうえでさまざまなメリットが存在します。
公務員になろうか迷っている方は、メリットを知ることで目指すための一歩を踏み出す勇気が生まれるはずです。
雇用と給与が安定している
地方公務員は雇用が安定しており、犯罪を犯すなどイレギュラーなことがないかぎり、解雇されるリスクはほぼありません。
さらに景気が悪化しても給与が大きく減ることはなく、毎月安定した額が支払われます。
コロナ禍やリーマンショックなど、民間企業が大打撃を受けるような経済ショックが起きた際にも、安心して働き続けられるというのは、非常に大きなメリットです。



ライフプランが立てやすく、結婚や住宅購入といった将来の大きなイベントにも安心して備えられますね!
福利厚生が手厚い
地方公務員は共済組合に加入しており、医療や年金に関して一般的な会社員よりも優遇されています。
例えば、医療費の自己負担割合が軽減される制度や、傷病手当金・休業補償の仕組みが整っているため、もし病気やケガで働けなくなった場合でも収入が途絶えにくい環境です。
さらに、住居手当や扶養手当、退職金制度なども充実しており、ライフステージに応じた支援を受けられます。



住居手当等の諸手当も充実していますし、生活におけるサポートが充実しているところは公務員としての大きなメリットですね!
社会的信用度が高い
地方公務員は雇用と給与が安定しているため、社会的信用度が非常に高い職業だと判断されます。
特に住宅ローンやクレジットカードの審査、賃貸契約等の場面においては、公務員であることが有利に働くでしょう。
また「あの人は安定した仕事に就いている」と、他人からの評価も高くなることが多く、公務員という肩書そのものが、日常生活に多くのメリットをもたらします。



結婚時には、パートナーの親御さんからも安心してもらえるんだなあと、友人の話を聞いても感じました。個人的に、田舎だと特にその傾向が強い感覚があります。
転勤がない
地方公務員は、原則として採用された自治体以外の地域に転勤することはありません。
3〜4年で異動がありますが、採用された自治体内でのみ行われます。
住環境に変化がないということは、住宅購入が気兼ねなくできたり、近場の人間関係を維持できたりと、暮らしやすさを守るうえでは非常に大きなメリットです。



ちなみに派遣や出向など、ごく一部例外はありますが、全員がするものではないため、そこまで心配はいらないでしょう。
地方公務員として働くデメリット2選


地方公務員は、さまざまな面で安定しているというメリットがある一方で、実際に働く中で「ここは不満だ」と感じやすい点もわずかに存在します。
デメリットも理解しておけば、働き始めてからのミスマッチを減らせるはずです。
具体的にどのようなデメリットがあるのか、詳しく見ていきましょう。
若いうちから大きく稼ぐのは不可能
地方公務員の給与体系は年功序列であり、20代や30代前半で年収600万円を超えるといったスピード出世はありません。
一方で、成果主義の民間企業では若くして大きなプロジェクトを任されることもあり、年収が急増することもあります。
この差は「周りの人よりも稼ぎたい」と考える人にとっては大きな不満につながるでしょう。
つまり、公務員は長く勤めれば安定的に収入が上がるものの、若手時代に余裕のある暮らしを実現するのは難しいと言えます。



管理職に昇進するまでは昇給額もそこまで高くないため、人によってはモチベーションの低下につながってしまうかもしれません。
税金で働いているくせにと言われがち
地方公務員は公費で給与が支払われているため、一部の人から「税金で食べている」という目線を向けられることがあります。
特に景気が悪化して民間の給与が下がる時期には「公務員は安定していてズルい」「ノルマもないくせに楽して稼いでいる」「給料が高すぎる」といった批判を受けることも少なくありません。
とはいえ、上記のような心無い意見は基本的にただの嫉妬であることが多いため、ほとんど気にする必要はないでしょう。



窓口業務を担っている場合は、直接地域住民から嫌味を言われるケースもあるため、心理的負担がかかる可能性があることは知っておいた方がよいですね…
まとめ
地方公務員の生活は、若手時代はなかなか裕福に過ごせない一方で、徐々に給与も上がってき、安定して稼げるため、決して苦しいものではありません。
生きていくうえで「安定」は多くのメリットをもたらしてくれるため、毎年多くの方が地方公務員を目指すのも納得ですね。
ただし、人気の職業ということは当然倍率も高く、試験に合格するのは簡単ではありません。
もし「独学で合格できるか不安…」「少しでも合格できる確率を上げたい」と考えている方は、以下のリンクから無料で試験対策ガイドを入手してみましょう。



LINEで「数的塾」の公式アカウントを友だち登録するだけで入手できます!今後配布を終了する可能性もありますので、今のうちにゲットしておきましょう!
\数的塾の限定講義&合格ガイド無料配布中/


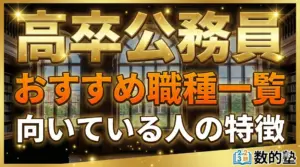
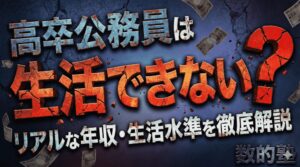


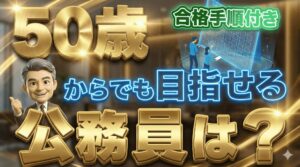
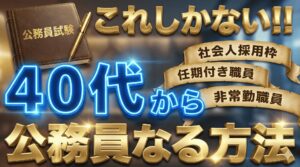


コメント