 ミキサック
ミキサックオンライン×最短で公務員試験合格を目指せる「数的塾」を運営しているミキサックです!
独学で国家総合職の教養区分を受験しようと考えている方の多くは、「本当に自力で合格できるのだろうか」「予備校に通わないと不利ではないか」と不安を抱えていることでしょう。
結論から言えば、独学でも十分に合格は可能です。
とはいえ、対策することが多く、完全に独学で合格するのは困難なこともまた事実。
そこで今回の記事では、教養区分の試験制度や内容を丁寧に整理し、独学で効率よく学習するための戦略を解説していきます。
正しい知識と計画を持てば、不安は自信に変わり、合格に向けて突き進んでいけるはずです。
\数的塾の限定講義&合格ガイド無料配布中/
まずは国家総合職の教養区分とは何かを理解しよう
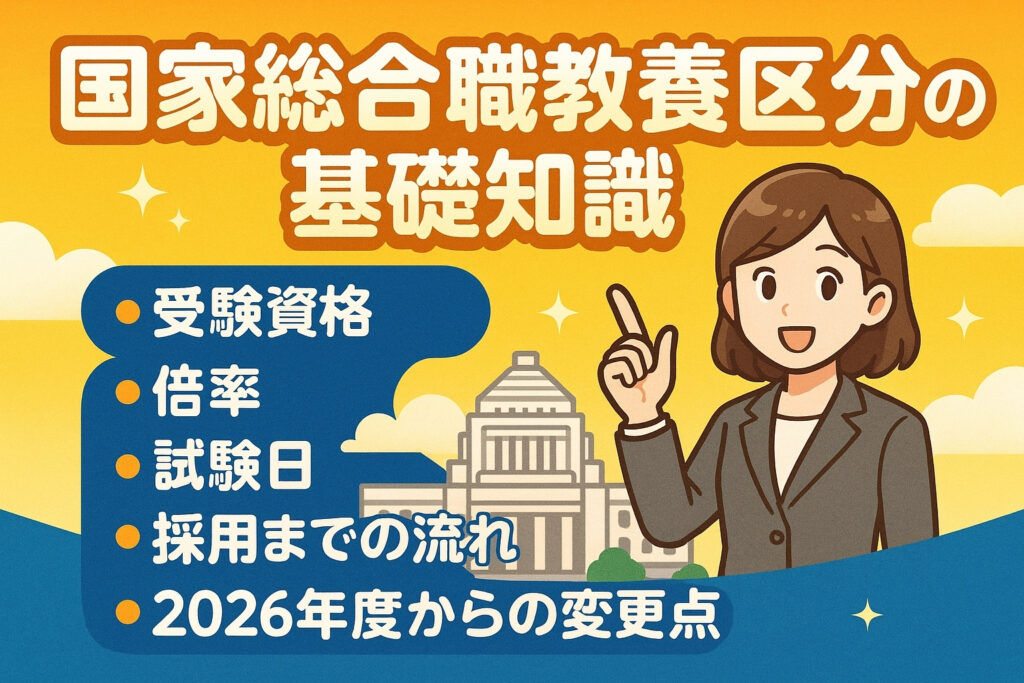
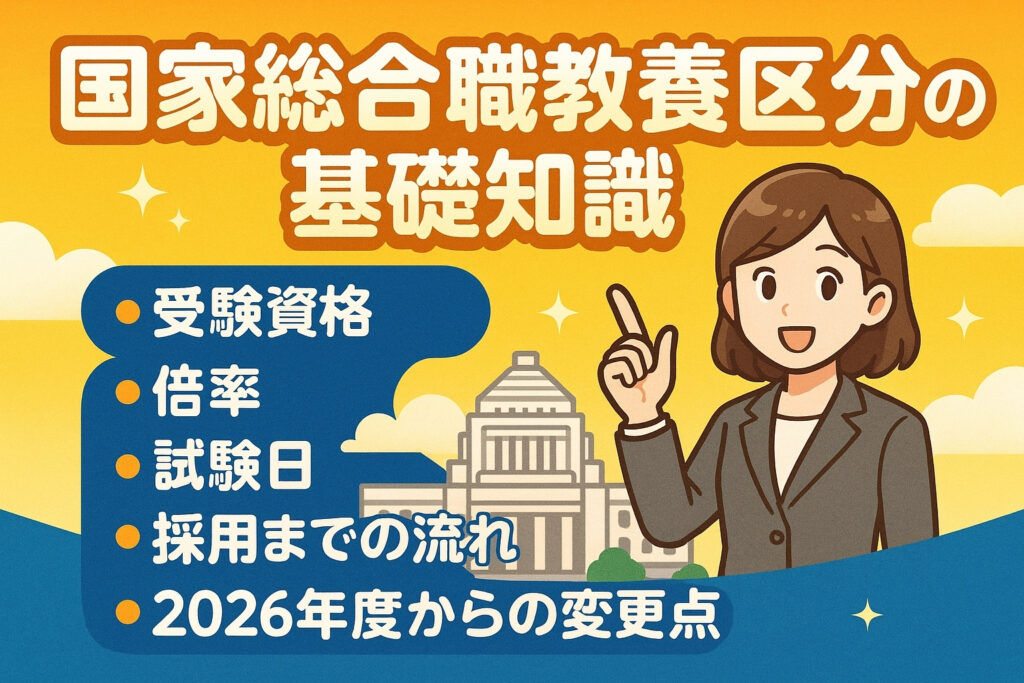
国家総合職の教養区分は、専門科目を課さず、主に基礎能力試験と論文、人物試験を通じて総合的な資質を評価する試験方式です。
従来の専門区分に比べて、幅広い層が挑戦できる仕組みとなっており、大学で特定の専門知識を深めていない人でも受験しやすいという特徴があります。
ただし「誰でも受けられる」分、受験者数が多く倍率が高いことも事実です。
まずは受験資格や試験の倍率、採用までのスケジュールなど基礎的な情報を押さえることで、受験に際しての不明点がなくなり、気持ちよく試験対策に移れるでしょう。



「これだけは絶対に知っておきたい」という受験情報を、詳しく見ていきましょう。
受験資格について
2025年度試験における国家総合職教養区分の受験資格は、以下のとおりです。
- 1995/4/2〜2006/4/1生まれは学歴要件の記載なし。
- 2006/4/2以降生まれは「大学卒業者または2026/3まで卒業見込み」等の要件あり。
つまり「21歳以上30歳未満」であれば学歴を問わず受験可能で、19歳以上21歳未満の場合は、採用年に大学卒業見込みであれば受験可能です。
受験資格に幅がある理由は、国家総合職が多様なバックグラウンドを持つ人材を必要としているためであり、学歴や経歴よりも資質や能力を重視する姿勢が表れています。
まず受験資格を理解することは、自分が試験に挑戦できるかどうかを確認する第一歩です。



最終学歴が高卒の方は、21歳以上になるまでは受けられないため注意しましょう!
倍率について
国家総合職教養区分の倍率は毎年高く、他の公務員試験と比べても合格するのはやや高難度です。
人事院の公表データによれば、2024年度の受験倍率は6.6倍、2023年度は6.0倍となっています。
倍率が高い理由は、専門知識を問われないため受験ハードルが低く、幅広い層から受験希望者が集まるからです。
過去に専攻してきた学問に関係なく受けられることから、民間就活と並行して挑戦する学生や、キャリア転換を目指す社会人まで、幅広い層が受験に参入します。
つまり、合格を目指すには単なる知識量だけでなく、戦略的に得点源を作ることが欠かせません。
独学で挑む場合も、倍率の高さを踏まえて計画的に学習を進めることが必須といえるでしょう。



地方公務員には倍率が10倍以上の試験もあるため、そこと比べると簡単に見えてしまいがちですが、国家公務員はそもそも対策難度が高いため、必要な努力は国家総合職教養区分の方が多めです。
試験スケジュールについて
国家総合職教養区分の試験は例年秋に実施され、全体の流れは「1次試験(基礎能力・総合論文)→2次試験(企画提案・政策課題討議・人物試験)→官庁訪問」という順序で進みます。
2025年度試験を例に挙げると、1次は10月5日、2次は11月22,23,29,30日、最終合格は12月18日となっています。
官庁訪問は翌年度の4月採用に向けた選考で、夏前くらいから始まるのが基本です。
上記スケジュールは毎年大きく変わることはありませんが、受験準備を進めるうえで早めに把握しておく方がよいでしょう。



試験日から逆算して学習スケジュールを立てるので、必ず試験対策を始める前に試験日を確認してください!
採用までの流れ
まずは1次試験(基礎能力・総合論文)を突破し、2次試験(企画提案・政策課題討議・人物試験)で総合的な能力が評価されます。
ここで最終合格者となった後、各省庁や機関で行われる「官庁訪問」に参加し、採用側と面談や説明を重ねることで、内々定を得る流れです。
試験の成績だけでなく、官庁訪問を通じての志望動機や人柄、組織との相性が最終的な採否を大きく左右するため、試験が終わったからと言って気を抜かないように注意しましょう。
例えば、同じ成績帯の合格者でも、官庁訪問での熱意や表現力が評価されることで採用に繋がるケースは珍しくありません。
したがって「最終合格=採用」ではなく「官庁訪問=採用の決め手」という流れを理解して準備を進めることが不可欠です。



面接と官庁訪問は1人だと対策しづらいため、独学の方が不利になりがちなポイントですね。
2026年度からの変更点
2026年度から国家総合職教養区分にはいくつかの制度変更が予定されており、受験を検討する方は必ず把握しておきましょう。
変更点としては、従来の試験は秋に1回だけの実施だったところ、春実施の追加(年2回化)されることや、名簿有効期間7年になったことで、国家公務員としての採用希望年度について幅を持って選択することができるようになった点です。
こうした変更は受験戦略に直接影響するため、最新情報を人事院の公式発表などで常に確認しながら学習を進める必要があります。
各試験の内容と対策法を紹介
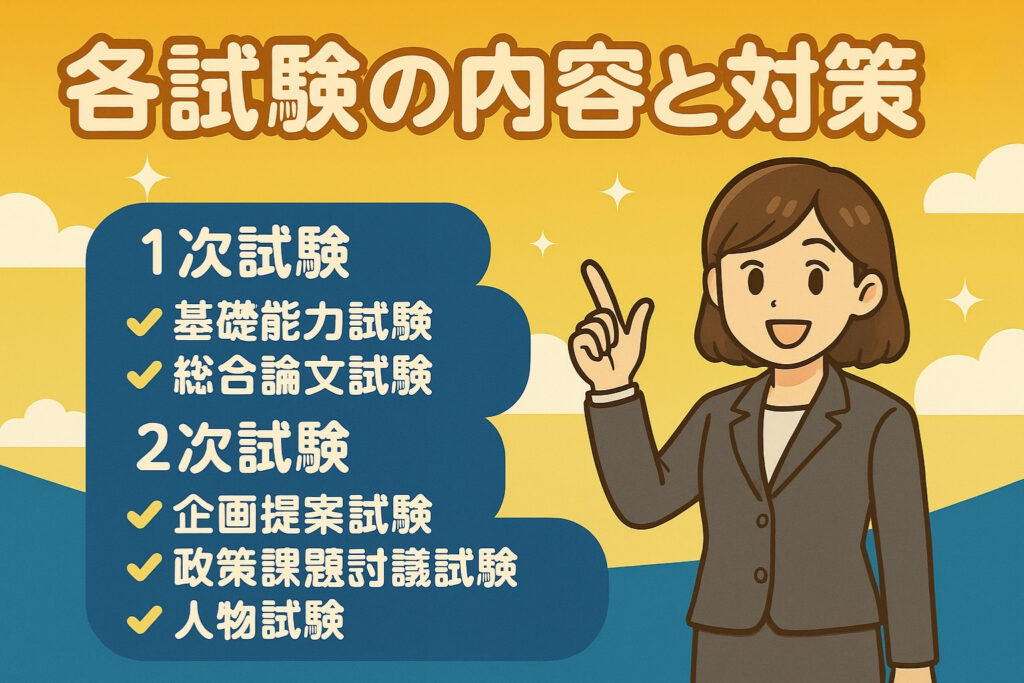
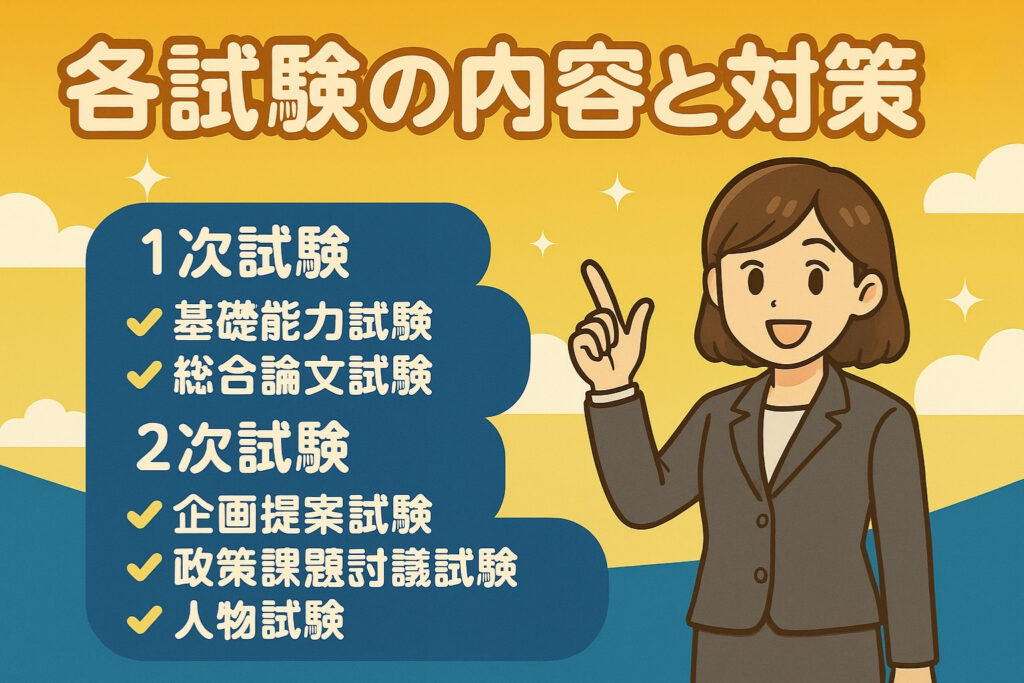
試験内容が少々複雑ですが、各試験がどのような試験なのか、しっかりと理解しておきましょう。
- 【1次試験】
-
- 基礎能力試験
- 総合論文試験
- 【2次試験】
-
- 企画提案試験
- 政策課題討議試験
- 人物試験(面接)
上記の試験による選考に加え、英語試験による加点制度もあります。
これは、事前に受験者が一定レベルの英語試験のスコアを有している場合に、本試験の点数に一定の点数が加算される制度です。
英語が得意で、受験を有利に進めようとしている方は、事前に英語試験を受験しておくのも1つの手でしょう。
| 試験名 | 加算点数 |
|---|---|
| TOEFL iBT | 65以上:15点 80以上:25点 |
| TOEIC Listening & Reading Test | 600以上:15点 730以上:25点 |
| IELTS | 5.5以上:15点 6.5以上:25点 |
| 実用英語技能検定(英検) | 準1級以上:25点 |
なお、TOEICは公開テスト限定でIPテスト(オンライン)は不可となっており、各試験における加算有効期間は試験年度4月1日から遡って5年以内、書類は2次試験で提出することとなっています。
続いて、本試験における各試験の配点比率は以下のとおりです。
| 試験種目 | 配点比率(28分割) |
|---|---|
| 基礎能力試験 | Ⅰ部:3/28 Ⅱ部:2/28 |
| 総合論文試験 | 8/28 |
| 政策課題討議試験 | 4/28 |
| 企画提案試験 | 5/28 |
| 人物試験 | 6/28 |
1次試験合格者の決定については、総合論文試験の点数は考慮せず、基礎能力試験の各部の基準点に達しているかどうかのみで判断されるため注意しましょう。
総合論文試験の結果は、1次試験合格者を対象に、最終合格者の決定時に評定されます。
また、基準点に達していない試験種目が1つでもある場合は、他の試験種目の成績にかかわらず不合格となってしまいます。
- 基礎能力試験:各部ごとに満点の30%以上
- 総合論文試験:Ⅰ部・Ⅱ部ともに10点満点中の各部ごとに4点以上
- 政策課題討議試験:A〜EのうちD評価以上
- 企画提案試験:12点満点中の4点以上
- 人物試験:A〜EのうちD評価以上
(総合論文試験、企画提案試験においては、2025年度試験から「個別に定める」という記載のみで明確な数値は非公表)
基礎能力試験以外は明確な正解・不正解がないため、具体的な評価基準は明かされてはいませんが、基準点は参考程度に知っておきましょう。



それでは、それぞれの試験内容と対策法を解説していきます。
基礎能力試験の内容と対策法
前述のとおり、1次試験は基礎能力試験の結果のみで判定されるため、まずはここで高得点を取ることが重要です。
- Ⅰ部(知能分野):24第・2時間
-
- 文章理解(現代文、英文読解)
- 数的処理(数的推理、判断推理、資料解釈)
- Ⅱ部(知識分野):30題・1時間30分
-
- 社会科学(政治・経済・社会)
- 人文科学(日本史・世界史・地理・文学・哲学など)
- 自然科学(数学・物理・化学・生物・地学)
- 情報・時事問題
各部ごとに満点の30%以上得点しなければ、その時点で不合格になるため注意しましょう。
- 学習は頻出箇所に絞り、出題数の少ない分野は後回しにする
- 必ず復習を取り入れ、学習した内容を効率よく思い出せるようにしておく
- 過去問→参考書→問題集の順に対策を進める
- スキマ時間を活用し、少しでも学習時間を確保する
- ポモドーロ・テクニック(タイマー学習)を取り入れ、集中力を最大化させる
総合論文試験の内容と対策法
総合論文試験は、受験者の論理的思考力や政策課題への理解を測る重要な試験です。
内容はⅠ部とⅡ部でそれぞれ1題ずつ出され、合計4時間で記述します。
- Ⅰ部(教養的論述):1題
-
哲学・倫理・社会問題など、抽象度の高いテーマが提示され、それについて自分の考えを論理的にまとめる力が試される。
- Ⅱ部(政策的論述):1題
-
具体的な行政課題(少子化対策、環境問題、経済成長など)がテーマとなり、自分なりの政策提案を行うことが求められる。
出題形式は、与えられたテーマに対して一定時間内で論理的に文章を構成し、自分の意見を展開するというものです。
この試験はもっとも配点が多く、軽視すると合格は難しいでしょう。
例えば「少子高齢化への対応」や「地方創生」など、国の政策課題に直結するテーマが頻出します。
知識よりも「論理力と文章力」が問われるため、日頃から書く練習を習慣化することが重要です。
- 普段から新聞のコラムや評論文を読み、要約・意見をまとめる練習をしておく
- 政府が発表する白書や時事問題の基本を押さえ、課題に対して「現状 → 課題 → 解決策 → 期待される効果」という流れで整理する
- 導入・本論・結論の三段構成にするなど、読みやすい文章構成を心がける
企画提案試験の内容と対策法
企画提案試験は、与えられた課題に対して具体的な解決策や施策を提案する力を評価する試験です。
- Ⅰ部(資料分析・資料作成):1題・1時間30分
-
与えられた資料をもとに政策課題を整理し、プレゼン資料を作成する。短時間で要点を抽出し、論理的にまとめる力が必要。
- Ⅱ部(プレゼン+質疑応答):おおむね30分
-
作成した資料をもとに、試験官へプレゼンを行い、その後の質疑応答で自分の考えを論理的に説明する。
この試験では「現実的かつ実行可能な提案」を出せるかが合否の分かれ目となります。
単なるアイデアではなく、政策として実際に機能する内容が求められるからです。
例えば「行政のデジタル化をどう推進するか」といった課題が出題された場合、単なる理想論ではなく、予算や人員、法制度との整合性を踏まえて提案する必要があります。
- 政府が発表する白書や制作資料を読み込み、実際の行政施策の枠組みを理解しておく
- まずは身近な課題を題材に「問題点→原因→解決策→期待される効果」という流れで情報を整理する練習をする
- 声の大きさや話し方の分かりやすさも評価対象となるため、模擬練習で慣れておく
政策課題討議試験の内容と対策法
政策課題討議試験は、6人で1グループを組み、与えられた政策テーマについて約1時間30分程度で討議を行う試験です。
- レジュメ作成(約20分)
- 各人あたりの個別発表(約3分ずつ)
- グループ討議(45分)
- 討議を踏まえたうえでの個別発表(約2分ずつ)
この試験では「論理的に議論を進めながら協調性を示すこと」が合格の鍵となります。
国家総合職に求められるのが個人の知識だけではなく、他者と連携して課題を解決する能力だからです。
例えば、テーマが「地域活性化策」だった場合、自分の意見を一方的に主張するだけでは評価されず、他者の意見を理解しつつ建設的な意見交換に導く姿勢が高く評価されます。
- ニュース記事や政府発表の白書等をもとに、自分なりに「問題→原因→対策→効果」の形で意見をまとめる練習をする
- 友人やオンラインコミュニティ等で模擬討論をしておく
人物試験(面接)の内容と対策法
人物試験は、受験者の人柄や志望動機、将来の適性を見極める試験であり、最終的な採用に直結する非常に重要なプロセスです。
特に「自分の考えをわかりやすく伝える力」と「一貫性」が問われます。
試験官が知りたいのは単なる暗記した回答ではなく、受験者が国家公務員として働く覚悟や具体的なキャリアビジョンを持っているかどうかだからです。
例えば「なぜ国家総合職を志望したのか」「将来どのような政策分野に関わりたいか」といった質問に対して、経験や価値観に基づいて一貫したストーリーを語れることが評価につながります。
- 自己分析を徹底的に行い、自分の強み・弱みを把握する
- 頻出の質問事項に対しては必ず上手に回答できるように練習する
- 模擬面接を受けて客観的なフィードバックを得る
- 映像として録画して改善点を見つける
独学でも合格できる人の特徴とは
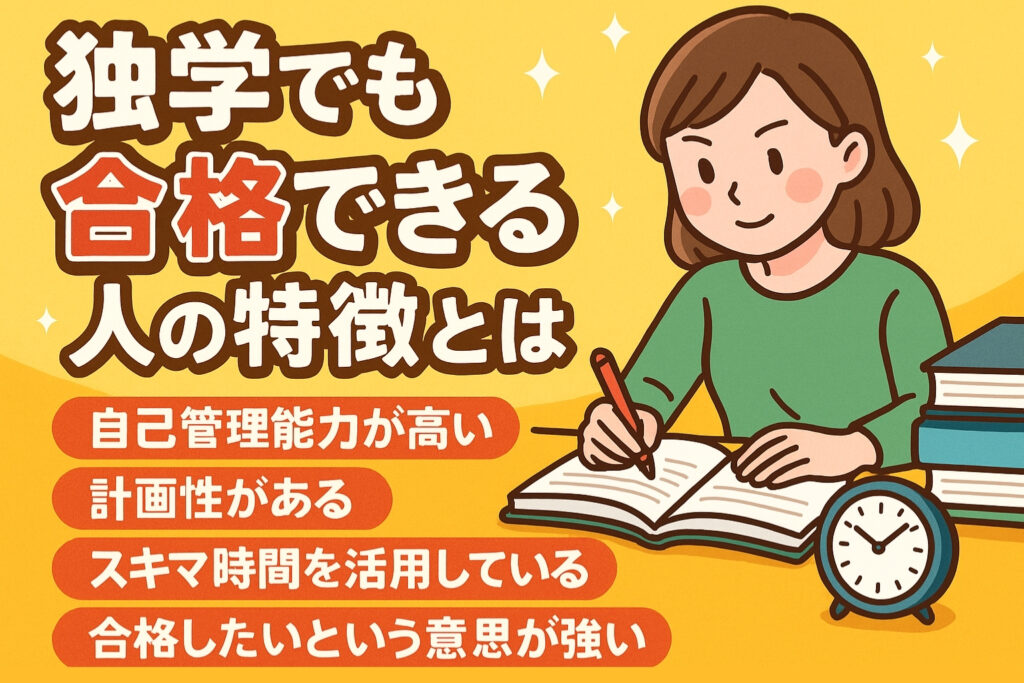
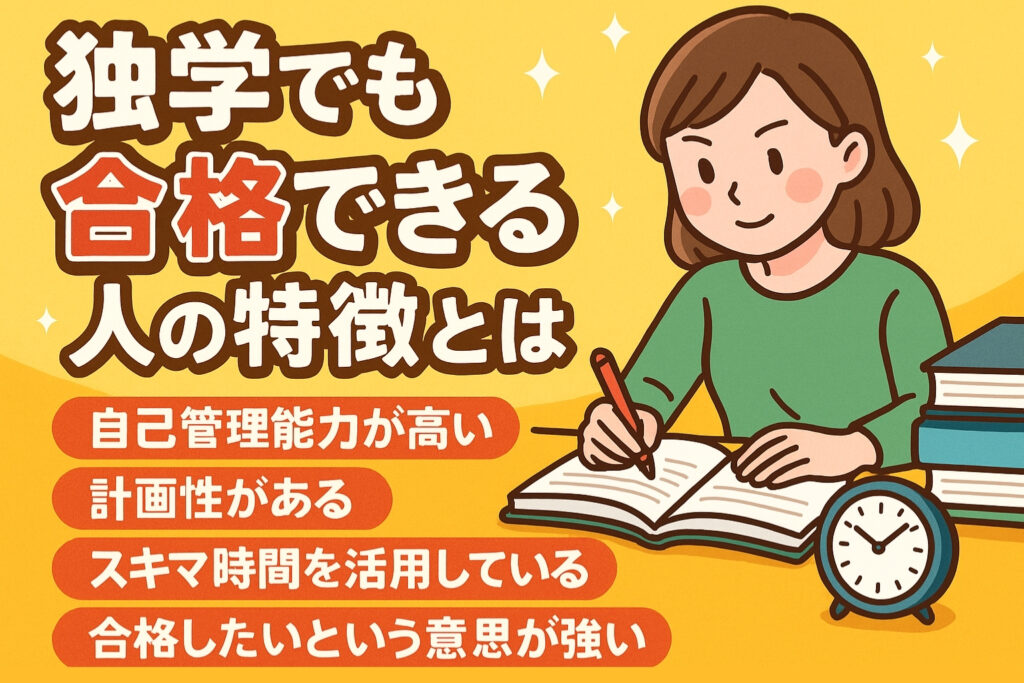
独学で国家総合職教養区分に合格する人には、いくつかの共通する特徴があります。
自分の特性を客観的に把握し、弱点を補いながら試験対策をするためにも、合格者の特徴は必ず理解しておきましょう。
自己管理能力が高い
独学で合格を勝ち取るためには、自己管理能力が最も重要です。
予備校に通えば講師が進捗を管理してくれ、学習にもある程度の強制力が働きますが、独学ではすべて自分で調整する必要があるからです。
例えば、1日の勉強時間を「午前は数的処理、午後は社会科学」と区切り、進捗を記録して振り返る習慣をつけるだけでも効果が大きく変わります。
また、模試を自分で受けに行き、弱点を洗い出す姿勢も自己管理能力の一部です。
こうした工夫を積み重ねられる人は、本番までに確実に力を伸ばすことができるでしょう。



現代はYoutubeやTikTok、Xなどあらゆる娯楽的なSNSが発達しているため、独学だとついスマホを触りがちです。勉強を始めると決めたら、絶対にスマホを触らないという固い決意を持って取り組みましょう。
計画性がある
試験日から逆算し、それぞれの試験科目・分野に対して正しい優先順位を付け、効率的な学習スケジュールを立てられる人が合格を掴めます。
特に基礎能力試験の対策範囲は広いため、やみくもに勉強すると時間が足りなくなるからです。
例えば「何月までに基礎能力試験の過去問を3周」「夏中に論文の答案を10本書く」など、具体的な数値目標を設定することが効果的です。
さらに、配点比率を意識して得点源となる科目から取り組むことも重要となります。
無理のない計画を立て、柔軟に修正しながら進められる人は、独学でも効率的に合格レベルに到達できるでしょう。



行き当たりばったりで対策をしている人は、時間が足りなくなって急に焦りだしてしまいます。そうならないためにも、いつまでにどの単元を終わらせるのかなど、学習スケジュールは最初に立てましょう。
スキマ時間を活用している
スキマ時間の有効活用も、独学で合格する人の特徴です。
通学時間や休憩時間を活かせる人は、限られた勉強時間を大幅に増やせます。
通勤・通学中にアプリで学習する、昼休みに数的処理の参考書を読む、寝る前にニュース記事を読んで政策課題を整理する、といったことを試しましょう。
こうした細切れ時間の勉強は集中力を高め、飽きにくいという利点もあります。
1日のスキマ時間をすべて学習時間に充てられれば、1日あたりの学習時間を約1時間半程度増やすことも不可能ではありません。



朝20分早く起きて出勤・出社前に前日の復習をするなど、自ら学習時間を増やそうとすることも重要ですね!
合格したいという意思が強い
最後に、合格したいという強い意志を持ち続けられることも、独学で合格するための重要な要素です。
試験対策は長期戦になるため、思うように暗記が進まなかったり、論文の書き方で行き詰まったりと、挫折しそうな局面を必ず経験します。
そのようなときに「自分は必ず合格する」という強い意志を持つことで、再び机に向かうことができるはずです。
志望動機を明確にし、働いた後のキャリア像を具体的に思い描くことはモチベーション維持に役立ちますし、面接対策にもつながるため、心が折れそうなときは「なぜ自分はそこまでして国家公務員になりたいのだろうか」と自問自答してみましょう。



結局のところ、絶対に叶えたい目標がある人が1番強い人間です。意志の力があれば心が折れることはまずありません。
独学が厳しいと感じたら数的塾がおすすめ
独学で勉強を進めていると、多くの人が情報不足に陥ったり、モチベーションが低下したり、自分の勉強法が正しいか不安になったり、といった壁に直面します。
もし不安を感じ始めたなら、公務員試験対策に特化したオンラインスクール「数的塾」を利用するのがおすすめです。
誰でも受講しやすい価格設定で、なおかつ独学の弱点を補いながら効率的に学習を続けられるからです。
「数的塾」では、最新の試験情報や頻出問題の解説、個別の学習相談などをオンラインで受けられる仕組みが整っており、地方在住者や忙しい社会人でも利用しやすくなっています。
独学では得にくい第三者からのフィードバックを受けられることで、自分の弱点を客観的に把握でき、合格への最短ルートを描きやすくなります。



今なら公式LINEを友だち登録するだけで、筆記試験の対策ガイドが無料でもらえますので、以下のリンクから入手してみましょう!サービスの説明資料もダウンロードできます!
\数的塾の限定講義&合格ガイド無料配布中/
よくある質問(Q&A)
国家総合職の教養区分を独学で受験する際に浮かぶよくある疑問点を、以下でご紹介します。
まとめ
国家総合職教養区分は、専門試験がないため幅広い層が挑戦できる一方、倍率が高く合格するのが大変な試験です。
独学でも合格は十分可能ですが、効率的な対策は必須となります。
独学合格のために特に重要なポイントを以下にまとめました。
- 基礎能力試験:1次試験は基礎能力試験のみで合否が決まるため最優先で対策
- 総合論文・企画提案・政策課題討議:政策課題のリサーチや論理的思考力と文章力を鍛えることがカギ
- 人物試験:自己分析を徹底し、一貫した志望動機とキャリア像を語れるようにする
- 合格に必要なこと:徹底した自己管理、効率的な学習計画の立案、スキマ時間の活用、合格するという強い意思
この記事を読んだことをきっかけに、まずは学習計画を立てる(見直す)ところから始めてみてみてはいかがでしょうか。
ゆっくりしているとライバルにどんどん差をつけられてしまいますので、すぐにでも合格のための一歩を踏み出しましょう。
\数的塾の限定講義&合格ガイド無料配布中/
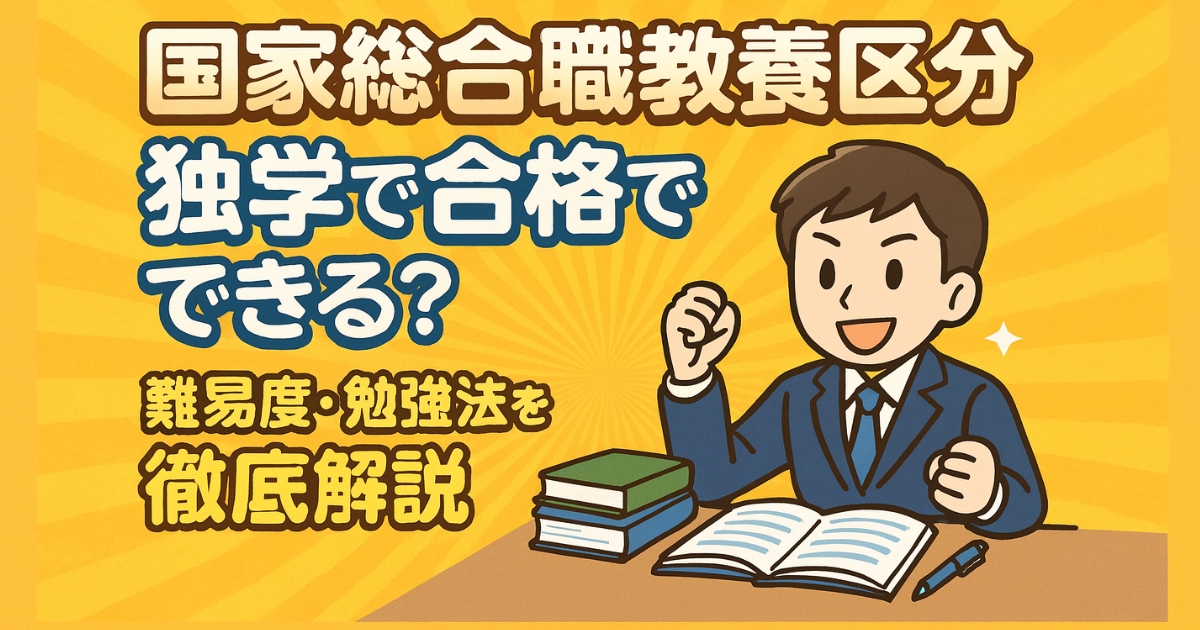

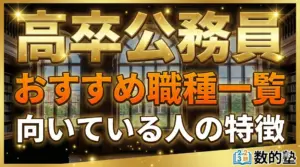
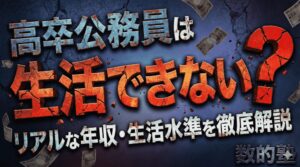


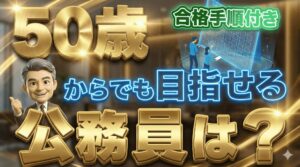
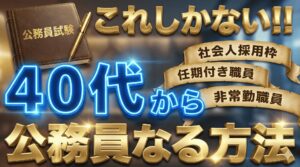


コメント