公務員試験の面接では、面接官の質問に対して適切かつ簡潔に答えられなければ不合格になる可能性が高いです。適切な回答をするためには、質問内容について理解を深め、自分なりの回答も用意しておく必要があります。
そして、面接試験でのよくある失敗例や合格のポイントを理解しておくことで、他の受験者との差別化も図りやすくなるでしょう。
今回は、公務員試験の面接で聞かれやすい質問例&回答例50個や面接の重要性、回答の質を上げるポイントなどを解説します。この記事を参考にすることで、頻出質問について理解できるだけでなく、面接対策全体の強化も図れるでしょう。
 ミキサック
ミキサックオンライン×最短で公務員試験合格を目指せる「数的塾」を運営しているミキサックです!
\数的塾の限定講義&合格ガイド無料配布中/
公務員試験における面接の重要性と配点


「公務員試験に合格するためには面接対策が必須」と言われることが多いですが、実際にどの程度重要なのか理解できている方は少ないです。面接の重要性をしっかりと理解しておくことで、面接対策の丁寧さやモチベーション向上にも繋がるでしょう。
国家公務員や地方公務員における各試験の配点と全体における面接の配点は、以下の表を参考にしてください。
| 基礎能力試験 | 課題対応能力・専門試験(多肢選択式) | 専門試験(記述式) | 一般教養・政策論文試験 | 人物試験 | 全体における面接の配点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家一般職 (大卒程度) | 4/9 | 1/9 | — | 2/9 | 2/9 | 約22.2% |
| 国家総合職 (大卒程度) | 2/15 | 3/15 | 5/15 | 2/15 | 3/15 | 約20% |
| 千葉県職員 (上級・一般行政A) | 100点 | 100点 | — | 100点 | 400点 | 約57.1% |
| 埼玉県職員 (上級・一般行政) | 100点 | 100点 | — | 100点 | 300点 | 約50% |
| 神奈川県職員 (Ⅰ類試験) | 100点 | 100点 | — | 50点 | 300点 | 約54.5% |
参考:2025年度国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)合格者の決定方法
参考:令和7年度千葉県職員採用上級試験
参考:令和7年度埼玉県職員採用上級試験 受験案内
参考:神奈川県職員採用試験 受験案内
国家公務員試験では面接の配点が約20%なのに対し、地方公務員試験では約50%以上となっています。つまり、地方公務員では半分以上が面接で評価されているということです。
以上のように、受験先によって面接の配点・重要性は異なるものの、面接が評価の大部分を担っている可能性は高いため、公務員試験に合格するためには面接対策がかなり重要と言えるでしょう。



受験先によっては、各試験の配点が公開されていないこともありますが、面接試験は重要視されている可能性が高いです!
公務員試験でよくある面接のタイプ


公務員試験の面接は、個人面接だけではありません。面接のタイプによって、評価されているポイントも異なるため、以下3つの面接のタイプについて理解を深めておくことが大切です。
- 個人面接
- 集団面接
- 集団討論
個人面接は「1対1」の面接試験なのに対し、集団面接や集団討論は「複数対複数」の面接試験となります。個人面接と集団面接・集団討論では、特徴や意識すべきポイントも異なるため、それぞれの特徴を理解した上で対策を進めましょう。



受験先によってどんな面接試験が行われるかは異なるため、確認した上で適切な対策を進めましょう!
個人面接


個人面接とは、受験者1人に対して3〜5人程度の面接官が対応する形式です。所要時間は、15〜20分程度が一般的です。
個人面接では、受験者1人に対して細かい質問ができるため、人間性の部分を重点的に評価されます。さらに、人間性の部分だけでなく、受験先についても細かく聞かれる可能性が高いため事前に調べられることは必ず調べておきましょう。



個人面接は、公務員試験だけでなく最も一般的な面接形式です!
集団面接


集団面接とは、複数の受験者(3〜8人程度)に対して、複数の面接官が対応する形式です。一度に複数の受験者が面接を受けるため、1人あたりの所要時間は個人面接より少なくなります。
集団面接では、個人についてだけでなく他の受験者の発言を聞く様子や他の受験者との比較などにより評価されます。また、1人あたりの所要時間が少ないため、質問に対して簡潔に回答できるかも評価されるのが特徴です。



他の受験者が一緒に評価されるため、個人面接では見られないような部分も評価対象となっています!
集団討論


集団討論とは、受験者同士で1つのテーマについて話し合い、制限時間内に結論をまとめて発表する形式です。他の面接とは異なり、話す相手が受験者同士となり、面接官はその様子を観察して評価しています。
集団討論では、協調性の有無や話を冷静に進める力などが評価されています。また、「自分の役割を理解して、話し合いが円滑に進められるように努めているか」も評価されていることを理解しておきましょう。



自分のことだけでなく、全員が話し合いに参加できるような振る舞いをしなければ、グループ全員が不合格なる恐れもあるため注意しましょう!
公務員試験の面接で聞かれやすい質問例&回答例50選


公務員試験の面接で好印象を残すためには、面接で聞かれやすい質問例&回答例について理解しておくことが大切です。面接で聞かれやすい質問を、大きく分けると以下の2つに分けられます。
- 受験者自身に関する質問
- 受験先や公務員試験に関する質問
面接の所要時間は長くても20分程度のため、紹介する全ての質問が聞かれるわけではありません。しかし、質問に対する回答を準備しているに越したことはないため、全ての質問に目を通し、自分なりに回答をまとめておきましょう。



実際の面接では、これらの基本的な質問に加え、発言に対して深掘りする質問をされる可能性が高いです!
受験者自身に関する質問例&回答例25選
受験者自身に関する質問例としては、以下の25個が挙げられます。
- 自己紹介をしてください
- 自己PRをしてください
- 長所と短所を教えてください
- あなたの強みを公務員としてどう活かせると思いますか?
- 趣味や特技を教えてください
- 今までで達成感を感じた出来事はありますか?
- 過去に失敗したことと乗り越えた方法を教えてください
- これまでにチームで何かに取り組んだ経験はありますか?
- ストレスを感じた時はどう対処していますか?
- 学生時代に頑張ったことを教えてください
- 同じ職場に苦手な人がいたらどうしますか?
- 尊敬する人とその理由を教えてください
- 最近読んだ本や印象に残った作品を教えてください
- 公務員以外の職業に就くとしたら、何を選びますか?
- 公務員として働く上で不安に感じていることはありますか?
- 周囲から信頼を得るために普段心掛けていることは何ですか?
- 体調管理や健康維持のために行っていることはありますか?
- プレッシャーがかかる場面で力を発揮できた経験を教えてください
- 他の受験者と比べて自分が優れていると思う点は何ですか?
- 公務員として働くことを家族は何と言っていますか?
- 今の自分に足りないと感じている部分はどこですか?
- 周りの人からどんな人だと言われることが多いですか?
- 今までに大きな病気や怪我をしたことはありますか?
- 意見が対立したらどのように解決しますか?
- 最近のニュースで気になったことはありますか?
これらの質問は、個人面接・集団面接関係なく聞かれやすい質問です。受験者自身に対する質問は、自己分析が不十分だと適切な回答ができません。表面的な回答例をそのまま使用するのではなく、自己分析をした上で自分なりにアレンジすることが大切です。



面接官は深掘りして聞いてくるため、浅い回答だと悪印象を与える恐れがあります!
1.自己紹介をしてください
受験者の基本情報(学歴・経歴)や人柄、話し方の雰囲気を把握しようとしています。特に公務員面接では、簡潔に要点をまとめて話せるかが見られており、最初の印象にも繋がる大切な問いです。自己PRのような内容ではなく「あなたは誰か」を紹介するバランスが求められます。
| 【回答例】 |
|---|
| 〇〇大学△△学部の□□と申します。学生時代は〇〇について学びながら、ゼミ活動やアルバイトなどにも積極的に取り組んできました。特に、〇〇研究ゼミでは〇〇というテーマに取り組み、地域の方々にインタビューを重ねて、発表までまとめ上げた経験があります。本日はこれまでの経験を活かし、誠実にお話しできればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 |
自己紹介では、自己PRのように強みを押し出すのではなく、自分の名前や学歴・これまでの学びや取り組みなどを、簡潔かつ自然な流れで伝えることが大切です。話の構成は「名前 → 学歴 → 学生時代の活動 → 結びの挨拶」が基本で、1分以内に収まる内容を心掛けましょう。
2.自己PRをしてください
受験者が自分の強みを明確に理解し、それを簡潔に伝える力があるかどうかを見ています。限られた時間の中でどこに重点を置いて話すか、伝える順序や論理性も評価対象です。また、公務員として求められる課題解決力・継続力・協調性などの資質と関連付けられているかどうかも重要なポイントになります。
| 【回答例】 |
|---|
| 私の強みは、継続して努力を積み重ねられる力です。どんな状況でもコツコツと粘り強く取り組む姿勢を大切にしてきました。大学では、公務員試験の勉強とゼミ活動を両立させ、毎日早朝から勉強時間を確保し続けたことで、第一志望の筆記試験に合格できました。この継続力を活かし、公務員としても任された業務に責任を持って取り組みたいと考えています。 |
自己PRでは、自分の強みを明確に述べた上で、それを裏付ける具体的なエピソードを交えて話すことが大切です。1分という制限がある事も多いため、話の構成にはPREP法を用い、論理的かつ簡潔にまとめましょう。また、公務員としての適性に結びつけて締めくくることで、面接官に「この人と働きたい」と思ってもらいやすくなります。
3.長所と短所を教えてください
受験者が自分自身を客観的に理解できているか、その上で長所をどう活かし、短所をどう改善しようとしているかを見るために問われます。公務員には協調性や自己管理能力が求められるため、強みと弱みを冷静に分析し、前向きな姿勢を持っているかが評価のポイントとなります。
| 【回答例】 |
|---|
| 私の長所は計画的に物事を進められる点で、短所は慎重になりすぎて行動が遅れることがある点です。物事を効率よく進めたいという意識が強く、つい準備や確認に時間をかけすぎてしまう傾向があります。大学のゼミ発表では、事前に内容を何度も確認してしまい、準備がギリギリになることがありました。ただ、最近では優先順位を意識して行動するようにしています。慎重さは必要な特性でもあると思うので、その良さを残しつつ、柔軟に動けるよう意識しています。 |
長所を具体的に伝えるとともに、短所についても正直に答えましょう。短所では、現在克服に向けた努力や工夫をしていることを伝えることが大切です。単に性格を並べるのではなく、実際の経験と結びつけて話すことで、説得力のある回答になります。
4.あなたの強みを公務員としてどう活かせると思いますか?
自分の強みを話すだけでなく、その強みを公務員の業務と結びつけて説明できるかを見ています。強みが自己満足で終わらず、住民サービスや行政の役割にどう役立つのかを伝えられているかが評価のポイントです。
| 【回答例】 |
|---|
| 私の強みは「傾聴力」であり、公務員として住民対応の際に活かせると考えています。住民対応では、住民の要望や悩み事などを正確に聞き取り、適切な対応をしなければいけません。大学時代には、友人の悩みを聞いた上で、最適なアドバイスをしたことで悩みを解決することもできました。これらの傾聴力を生かし、住民の声をしっかり受け止めて適切な対応ができると考えています。 |
実際の経験を交えて裏付けを行い、公務員の仕事にどう役立てられるのかを結びつけて話すと説得力が増します。具体的にどんな場面で自分の強みが活かせるのかを具体的に話すことで、他の受験者とも差別化できるでしょう。
5.趣味や特技を教えてください
受験者の人柄や価値観、コミュニケーション力などを図るために行われます。公務員として働く上では、住民や職員同士との関係性を築く力も重要なため、趣味・特技から受験者の柔軟性も見られている場合があります。また、面接官との会話の入り口として、リラックスした雰囲気を作る目的もあります。
| 【回答例】 |
|---|
| 私の特技は料理で、毎日自炊を習慣にしています。節約や健康管理のために始めたのがきっかけですが、次第に創作料理や栄養バランスを考えることにも興味が湧くようになりました。最近は冷蔵庫の残り物で一品を作る「即興レシピ」に挑戦していて、SNSでレシピを発信したところ、友人からも好評でした。日々の料理を通じて得た発想力や工夫する力は、仕事の場面でも活かしていけると考えています。 |
特技を話す際は、その内容が実際に日常で活かされていることや自分の性格・行動習慣とどう結びついているかまで触れることが大切です。料理のような一見仕事に関係のない特技でも、計画性・継続力・創造性といった職務に通じる要素をうまく言語化することで、説得力あるアピールに繋がります。
6.今までで達成感を感じた出来事はありますか?
受験者がどのような目標を持ち、どのような努力を経て成果を出してきたのかを通して、人柄や価値観、課題への向き合い方を評価しています。また、公務員に必要な責任感や粘り強さ・達成までのプロセスを大切にできるかといった要素も同時に評価されています。
| 【回答例】 |
|---|
| 私は、地域ボランティアイベントの企画運営を成功させたとき、大きな達成感を得ました。初めて責任者として全体をまとめる立場になり、調整や集客など多くの課題に直面したからです。仲間と役割分担をしながら自治体や地域団体と連携を取り、最終的に100名以上の参加者を集めて無事に実施できました。一つの目標に向かって周囲と協力しながらやり遂げた経験が大きな達成感に繋がりました。 |
「何をやったか」だけでなく「なぜ達成感を得られたのか」「どのように取り組んだのか」といった背景やプロセスをしっかり説明することが重要です。単なる成功談ではなく、困難を乗り越える中で得た学びや成長を含めることで、面接官に印象深く伝わります。
7.過去に失敗したことと乗り越えた方法を教えてください
受験者が失敗をどう受け止め、どのように改善や成長に繋げたかを確認するために行われます。公務員の仕事を進める中では、想定外の出来事やミスのリカバリーが求められる場面も多いため、失敗から学ぶ姿勢・責任感・課題解決力があるかどうかを評価する意図があります。
| 【回答例】 |
|---|
| 大学時代、アルバイト先での伝達ミスによりトラブルを起こしてしまったことがあります。口頭のやりとりだけで済ませてしまい、必要な情報が他のスタッフに正しく伝わっていませんでした。この経験から、以降は必ずメモを残す・LINEなどで共有するなど、誰が見ても分かる形で情報を整理するように改善しました。失敗を通じて、報連相の重要性を実感し、以降は周囲との連携をより丁寧に行うように心掛けています。 |
失敗経験を語る際は、内容そのものよりもそこから何を学び、どう行動を変えたかが最も重要です。自己弁護や他責にせず失敗を素直に認め、具体的な改善策を実践した姿勢を示すことで、成長意欲と誠実さが伝わります。また、公務員に求められる冷静な自己分析と、再発防止の意識が感じられるような構成にすることで、前向きな印象を与えやすくなります。
8.これまでにチームで何かに取り組んだ経験はありますか?
受験者が協調性や主体性・コミュニケーション能力を備えているかを確認するために行われます。公務員の職場では、他部署との連携やチームでの行動が基本となるため、個人プレーではなく、組織の一員としてどう動けるかが重視されます。リーダー経験だけでなく、サポート役や調整役の立場も評価対象になります。
| 【回答例】 |
|---|
| 大学のゼミで行ったチーム発表の準備で、全員の意見をまとめながら取り組んだ経験があります。意見の食い違いも多く、メンバー間の認識をすり合わせる必要がありました。私は議事録を取りながら進行役を務め、各自の意見を資料に反映し、最終的には発表内容も評価されました。この経験を通じて、相手の立場を尊重しながら協力することの大切さを学びました。 |
「どんな役割だったか」「どのように貢献したか」を具体的に示すことが大切です。自分の役割やチーム内での工夫、成果に繋がったプロセスを交えて伝えることで、協調性や実行力を効果的にアピールできます。
9.ストレスを感じた時はどう対処していますか?
受験者がストレスと向き合う冷静さや自己管理能力を持っているかを確認しています。公務員の仕事は、住民対応やチーム業務、突発的な対応などストレスのかかる場面が多いため、安定した行動が取れる人物かどうかが評価の対象になります。
| 【回答例】 |
|---|
| ストレスを感じたときは、一度立ち止まって紙に書き出すことで気持ちを整理しています。頭の中だけで抱え込まず、見える形にすることで冷静に自分の感情や状況を客観視できるからです。大学のレポートとアルバイトが重なり追い込まれた時も、タスクを書き出して優先順位を決め、落ち着いて対応できました。この習慣によって、忙しいときでも冷静に行動でき、焦らずに課題を一つずつ解決できると思います。 |
ストレスを感じること自体を否定するのではなく、どう対処するか、そしてどのように前向きな行動に繋げているかを具体的に伝えることが大切です。感情に流されず冷静に整理できる方法や自分に合ったストレスコントロールの工夫を語ることで、自己管理能力と安定性の高さをアピールできます。
10.学生時代に頑張ったことを教えてください
受験者がどのような目標を持ち、どのように努力し、どのような成果や学びを得たのかを通して、人柄や価値観、行動力を把握しようとしています。公務員の仕事では継続力・協調性・課題解決力が求められるため、何を頑張ったかだけでなく、そのプロセスや考え方も重要です。
| 【回答例】 |
|---|
| 私は大学の学園祭実行委員として、来場者数の目標達成に向けて広報活動に力を入れました。例年より来場者が減っていたため、実行委員で課題を共有し、外部への発信を強化することになったからです。私はSNS運用を担当し、イベント内容の事前公開や投稿頻度を上げることで、前年より20%多い来場者数を記録できました。この経験を通じて、目標に向けて仲間と協力しながら試行錯誤する姿勢の大切さを学びました。 |
「なぜ取り組み、それによって何を得たのか」まで明確に伝えることが重要です。行動の背景や役割、具体的な成果に触れることで、単なる体験談ではなく、主体的な取り組みとしてアピールできます。
11.同じ職場に苦手な人がいたらどうしますか?
受験者の対人関係の柔軟性や職場でのストレス耐性、協調性を見極めるためのものです。公務員の職場では、年齢も立場も考え方も異なる人たちと関わるため、自分と合わない相手とも円滑に業務を進める姿勢や工夫があるかが問われています。感情だけで判断せず、冷静かつ建設的に関係を築こうとする姿勢が評価されます。
| 【回答例】 |
|---|
| 苦手な相手でも、業務に支障が出ないよう冷静にコミュニケーションを取るよう心掛けます。職場では性格よりも、目的に向けて協力することが最も重要だと考えているからです。アルバイト先で価値観が合わない先輩と仕事をする際も、感情的にならず、相手の得意分野を活かす形で役割分担を工夫した結果、業務は円滑に進みました。考え方の違いがあっても、まずは業務を円滑に進めることを優先し、冷静な対応を心掛けています。 |
「苦手な人がいても仕事はきちんとこなす」という前提をしっかり伝えた上で、感情に左右されず、目的や役割を意識して行動できる姿勢を示すことが大切です。自分の感情だけに焦点を当てず、相手との関係性をどう工夫して業務を進めるかという冷静で協調的な対応力をアピールすることで、公務員としての適性が伝わります。
12.尊敬する人とその理由を教えてください
受験者の価値観や目標とする人物像を知るために行われます。誰を尊敬しているかよりも、その人物のどのような姿勢や行動を評価し、自分の成長にどう繋げているかが重要です。
| 【回答例】 |
|---|
| 私が尊敬しているのは、高校時代の担任の先生です。なぜなら、常に生徒一人一人に向き合い、状況に応じて最善のサポートをしていたからです。私が部活動で大きな怪我をした時期に、勉強や進路の両面で寄り添っていただいたことで、腐らず前向きに努力を続けられました。この経験から、人を支える仕事の素晴らしさを学ぶことができたため、高校時代の担任の先生を尊敬しています。 |
この質問で誰を尊敬していると答えるかは重要ではありません。重要なのは「なぜその人を尊敬しているのか」という理由を自分の言葉で説明することです。尊敬する人物の行動や姿勢から学んだことを具体的に伝え、現在や将来像にどう結び付けているのかを明確にしておきましょう。
13.最近読んだ本や印象に残った作品を教えてください
受験者が普段どのようなことに関心を持ち、そこから何を学んでいるかを確認するための質問です。本や作品そのものよりも、受験者の価値観や思考力、学びを実務にどう活かすかを評価しています。
| 【回答例】 |
|---|
| 私が最近読んだ本は、「〇〇(例:自治体の挑戦に関する本)」です。この本が印象に残った理由は、行政が直面する課題や住民参加の重要性について考えさせられたからです。特に、市民との協働で地域課題を解決する事例が紹介されており、公務員は一方的にサービスを提供するのではなく、住民と共に作り上げる存在なのだと再認識できました。実際に公務員として働く際にも、住民の声を尊重する姿勢を持って働きたいと考えています。 |
本や作品から得た気付きや学びを、自分の姿勢や将来像に繋げて話すことが大切です。公務員としての視点にどう生かせるかを一言添えると、面接官に伝わりやすい回答になるでしょう。
14.公務員以外の職業に就くとしたら、何を選びますか?
受験者が公務員にこだわる理由を確認すると同時に、受験者自身のキャリア観を確認するための質問です。「公務員への志望度が揺らいでいないか」や「公務員以外でも自分の強みを活かせる仕事をきちんと考えているか」も確認されているため、何か1つでも自分の強みを活かせそうな職業を考えておきましょう。
| 【回答例】 |
|---|
| もし公務員以外の職業に就くなら、地元の信用金庫の職員として働きたいと考えてます。信用金庫の仕事は、金融を通じて地域の人々や中小企業を支える仕事であり、地域社会に貢献できると感じるからです。また、大学時代に地元企業の経営課題を調査した経験があったことも信用金庫を選んだ理由です。ただ、より幅広く長期的に地域に関わり続けられる点で、公務員の仕事が最も自分に適していると考えています。 |
具体的な職業を挙げるときは、憧れや待遇面ではなく、自分の価値観や経験と結びつけて話すことが大切です。答え方によっては「なぜ公務員なのか」を補強するチャンスにもなるため、公務員でなければいけない理由も添えて説明しましょう。
15.公務員として働く上で不安に感じていることはありますか?
自分の課題や不安を正直に把握できているか、不安をどのように克服しようとしているのかを評価するための質問です。公務員の仕事に現実的な視点を持ちつつ、前向きな姿勢で努力していけるかが評価されています。
| 【回答例】 |
|---|
| 公務員として働く上で不安に感じていることは、幅広い業務をこなす柔軟性が求められる点です。部署によって仕事内容が大きく変わるため、その度にイチから仕事を覚えなければならず、柔軟に対応できるかという点に不安を感じています。ただ、学生時代にアルバイトをしていた際には、自分なりのマニュアルを作ることで徐々に仕事をに慣れていくことができました。この経験から、公務員になってから不安に感じている部分に対して自分なりにマニュアルを作り、早く仕事を覚えられるように努力したいと考えています。 |
不安を聞かれたときに「特にありません」と答えると、現実を理解していない印象を与える恐れがあります。一方で、不安を強調しすぎるのもマイナスです。回答する際には、不安に対して自分の弱みや課題を冷静に把握し、その克服方法を前向きに伝えることが大切です。
16.周囲から信頼を得るために普段心掛けていることは何ですか?
周囲の人間との関わり方や信頼関係が築けているかを確認するための質問です。公務員として働くためには信頼関係が必要不可欠なため、誠実さや協調性、責任感を持って行動できる人物かどうかを判断する狙いがあります。
| 【回答例】 |
|---|
| 私は、周囲から信頼を得るために、約束を守ることと報連相を徹底することを心掛けています。小さなことでも誠実に対応することで、相手に安心感を与えられると考えているからです。大学のゼミ活動では、締切を守るだけでなく進捗をこまめに共有するように意識した結果、周囲の人から信頼を得ることができました。公務員としても、日々の行動の積み重ねで信頼を築き、住民や同僚から頼られる存在になりたいと考えています。 |
普段から意識している具体的な行動を示し、過去に信頼を得られたエピソードを伝えるのがおすすめです。また、公務員としてその姿勢をどう活かすかを結びつけることで、採用後も周囲に信頼されながら働ける人材であることをアピールできるでしょう。
17.体調管理や健康維持のために行っていることはありますか?
受験者の自己管理能力の有無を確認するための質問です。住民対応や災害時の対応などでは体力や健康が必要不可欠であり、普段から自分の体調を整える意識を持っているかが評価されています。
| 【回答例】 |
|---|
| 体調管理や健康維持のために、規則正しい生活と適度な運動を心掛けています。公務員としてだけでなく、社会人として高いパフォーマンスを維持するためには、健康でいることが第一だと考えているからです。具体的には、毎日同じ時間に就寝・起床することを徹底し、週に3回のランニングを習慣にしています。今後もこうした習慣を続け、健康な状態を維持することで、公務員として安定したパフォーマンスを発揮したいと考えています。 |
睡眠や食事、運動など日常的な取り組みを簡潔に伝えると、自己管理能力がしっかりしている印象を与えられます。また、公務員としてどう活かせるのかも加えることで、好印象を与えられる可能性が高いです。
18.プレッシャーがかかる場面で力を発揮できた経験を教えてください
緊張する状況でも、冷静に行動できるか人材かを確認するための質問です。プレッシャーのかかる場面でどれだけ力を発揮できるのかだけでなく、今までどう対処してきたのかも評価されています。
| 【回答例】 |
|---|
| 私がプレッシャーがかかる場面で力を発揮できた経験としては、大学時代ゼミ代表として大人数の前で発表を担当したことが挙げられます。前まで不安がありましたが、事前に仲間と繰り返しリハーサルを行ったことで、本番では落ち着いて発表でき、結果的に高い評価をいただきました。この経験から、緊張する場面でも準備と冷静さを意識すれば力を発揮できると学びました。公務員になった後も、想定される場面に対する対策を行っておき、本番で少しでも力を発揮できるように努力したいと考えています。 |
経験を語る際には、前向きな結論で締めることが大切です。面接官は、困難をどう受け止め、どう解決してきたかを通して、公務員としての適性を判断しています。公務員になった後にプレッシャーがかかる場面があった場合、どう対処するのかも伝えることで将来性もアピールできるでしょう。
19.他の受験者と比べて自分が優れていると思う点は何ですか?
自分の強みを客観的に理解しているかやその強みを公務員としてどのように役立てられるかを確認するための質問です。自己評価が高すぎても低すぎてもマイナスになるため、謙虚さを保ちつつ具体的に強みを示せるかが評価されます。
| 【回答例】 |
|---|
| 私の強みは「継続力」であり、この点が他の受験者より優れていると考えています。一度決めたことを長期的にやり抜いた経験があるからです。大学時代には、約4年間地域清掃ボランティアに継続して参加し、リーダーとして活動をまとめた経験があります。これらの経験から、「継続力」が他の受験者よりも優れていると考えており、公務員としても地道に努力を続けられると思います。 |
強みを裏付けるエピソードを簡潔に示し、その強みが公務員としてどのように役立つかを語ることで、回答に説得力を持たせやすくなります。また、比較するためでも他の受験者のことを悪く言うような発言は避けるのが無難です。
20.公務員として働くことを家族は何と言っていますか?
受験者の家庭環境や周囲からの理解度を確認するための質問です。家族の意見を通して、受験者が安定した環境で公務員として働けるかどうかを推し量る狙いもあります。
| 【回答例】 |
|---|
| 私の家族は、公務員として働くことを前向きに応援してくれています。安定性や地域貢献の面で、自分の性格や志向に合った仕事だと理解してくれているからです。父からは「責任感の強さを活かせる職業だ」と言われ、母からは「地域に役立つ姿を見られるのが楽しみ」と応援されました。家族の期待に応えるとともに、公務員として地域に貢献する姿を実現したいと考えています。 |
この質問では、家族が賛成していることを前提に答えるのが無難です。その上で、家族からどんな言葉をかけられているのかやどんな点を期待されているのかを具体的に示すと説得力が増します。また、単なる応援として終わらせるのではなく、応援が自分の志望動機や努力の原動力に繋がっていることを伝えるのがおすすめです。
21.今の自分に足りないと感じている部分はどこですか?
受験者が自己を客観的に見つめ、課題を認識し、成長意欲を持って行動しているかを評価しています。公務員は、変化する社会課題に柔軟に対応し続ける姿勢が求められるため、自分の弱点を認め、改善しようとする前向きな姿勢が重要です。
| 【回答例】 |
|---|
| 今の自分に足りないと感じているのは、臨機応変な対応力です。事前に準備することは得意ですが、予定外のことが起きると判断に時間がかかってしまうことがあります。大学のグループ発表で急な欠席者が出た際、代役の指名に迷い、進行が遅れた経験がありました。その経験から、複数の選択肢を考えておく習慣をつけ、状況に応じて柔軟に対応できるよう心掛けています。 |
短所のようにネガティブに語るのではなく、自分に足りない点を認識し、すでに改善に向けて努力している姿勢を伝えることが大切です。課題をただ述べるだけでなく、実際に行っている工夫や取り組みを添えることで、前向きな自己成長の姿勢を面接官に印象付けることができます。
22.周りの人からどんな人だと言われることが多いですか?
受験者の自己理解の深さや客観性、周囲との関係性を確認するために行われます。公務員の仕事はチームワークや住民対応が不可欠であるため、自分がどう見られているかを理解し、それを活かして行動できるかが評価されるポイントです。
| 【回答例】 |
|---|
| 周りからは、落ち着いていて冷静なタイプだと言われることが多いです。急なトラブルや緊張する場面でも、慌てずに状況を整理して動ける部分がそう見えるようです。ゼミの発表中にトラブルが起きた際、私が内容の一部を即興で補いながら進行したことで、落ち着いていると評価されました。この冷静さは、公務員としても住民対応や急なトラブル対応で役立てられると考えています。 |
他人からの評価をただ伝えるのではなく、自分でもその評価をどう受け止めているか、またそれをどのように行動に活かしているかまで言及することが大切です。客観的な視点を持っていることが伝われば、周囲と円滑に関係を築ける協調性や社会性のアピールに繋がります。
23.今までに大きな病気や怪我をしたことはありますか?
受験者の健康状態や勤務に支障がないかを確認するために行われます。公務員の仕事は、体力・継続性・現場対応が求められる場面も多いからです。同時に、過去に病気や怪我があった場合でも、どのように乗り越え、現在は問題ないかを冷静に説明できるかも評価されています。
| 【回答例】 |
|---|
| 高校時代の部活動中に足を骨折したことがありますが現在は完治しており、生活や仕事に支障はありません。当時は全治3ヶ月の診断で、一時的に日常生活にも支障が出ました。ただ、リハビリにしっかり取り組んだことで、今では運動も問題なく行えます。以降は健康管理にも意識を向けるようになり、現在は心身ともに安定した状態を維持できています。 |
病気や怪我の経験がある場合でも現在は回復しており、業務に支障がないことを明確に伝えることが重要です。また、健康に対する意識や再発防止のための取り組みを付け加えると、前向きな印象を与えることができます。問題がなかった場合でも「特にありませんが、日頃から体調管理に努めています」と一言添えることで、自己管理力をアピールできます。
24.意見が対立したらどのように解決しますか?
受験者が対人関係での調整力や冷静な対応力、協調性を持っているかどうかを確認する意図があります。公務員の仕事では、上司・同僚・市民など多様な立場の人と意見がぶつかる場面も多いです。
そのため、感情的にならずに建設的な解決策を導き出せる姿勢が求められています。ただ自分の意見を通すのではなく、相手の立場を理解し、折り合いをつけられる人かどうかを評価しています。
| 【回答例】 |
|---|
| 意見が対立したときは相手の考えを丁寧に聞き、お互いの目的を整理することで解決を図ります。意見が食い違う背景には、それぞれの立場や優先する視点の違いがあると考えているからです。大学のゼミで発表テーマがまとまらなかったとき、全員の意見を書き出して共通点を探り、最終的に内容を組み合わせてまとめました。以上の経験から、一方的に主張するのではなく、相手を尊重しながら建設的に話し合う姿勢を大切にしています。 |
「相手を否定せずに尊重しつつ、どう対話を進めていくか」という姿勢を示すことが重要です。自分の主張だけにこだわらず、対立の根本を整理し、双方にとって納得のいく解決策を見出す工夫や行動が伝わるエピソードを伝えましょう。
25.最近のニュースで気になったことはありますか?
受験者が社会や行政に対して関心を持っているか、情報を自分なりに考えて受け止めているかを確認する意図があります。公務員は社会の変化や住民のニーズを理解した上で行動する必要があるため、時事への関心や課題意識、自分の意見を持っているかが重要視されます。
| 【回答例】 |
|---|
| 最近、ある自治体で行われた大規模な防災訓練のニュースが印象に残りました。地震や豪雨のリスクが高まる中、地域全体での備えや住民の防災意識がますます重要だと感じたからです。この訓練では高齢者の避難支援体制や情報伝達の仕組みが見直されており、実践的な取り組みに関心を持ちました。今後自分が公務員として働く際にも、地域の安全を支える役割を真剣に考えながら行動したいと感じました。 |
ニュースの内容をただ説明するのではなく、それに対する自分の考えや感じたことを明確に伝えることが大切です。公務員として働く上で関わりがありそうなテーマ(防災・高齢化・行政サービス・地域活性化など)を選ぶと、より現実味のある印象を与えられます。
受験先や公務員試験に関する質問例&回答例25選
受験先や公務員試験に関する質問例としては、以下の25個が挙げられます。
- 公務員を選んだ理由を教えてください
- 〇〇市を選んだ理由を教えてください
- 採用されたら取り組んでみたい仕事はありますか?
- 公務員ではなく民間企業ではダメなんですか?
- 公務員にしかできない役割は何だと思いますか?
- なぜ国家公務員ではなく地方公務員を志望したのですか?
- 転勤や異動があっても問題ないですか?
- デジタル化やDX推進について、行政に必要な取り組みは何だと思いますか?
- 公務員にはどのような能力が求められると思いますか?
- 今後の行政に必要だと思う人材像はどのようなものですか?
- 住民から信頼されるために必要な姿勢は何だと思いますか?
- 併願状況を教えてください
- 配属先が希望通りいかなかったらどうしますか?
- 公務員が批判されやすい立場であることをどう考えていますか?
- もし今年不合格だったらどうしますか?
- 公務員の不祥事に対してどのように感じるか教えてください
- 公務員の仕事は地味だと言われることもありますが、その点をどう考えますか?
- 〇〇市が抱える問題についてあなたの意見を聞かせてください
- 市民の方からクレームを言われた場合、どのように対処しますか?
- 公務員としての将来像を教えてください
- 行政の中立性を守るために必要なことは何だと思いますか?
- 他自治体の先進的な取り組みで参考になるものはありますか?
- 少子化対策について、行政が取り組むべきことは何だと思いますか?
- ボランティアや地域活動など、行政に関わった経験はありますか?
- 最後に何か質問はありますか?
これらの質問は、受験者の志望度を図るためや公務員という仕事に対する理解度を評価している可能性が高いです。多くの自治体でも聞かれやすい質問となっているため、受験先のことを最低限調べた上で自分なりの考えをまとめておきましょう。



自分だけで考えるより、考えた案を第三者に評価してもらうのがおすすめです!
1.公務員を選んだ理由を教えてください
受験者がなぜ民間企業ではなく公務員を目指すのか、その動機が明確かつ現実的かどうかを見極めることが目的です。公務員は安定性だけでなく、公共性・継続性・責任の重さが求められる職業であるため「公務員として何をしたいのか」「どのように社会に貢献したいのか」まで考えが及んでいるかが評価されます。
| 【回答例】 |
|---|
| 私は、地域に密着した形で人々の暮らしを支える仕事がしたいと考え、公務員を志望しました。以前から地域の防災や福祉などの課題に関心があり、安定した立場で継続的に取り組める点に魅力を感じたからです。大学での地域調査の授業を通じて、行政が果たしている役割の大きさや住民と接する現場の重要性を実感しました。住民に最も近い立場から支えられる公務員として、責任を持って地域社会に貢献したいと考えています。 |
単に「安定しているから」などの一般的な理由ではなく、自分自身の関心・経験と結びつけた動機を語ることが重要です。なぜ公務員なのか、なぜその職種や自治体なのかを明確にすることで、志望度の高さと適性が伝わります。
2.〇〇市を選んだ理由を教えてください
受験者がその自治体についてどれほど理解し、志望しているかを見極めています。「なぜ数ある自治体の中で〇〇市なのか」を具体的に説明できなければ、志望度が低いと判断されることもあります。そのため、自治体の取り組み・地域性・自分の経験や関心との繋がりを踏まえた回答が求められます。
| 【回答例】 |
|---|
| 〇〇市を志望した理由は、子育て支援に力を入れている点に魅力を感じたからです。地域全体で子育てを支える姿勢や、若い世代が安心して暮らせる仕組みに共感したためです。実際に〇〇市の『子育て応援アプリ』や保育士確保の取り組みなどを調べる中で、職員の積極的な姿勢を感じました。私も将来、地域住民に寄り添いながら、暮らしやすい町づくりに貢献したいと強く思うようになりました。 |
「〇〇市だからこそ」という他では代替できない理由を盛り込むことが重要です。市の公式ホームページや広報誌などで取り組みを事前に調べ、自分の興味関心や経験と結びつけて話すことで、志望動機に説得力が生まれます。内容をコンパクトにまとめつつも、自治体への理解と貢献意欲が伝わる構成を意識しましょう。
3.採用されたら取り組んでみたい仕事はありますか?
受験者が志望先の業務内容を正しく理解しているか、またその中でどのように貢献したいと考えているかを確認する意図があります。単なる希望を述べるのではなく「なぜその業務に関心があるのか」「どんな姿勢で取り組みたいのか」といった点まで踏み込んで答えることで、意欲と職務理解の深さを示すことができます。
| 【回答例】 |
|---|
| 採用されたら、高齢者の地域支援に関わる仕事に取り組んでみたいです。高齢化が進む中で、住み慣れた地域で安心して暮らせる環境づくりが重要になると感じているからです。大学のボランティア活動で高齢者と関わる機会があり、孤立や生活の不安を感じている人が多いことに気づきました。行政の立場から地域と連携し、一人ひとりに寄り添った支援に携わっていきたいと考えています。 |
自分の興味や経験をもとにした希望業務を述べることが大切ですが、業務内容をしっかり理解した上で、現実的で前向きな姿勢を示すことが何より重要です。「その業務を通じて何を実現したいのか」「どんな社会課題と関わっているのか」といった視点を持ち、自分の強みや関心と結びつけて答えることで、意欲と適性をバランスよくアピールできます。
4.公務員ではなく民間企業ではダメなんですか?
受験者の志望動機の本気度を確かめるために行われます。「なんとなく安定しているから」や「他にやりたいことがないから」などの受け身な理由では、公務員としての適性が疑われます。民間企業との違いを理解した上で、なぜあえて公務員を選ぶのか、どんな貢献がしたいのかを語れるかが評価のポイントになります。
| 【回答例】 |
|---|
| 民間企業にも魅力はありますが、私は地域に継続的に関わる公務員の立場にこそやりがいを感じています。民間では異動や転勤が多く、地域に長く根付いた取り組みが難しいと感じたからです。大学で地域福祉に関する調査に参加し、行政職員の方が長期的に信頼関係を築きながら住民と向き合っている姿に憧れました。私も公務員として、地域に根差した責任ある仕事を通じて、住民の安心に繋がる支援をしていきたいと考えています。 |
民間を一方的に否定するのではなく、公務員ならではの役割や価値に共感している点を具体的に伝えることが大切です。仕事内容や組織の違いを理解し、その上で「自分のやりたいこと・実現したい姿勢に合っているのは公務員である」と論理的に話すと、志望動機に一貫性と信頼感が生まれます。
5.公務員にしかできない役割は何だと思いますか?
公務員としての役割をどのように理解しているかを確認するための質問です。民間企業との違いを踏まえながら、公務員だからこそ担える役割を自分の言葉で説明できるかが評価されています。
| 【回答例】 |
|---|
| 公務員にしかできない役割は、「公平で中立的な立場から行政サービスを提供すること」だと考えています。なぜなら、利益を追求する民間とは異なり、公務員は全ての住民に対して平等にサービスを届ける責任があるからです。これは公務員だからこそ果たせる役割だと考えています。私は、公平性と責任感を持ち、公務員だからこそできる仕事があると意識して働きたいと考えています。 |
この質問では、「公務員と民間企業との違い」を意識することが重要です。公平性や中立性、公共性といった公務員ならではの特徴を押さえた上で、自分の意識や将来像と結びつけて伝えましょう。
6.なぜ国家公務員ではなく地方公務員を志望したのですか?
「国家公務員」と「地方公務員」の違いを理解した上で、自分のキャリアにふさわしい選択をできているかを確認する質問です。地域密着性や住民との近さなど、地方公務員ならではの特徴を明確に伝えることが評価に繋がります。
| 【回答例】 |
|---|
| 私は、地域に密着して住民に寄り添える仕事がしたいと考え、地方公務員を志望しました。国家公務員は国全体の制度や政策を扱いますが、地方公務員の住民に最も近い立場で課題解決に携われる点に魅力を感じたからです。大学時代に地元の地域活動に参加した際、行政職員の方が住民の相談に親身に対応している姿を見て、自分も直接的に地域を支える立場になりたいと感じました。こうした経験から、私は地方公務員として地域の方々と向き合い、身近な課題に取り組むことで社会に貢献したいと考えています。 |
どちらが上か下かという比較ではなく、自分の志向や経験から地方公務員に適性があると前向きに説明することが大切です。地方公務員の志望動機が曖昧だと「国家公務員の方が良いのでは?」と思われる恐れがあるため注意しましょう。
7.転勤や異動があっても問題ないですか?
受験者が組織人として柔軟に働く意識を持っているか、勤務地や職務内容の変化に前向きに対応できるかを確認するために行われます。公務員は部署異動や転勤が定期的にある職種のため、長期的な視点でキャリアを捉えているかどうか、またその変化に対して適応する意欲があるかが評価のポイントになります。
| 【回答例】 |
|---|
| はい、転勤や異動があっても前向きに受け入れるつもりです。様々な業務や地域に関わることで視野が広がり、より柔軟な対応力が身に付くと考えているからです。大学のアルバイトでは部署異動を経験しましたが、新しい環境に適応しながら役割を果たす中で成長を実感しました。異動先でも自分に求められる役割を理解し、早く信頼されるよう努力していきたいと考えています。 |
異動や転勤をネガティブに捉えず、新たな経験や成長の機会として前向きに捉えている姿勢を示すことが重要です。「慣れた環境にこだわらず、柔軟に対応できる力がある」という印象を与えることで、組織内で信頼されやすい人物として評価されます。また、過去の経験を絡めて「環境変化への適応力」を具体的に示すと、説得力が高まります。
8.デジタル化やDX推進について、行政に必要な取り組みは何だと思いますか?
社会の変化や行政の課題に対するIT技術導入を、どの程度理解しているかを確認するための質問です。単に知識を披露するだけでなく、自分なりの視点を交えて答えることが重要です。
| 【回答例】 |
|---|
| 行政のDX推進で必要なのは、住民が使いやすいサービスの提供だと考えます。単にシステムを導入するだけではなく、高齢者やITに不慣れな人も含めて「誰もが利用できる仕組み」でなければ意味がないからです。例えば、手続きのオンライン化を進める際に、窓口でのサポート体制を併設することで、住民全員が安心してサービスを利用できると考えます。以上のように、「効率化」だけを考えるのではなく、「住民に寄り添うサービス向上」を目指すべきだと考えています。 |
最新のキーワードを知っているかよりも、「行政の立場でどう取り組むべきか」を住民目線で伝えることが大切です。オンライン化や効率化の利点を述べつつ、誰一人取り残さないための工夫を加えると説得力を持たせられます。
9.公務員にはどのような能力が求められると思いますか?
受験者が公務員の職務や責任を正しく理解しているかどうかを見極めています。民間企業との違いや公務員の社会的役割を踏まえた上で、どのような資質が求められるかを自分なりに考えているかがポイントです。
| 【回答例】 |
|---|
| 公務員には、住民目線に立って物事を考える力が求められると思います。公務員は行政の立場からサービスを提供する一方で、常に市民の立場に立って考えることが重要だからです。大学の地域調査で高齢者の生活環境について聞き取りをした際も、現場の声を踏まえた対応の大切さを実感しました。制度や業務の枠組みだけで判断せず、相手の立場を想像しながら行動できる力を大切にしたいです。 |
公務員の役割や働き方を理解した上で「なぜその力が必要なのか」「どのように活かせるのか」まで答えることが重要です。また、自分の経験や価値観と繋げることで、受け売りではない説得力のある答えになります。
10.今後の行政に必要だと思う人材像はどのようなものですか?
社会情勢や行政の課題を踏まえ、どのような人材が求められているのかの理解度を評価するための質問です。理想像を語るのではなく、行政の現状や将来を踏まえた上で具体的にどんな人材が必要かを示すことが評価に繋がります。
| 【回答例】 |
|---|
| 今後の行政に必要なのは、住民に寄り添いながら新しい変化に柔軟に対応できる人材だと考えます。なぜなら、少子高齢化や災害対策、DX推進など課題は多様化しているため、前例に捉われず改善を続ける姿勢が求められるからです。私も公務員として、住民の声を丁寧に聞き取り、変化に対して前向きに対応できる職員を目指したいと考えています。 |
「行政課題の多様化」と「社会の変化」を背景にした上で、今後の行政に必要だと思う人材像を語ることが大切です。具体的なキーワードを用い、なぜ必要なのかを伝えることで、面接官を納得させられます。
11.住民から信頼されるために必要な姿勢は何だと思いますか?
公務員として住民と接する上で欠かせない姿勢を理解しているかどうかを確認するための質問です。行政の仕事は、住民の協力や理解があってこそ成り立つため、信頼関係を築くためにどんな心構えを持っているかを評価しています。
| 【回答例】 |
|---|
| 住民から信頼されるためには、誠実さと公平さを持って対応する姿勢が必要だと考えています。行政はすべての住民に平等にサービスを提供する立場にあり、対応に偏りや不誠実さがあれば信頼を失うからです。大学時代の地域活動では、住民の要望にすぐ応えられない時でも誠意を持って対応したことで、信頼関係を築くことができました。これらの経験から、住民に信頼してもらうためには誠実さと公平さを持って取り組む姿勢が重要だと考えています。 |
自分の経験を交えて説明することで、理想論ではなく現実的な考えであることを示せます。また、なぜこの姿勢が重要なのかも説明することで、面接官も納得しやすくなります。
12.併願状況を教えてください
受験者が本当にその自治体や官庁を志望しているのか、志望度の高さや本気度を確認しています。併願していること自体が問題ではなく、なぜこの受験先を選んでいるのか、志望理由に一貫性があるかが見られています。
| 【回答例】 |
|---|
| はい、他にも〇〇市と△△県を併願していますが、〇〇市(志望先)が第一志望です。それぞれの地域の特色や取り組みを比較した上で、自分の目指す方向と合致していると感じたためです。」特に〇〇市(志望先)の子育て支援策や職員の現場主義に魅力を感じ、自分の関心分野と強く結びついていると実感しました。他も受験していますが、〇〇市(志望先)で働きたいという気持ちが最も強く、その意志を持って臨んでいます。 |
正直に併願先を伝えつつ、その中でもなぜこの受験先が第一志望なのかをしっかり説明することが大切です。併願するのは当然のこととして受け止められているため、問題はありません。ただし、すべてを「横並び」にせず「だからこそこの自治体を選びたい」といった一歩踏み込んだ理由付けがあると、志望度の高さがより伝わります。
13.配属先が希望通りいかなかったらどうしますか?
受験者が組織の一員として柔軟に働けるかどうか、割り当てられた仕事にも真摯に取り組む姿勢があるかを見極めています。配属先は組織の判断で決まることが多いため、希望が通らなくても前向きに適応し、学ぶ意欲があるかが重視されます。一方で、自分の希望を押し通す姿勢や消極的な反応はマイナス評価に繋がります。
| 【回答例】 |
|---|
| 希望と違う配属先でも、自分に与えられた役割を前向きに受け入れて取り組みます。どの部署にも、地域や住民に貢献できる役割があると考えているからです。大学のゼミでも希望外の研究テーマを担当しましたが、視点を変えて調べる中で興味が広がり、最後までやりがいを持って取り組めました。まずは目の前の業務で信頼を積み重ね、将来的に自分の希望や強みを活かせる場面でも貢献できるよう努力したいです。 |
「どこでも貢献できる」「与えられた環境でベストを尽くす」という前向きな姿勢を示すことが重要です。希望があること自体は問題ではありませんが、それに固執せず組織の一員として柔軟に対応できること、そこから学ぶ意欲があることを伝えることで、公務員にふさわしい適応力と責任感をアピールできます。
14.公務員が批判されやすい立場であることをどう考えていますか?
公務員の特性を理解しているかや批判や厳しい意見に対してどう感じているかを確認するための質問です。公務員は税金で成り立つ組織であるため、常に説明責任や公平性が求められ、批判を受けやすい立場にあることを理解しているかが評価のポイントとなります。
| 【回答例】 |
|---|
| 公務員が批判を受けやすい立場にあることは、当然だと考えています。税金で運営され、住民の生活に直結する業務を担っている以上、透明性や説明責任が求められるからです。批判があれば内容を真摯に受け止め、責任を持って説明することで、今まで以上に住民から信頼してもらえるとも考えています。 |
「批判は不当だ」と否定的に捉えるのではなく、批判されやすい立場であることを受け入れた上で、前向きに対応する姿勢を示すことが大切です。誠実な説明責任や改善の意欲を伝えられれば、公務員としての適性や住民目線で考えられる点をアピールできるでしょう。
15.もし今年不合格だったらどうしますか?
受験者の志望への本気度や継続的な努力をする姿勢があるかどうかを確認しています。公務員試験は倍率が高く、1回で合格できないケースも多いため、結果に左右されずにどう行動するか、気持ちの強さと計画性を見極める意図があります。「不合格=終了」と受け止めてしまうような受動的な姿勢はマイナス評価に繋がります。
| 【回答例】 |
|---|
| もし今年不合格だった場合でも、来年の合格に向けて準備を続けます。公務員になりたいという思いは変わらず、時間がかかっても目指す価値があると考えているからです。今年の試験を通して見つかった課題を分析し、模擬面接や論文の添削など実践的な対策を強化して再挑戦したいと考えています。結果に一喜一憂せず、地道に努力を重ね、必ずこの道に進むという意志で取り組み続けます。 |
不合格を想定してもなお前向きに挑戦を続ける意志と具体的な行動計画があることを示すことが大切です。単なる精神論ではなく「どう改善し、どう準備を進めるのか」まで言及できると、計画性と継続力が伝わります。
16.公務員の不祥事に対してどのように感じるか教えてください
受験者が公務員としての倫理観や責任感をどう捉えているか、公的立場に対する意識の高さがあるかを見極めようとしています。不祥事そのものへの意見に加えて、自分が公務員になったときにどう向き合うか・どう防ぐかという姿勢を語れると、信頼性や誠実さを評価されます。
| 【回答例】 |
|---|
| 公務員による不祥事は、住民からの信頼を大きく損なう行為であり、非常に重く受け止めるべきだと感じています。一人の不正が組織全体の評価に影響し、誠実に働く職員まで疑われてしまうからです。ニュースで公金の私的流用が報じられた際、その組織全体が批判されているのを見て、公務員の行動の重みを改めて実感しました。自分自身も常に公務員としての自覚と責任を持ち、透明性と誠実さを大切に働きたいと考えています。 |
不祥事に対して批判的な立場を示すだけでなく、自分が公務員になったときにどう防止・意識づけをするかまで答えることが重要です。倫理観や責任感を冷静に伝えつつ、「自分ごと」として意識していることが伝われば、信頼性と意欲の両方を評価される回答になります。
17.公務員の仕事は地味だと言われることもありますが、その点をどう考えますか?
公務員の仕事の本質を理解しているかどうかを確認するための質問です。派手な成果や目立つ活躍ばかりではなく、裏方の積み重ねが社会を支えているという意識を持っているかを評価しています。
| 【回答例】 |
|---|
| 公務員の仕事は確かに地味に見えることもありますが、その積み重ねが住民の生活を支える大切な役割だと考えています。目に見えづらい事務や取り組みの一つ一つが、安心して暮らせる社会を成り立たせているからです。大学時代に地域イベントの運営を担当した際、事前の準備や裏方の作業は地味でしたが、それがあったからこそ多くの人が安心して楽しむことができたと感じました。この経験から、見えない努力が結果に繋がる大切さを実感しました。公務員としても、表に出ない地味な仕事だからこそ真剣に行い、住民の暮らしを支える存在になりたいと考えています。 |
地味に見える仕事こそが社会に必要不可欠であると、前向きに捉える姿勢を示すことが大切です。目立たない業務でも責任を持って取り組む姿勢を強調すれば、誠実さと使命感をアピールでき、面接官に好印象を与えられるでしょう。
18.〇〇市が抱える問題についてあなたの意見を聞かせてください
受験者が志望自治体への関心や理解をどれだけ深めているかを確認する意図があります。表面的な情報ではなく、地域の課題を自分なりに分析し、主体的に意見を持っているかが評価の対象です。また、課題に対する視点や改善に向けた前向きな考え方も、公務員としての資質を測るポイントになります。
| 【回答例】 |
|---|
| 〇〇市(志望先)が抱える課題として、高齢化による地域コミュニティの希薄化が挙げられると考えています。高齢者の単身世帯が増える一方で、地域の繋がりが弱まり、孤立や支援不足が問題になっていると感じるからです。市の統計資料でも、民生委員の担い手不足や町内会の活動低下が課題として挙げられており、住民主体の取り組みの維持が難しくなっていると知りました。行政としても、地域団体や若い世代との連携を促進し、誰もが安心して暮らせる仕組みづくりに取り組む必要があると考えます。 |
事実やデータを踏まえつつ、その問題がなぜ重要か、どう解決すべきかという自分の考えを簡潔に伝えることが大切です。自治体ホームページや地域ニュースなどから課題を把握し、自分の関心や経験と結びつけて答えると、より説得力のある内容になります。また、否定的な論調に偏らず、前向きな視点と公務員として関わる意欲を添えると好印象です。
19.市民の方からクレームを言われた場合、どのように対処しますか?
住民対応において、冷静かつ誠実な対応ができるかを確認するためのものです。クレーム対応は現場で頻繁に発生するため、感情的にならず、住民の立場に立って対応できるか、適切な傾聴姿勢と課題解決意識を持っているかどうかが評価のポイントです。
| 【回答例】 |
|---|
| まずは冷静に話を受け止め、相手の気持ちを理解する姿勢で対応します。相手が感情的になっている場合でも、しっかり話を聞くことで信頼関係を築く第一歩になると考えるからです。以前、飲食店でのアルバイト中にお客様から厳しい指摘を受けた際も、まずは共感の姿勢で話を聞いたことで、最終的には感謝の言葉をいただけました。市民の声には必ず背景があると考え、一方的に判断せず、事実確認と丁寧な説明を心掛けたいです。 |
「クレーム=困った人」という偏見を持たず、住民の声を行政サービスの改善機会と捉える前向きな姿勢を示すことが重要です。冷静さ・共感・丁寧な説明の3点を押さえながら、必要に応じて上司や関係部署と連携する姿勢を示すと、組織人としての柔軟さや信頼性も伝わります。
20.公務員としての将来像を教えてください
受験者が中長期的に公務員としてどう成長し、どのように貢献していきたいのかを見ています。将来像を明確に描けている人は、自己理解と職務理解が深く、継続的に努力できる人材と評価されます。
| 【回答例】 |
|---|
| 将来的には、市民にとって信頼される職員となり、地域の課題解決を主体的に進められる存在になりたいと考えています。一人一人の声に丁寧に向き合い、行政の現場から社会をより良くできるのが公務員の魅力だと感じているからです。学生時代のボランティア活動を通じて、制度の支援があっても、現場の課題を丁寧にすくい上げる存在が重要だと実感しました。目の前の業務に真摯に取り組みながら、将来的には企画立案や地域連携にも携わり、住民と行政の橋渡し役を担えるよう努力したいです。 |
理想論だけでなく、自分がどのような姿勢で成長し、地域や市民にどう貢献したいのかという「目的意識」を持って語ることが重要です。段階的な成長ストーリーを意識して伝えることで説得力が増します。
21.行政の中立性を守るために必要なことは何だと思いますか?
公務員の基本的な資質である中立性を守るために、何が必要かを理解しているかどうかを確認するための質問です。特定の個人や団体の利益に偏らず、すべての住民に平等に対応できるかどうかを判断する意図があります。
| 【回答例】 |
|---|
| 行政の中立性を守るためには、法令やルールに基づいた公平な対応を徹底することが必要だと考えてます。公務員が恣意的に判断してしまうと、不平等感が生じ、住民からの信頼を損なう可能性があるからです。公務員として働く際には、法令と規則を軸にして中立性を守り、住民から信頼されるように努力しようと考えています。 |
どうすれば中立性を守れるのかを具体的に伝えましょう。また、政治や利害関係に左右されず、法令や規則に従って判断する姿勢を強調することで、公務員に求められる誠実さや適性をアピールできます。
22.他自治体の先進的な取り組みで参考になるものはありますか?
行政の動向に関心を持っているかや他自治体の取り組みを自分の志望先にどう生かそうとしているかを確認するための質問です。単に取り組みを知っていることだけでなく、学びを自分の志望先にどう応用できるかを考えられているかが評価のポイントになります。
| 【回答例】 |
|---|
| 私は、他自治体の取り組みの中で「デジタル窓口の導入」が参考になると考えています。なぜなら、高齢者や子育て世代を含む幅広い住民が、効率的に行政サービスを利用できる仕組みだからです。例えば、〇〇市では手続きをオンラインで一元化し、窓口での待ち時間を大幅に削減しています。スマホ利用が苦手な方でも、簡単に予約できるようなシステムとなっており、参考になると感じました。公務員として働き始めたら、他自治体の先進事例を学びつつ自分の地域に合わせて応用し、住民が利用しやすい行政サービスを実現していきたいと考えています。 |
「〇〇市の取り組みが良いと思います」と述べるだけでは不十分です。その取り組みのどの部分が参考になると感じたのかを明確にし、自分の経験や住民目線と結びつけることで説得力が増します。また、それを志望先でどう活かしたいかを示すことで、問題意識と実行力の両方を持つ人材であるとアピールできるでしょう。
23.少子化対策について、行政が取り組むべきことは何だと思いますか?
社会的課題に対する理解度や問題意識を確認するための質問です。非現実的な理想論ではなく、現実的な視点で行政ができる支援策をどう考えているかを評価しています。
| 【回答例】 |
|---|
| 行政が取り組むべき少子化対策は、子育て世帯が安心して生活できる環境づくりだと考えます。子育てにかかる経済的・精神的な負担を軽減できなければ、出生率の改善は難しいからです。例えば、保育園や学童の充実、住宅支援、オンライン相談など、身近な制度が整っていれば子育ての安心感が増します。大学時代に地域の子育てボランティアに参加した際も「預け先が少ないことが一番の不安」という声を多く聞きました。こうした現場の声を踏まえ、行政が子育て世帯を具体的に支える仕組みを拡充することが、少子化対策に繋がると考えています。 |
抽象的な内容ではなく、具体的かつ現実的に可能な範囲の対策を伝えることが大切です。また、自分の経験や周囲の声を交えて答えると、机上の理論ではなく現実を理解しているとして評価されやすくなるでしょう。
24.ボランティアや地域活動など、行政に関わった経験はありますか?
受験者が地域や社会に対する関心をどれだけ持ち、実際に行動してきたかを確認する意図があります。行政との関わりや地域活動の経験があることで、住民目線や協働の大切さを理解しているか、現場感覚があるかを見極める材料になります。直接的な行政参加でなくても、地域社会と関わった経験があれば前向きに評価されます。
| 【回答例】 |
|---|
| 大学時代に地元の市民祭りの運営ボランティアとして、地域活動に関わった経験があります。地域住民の方々と協力しながらイベントを支える中で、行政と市民の連携の大切さを実感したからです。当日は高齢者の誘導やアンケート回収などを担当し、来場者と直接触れ合いながら、現場の声を行政職員に届ける役割も担いました。この経験から、行政の取り組みを市民にどう伝え、どう支えるかを考える力が身に付いたと感じています。 |
経験の有無だけでなく、その活動を通じて何を感じ、何を学んだかまでしっかり伝えることが重要です。イベントや清掃活動、防災訓練など小さな経験でも構いませんが、それを地域貢献や行政理解に繋げる視点があると好印象です。
25.最後に何か質問はありますか?
受験者の関心の方向性や志望度の高さ、主体的な姿勢が見られています。何も質問が無いと「関心が薄い」と受け取られることもあるため、自分が働くイメージを持っていることや事前に調べた上でさらに知りたいことがある、という姿勢を見せることが評価に繋がります。
| 【回答例】 |
|---|
| ありがとうございます。最後に、新人職員の研修制度についてお聞きしてもよろしいでしょうか。入庁後にどのような研修や学びの機会があるのかを知ることで、より具体的に働くイメージを持ちたいと考えたからです。〇〇市のホームページで、OJTや配属前研修があることは拝見しましたが、実際に現場でどのようなサポートが受けられるのか興味があります。 |
あらかじめ調べた上で、さらに知りたいことを前向きな意図で質問することが重要です。待遇や休暇など個人的な条件よりも、業務内容・研修・職場環境・やりがいなど、志望動機と繋がる質問を選ぶことで、意欲と関心の高さを伝えられます。
公務員試験の面接の回答でよくある失敗例
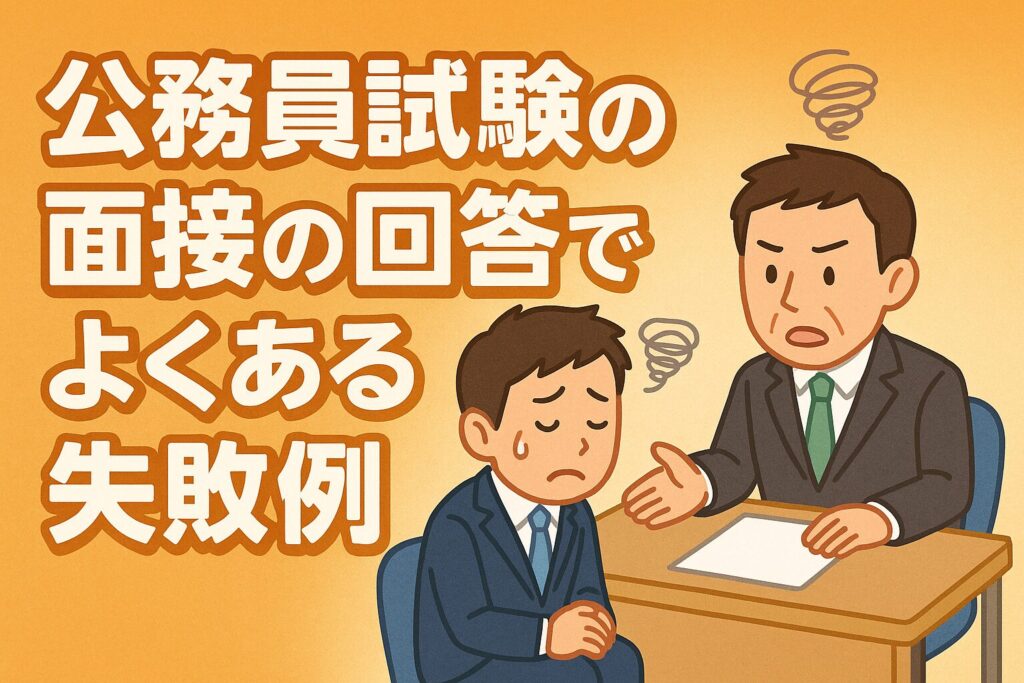
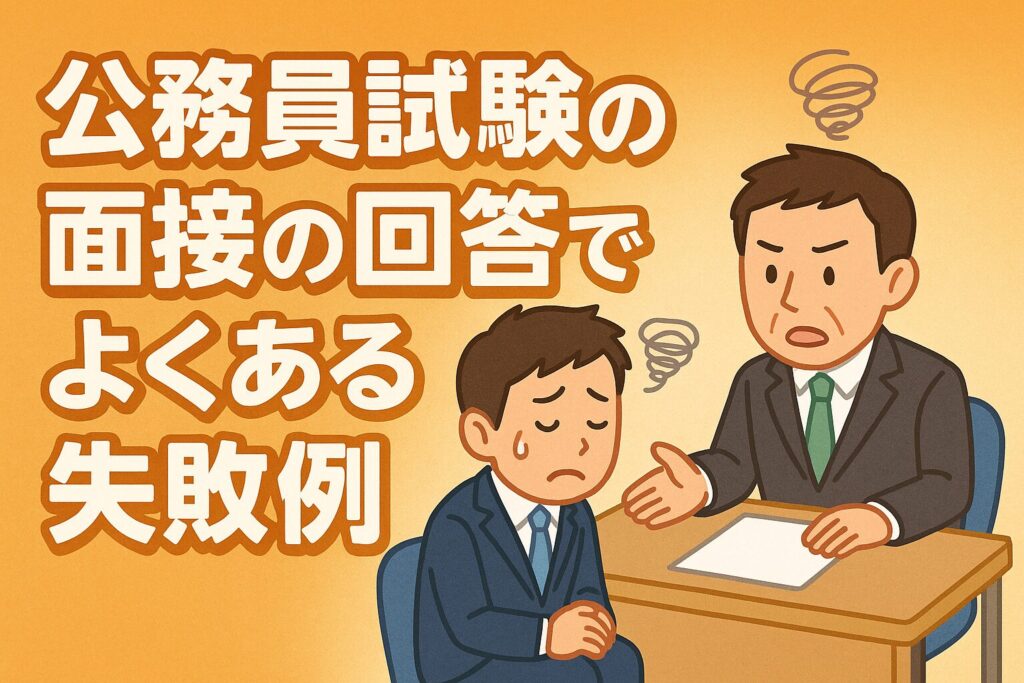
公務員試験の面接の回答では、不合格になる多くの受験者がやってしまっている失敗例があります。公務員試験の面接の回答でよくある失敗例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 志望動機や自己PRが抽象的で説得力に欠ける
- 質問の意図を正しく理解できず、的外れな回答をしている
- 一方的に話しすぎて面接官との会話になっていない
- 緊張しすぎて「はい」「いいえ」だけで終わっている
- マイナスな要素をそのまま伝えている
- 正しい敬語を使えていなくカジュアルすぎる
質問に対する回答でこのような回答をしている方は、マイナスな印象を与えている可能性が高いです。また、回答内容だけでなく面接官と会話しているということを意識し、適度な表情やアイコンタクト、間の取り方なども大切です。
こうした失敗を防ぐためにも、頻出質問の対策だけでなく、模擬面接や録画練習を通じて実践感覚を養っておきましょう。



失敗例を知り、適切な対策をすることが面接合格への第一歩です!
【手順別】公務員試験の面接で回答の質を上げる方法
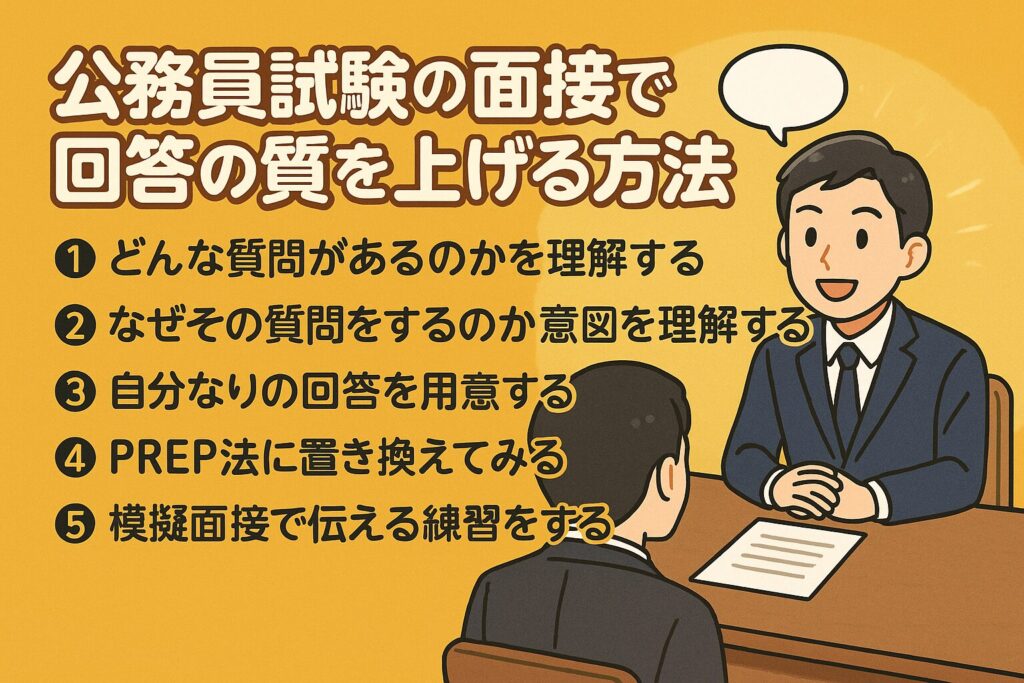
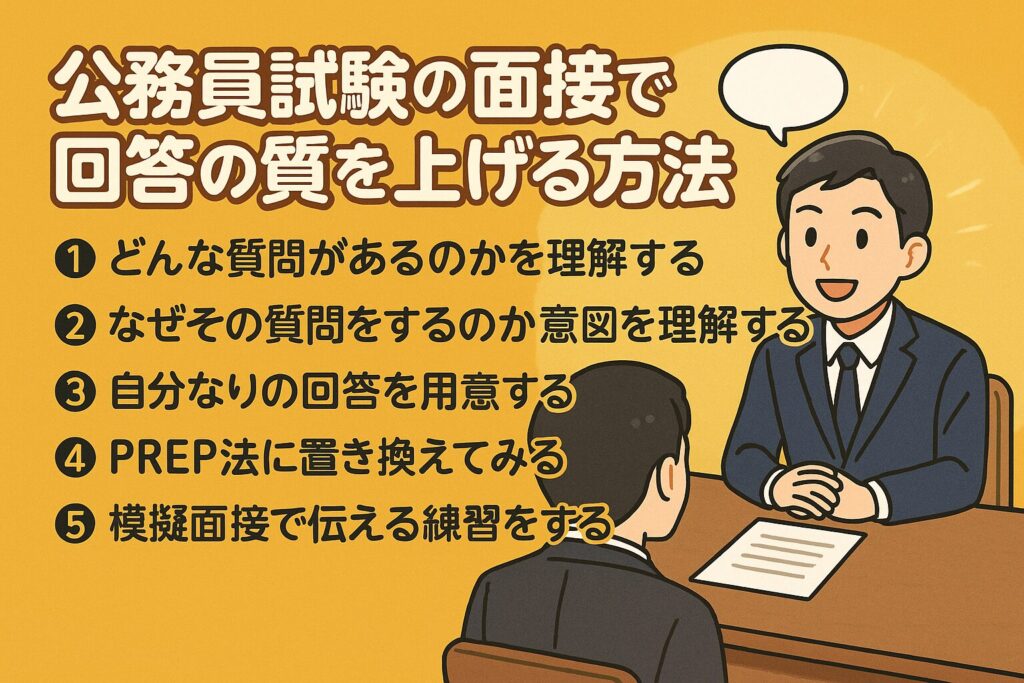
公務員試験の面接では、面接官の質問に対してただ回答すれば良いというわけではありません。自分の魅力を知ってもらい、面接官に「採用したい」と思わせることが大切です。そのためには、回答の質を上げることを意識しましょう。
公務員試験の面接で回答の質を上げる方法としては、以下の手順を参考にしてください。
- どんな質問があるのかを理解する
- なぜその質問をするのか意図を理解する
- 自分なりの回答を用意する
- PREP法に置き換えてみる
- 模擬面接で伝える練習をする
以上を意識することで回答の質を高められ、説得力を持たせやすくなります。また、PREP法の活用や模擬面接で練習することで、より精度を高められるでしょう。



初めて公務員試験の面接に挑戦する方だけでなく、過去に面接に落ちた経験のある方も、この手順で回答を考えてみるのがおすすめです!
①どんな質問があるのかを理解する
面接で質の高い回答をするためには、どんな質問があるのかを理解しましょう。公務員試験の面接では、志望動機や自己PR、学生時代に力を入れたこと、長所・短所などの定番質問に加え、自治体ごとに聞かれやすい質問が異なります。
また、受験先の自治体や官庁に関する質問、最近のニュースや行政課題などの時事を問う質問も多いです。
想定される質問を理解することで、効率的に回答を準備できます。さらに、自分が苦手とする質問の傾向も見えてくるため、重点的な対策もできるでしょう。



過去の面接体験談や模擬面接の情報を参考に、よくある質問を一覧化してみることで、回答を考えやすくなります!
②なぜその質問をするのか意図を理解する
回答の質を上げるためには、面接官がその質問で何を評価したいのか(質問の意図)を理解することが重要です。面接官の質問の意図は、受験者の情報を聞き出すことだけではありません。回答内容から、受験者の人柄や価値観、公務員としての適性なども判断しています。
例えば「あなたの長所は何ですか?」という質問には、自己分析の深さやそれをどう職務に活かそうとしているかを確認する意図もあります。
質問の背景にある意図を汲み取れれば、より的確で説得力のある回答を考えやすいです。各質問に対して、直接的な回答を考えるだけでなく、常に「この質問をする意図は何なのか?」を考えることを意識しましょう。



ただ、意図を考えすぎて言葉足らずになったり、簡潔に答えられなくなったりするのはNGです!
③自分なりの回答を用意する
各質問の意図を理解できたら、自分自身の経験や価値観に基づいて自分なりの回答を用意しましょう。面接では、テンプレートのような回答ではなく、「その人らしさ」が感じられる言葉にこそ説得力が生まれます。
例えば、志望動機に対する回答で「地域に貢献したい」だけでは不十分です。自分がどんな経験を通してそう考えるようになったのかやどのように公務員の仕事と結びつけているのかを自分の言葉で語る必要があります。
また、回答全体に一貫性を持たせることも大切です。回答に一貫性が無いと、信頼性に欠けると判断される恐れがあるため、各質問だけでなく全体の整合性も確認しておきましょう。



「自己PRと志望動機」、「自分の強みと志望先の職務内容と結びついているか」などは矛盾が生まれやすい部分のため、注意が必要です!
④PREP法に置き換えてみる
自分なりの回答を用意できた後は、面接官に伝わりやすい形に整理することが大切です。整理する際に効果的な方法として「PREP法」が挙げられます。
PREP法とは、「Point(結論)→ Reason(理由)→ Example(具体例)→ Point(結論)」の頭文字を取った、簡潔にわかりやすく伝えるための話し方です。例えば「あなたの長所は何ですか?」という質問に対して、PREP法で回答すると以下のような文章になります。
| PREP法例文 |
|---|
| ・P→結論(Point):「私の長所は継続力です。」 ・R→理由(Reason):「理由として、何事も毎日少しでも続ける姿勢を大切にしているからです。」 ・E→具体例(Example):「継続力が発揮された場面として、大学時代は毎朝7時に図書館へ通い、1日も欠かさず勉強を続けたことで、国家試験に一発合格できたことが挙げられます。」 ・P→結論(Point):「この継続力を活かして、公務員としても粘り強く課題に取り組みたいです。」 |
PREP法を使うことで話の流れが整理され、説得力と印象が格段にアップします。最初は難しく感じるかもしれませんが、回答を1つずつPREPの順番に当てはめてみることで、誰でも使いこなせるためおすすめです。



最初は慣れないですが、模擬面接などで繰り返し回答することで徐々に慣れることができるでしょう!
⑤模擬面接で伝える練習をする
どれだけ質の高い回答を考えても、実際の面接で緊張や予想外の質問が来て、用意した回答をうまく伝えられないことも多いです。本番で100%の力を発揮したい方は、模擬面接を繰り返し行いましょう。
模擬面接では回答内容だけでなく、話し方や声のトーン、目線、姿勢など、本番と同じ状況を想定してアウトプットできます。回答内容に話し方や表情が伴っていなければ不自然な印象を与える可能性も高いため、模擬面接は非常に効果的です。
また、第三者に評価してもらうことで「伝わりづらい部分」や「悪印象を与える癖」など、自分では気付きづらい部分も明確になるでしょう。結果的に、面接力全体の向上にも繋がります。



模擬面接は、可能な限り様々な方に面接官役をしてもらうのがおすすめです!
公務員試験の面接対策はどのように行う?


公務員試験の面接対策方法としては、以下3つの方法が一般的です。
- 独学
- 予備校や専門学校
- オンライン講座
対策方法によって、特徴やメリットデメリットが異なります。最適な対策方法で対策するためにも、それぞれの特徴を抑えておきましょう。



どんな点を重視したいかを明確にした上で、自分に合ったものを選ぶことが合格への近道です!
独学
独学で公務員試験の面接対策を行う場合、過去に頻出した質問を把握し、回答を準備しておくことが大切です。志望動機や自己PR、長所・短所など定番の質問は、必ず答えられるようにしておきましょう。
独学のメリットとデメリットは、以下の通りです。
独学では、対策を自分だけで行うことがほとんどのため、対策に費用が掛かりません。さらに、自分のペースで対策できることから、ストレスなく確実に対策を進められるのがメリットです。
ただ、模擬面接がしづらいため、第三者からのフィードバックが得づらいのがデメリットです。可能であれば、家族や友人に面接官役をお願いして練習することで、独学でも実践的な対策ができるでしょう。



自分に厳しく対策できる方は、独学が1番おすすめです!
公務員試験の面接対策において独学について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。


予備校や専門学校
予備校や専門学校では、面接対策に限らず筆記試験や小論文試験など網羅的に対策できるのが特徴です。ノウハウを基に専門講師による実践的なサポートが整っているため、とにかく面接対策を効果的に進めたい方におすすめです。
予備校や専門学校のメリットとデメリットは、以下の通りです。
予備校や専門学校は、独学のデメリットをカバーできることに加え、モチベーションを維持しやすいのがメリットです。計画に沿って対策を進めやすく、面接が苦手な方でも面接力を向上させやすいと言えるでしょう。
ただ、高額な費用がかかることや通学時間の負担といったデメリットもあるため、コストと利便性を考えた上で活用するかどうかを決めることが大切です。



年間で100万円前後かかる学校も多いため、面接対策だけを重点的に対策したいなら次の「オンライン講座」をおすすめします!
オンライン講座
オンライン講座とは、オンライン上で講師に面接してもらえるサービスのことです。最近では、動画講義やライブ授業で基礎を学び、チャットやオンライン添削で面接カードをチェックしてもらえるサービスも増えています。
オンライン講座のメリットとデメリットは、以下の通りです。
オンライン講座のメリットは、予備校や専門学校に比べて費用が比較的安く、同じような質の対策ができることです。面接官役をしてくれる講師は、面接官経験や過去に予備校などで働いていた経験のある講師もいる可能性が高いため、専門的なフィードバックを受けられるでしょう。
一方で、自己管理が甘いと学習が進みづらいことや対面に比べて緊張感に欠けるデメリットもあります。それらのデメリットよりも、効率やコスパを重視する方にはおすすめの対策方法です。



オンライン講座は、良いとこ取りができる面接対策方法とも言えます!
数的塾では、LINE公式アカウントを追加することで、公務員試験対策の特典を受け取れます。面接対策に関する特典もあるため、気になる方は活用してみましょう。
\数的塾の限定講義&合格ガイド無料配布中/
公務員試験の面接に関するよくある質問
公務員試験の面接に関するよくある質問を以下にまとめたので、参考にしてください。
まとめ
公務員試験の面接試験を突破するためには、よくある質問を理解して自分なりの回答を用意しておくことが大切です。
ただ、面接では受け答えの部分だけを判断しているわけではありません。
身だしなみや第一印象、人間性など様々な部分から総合的に評価されることを忘れずに、バランスよく対策した上で面接に臨みましょう。
\数的塾の限定講義&合格ガイド無料配布中/

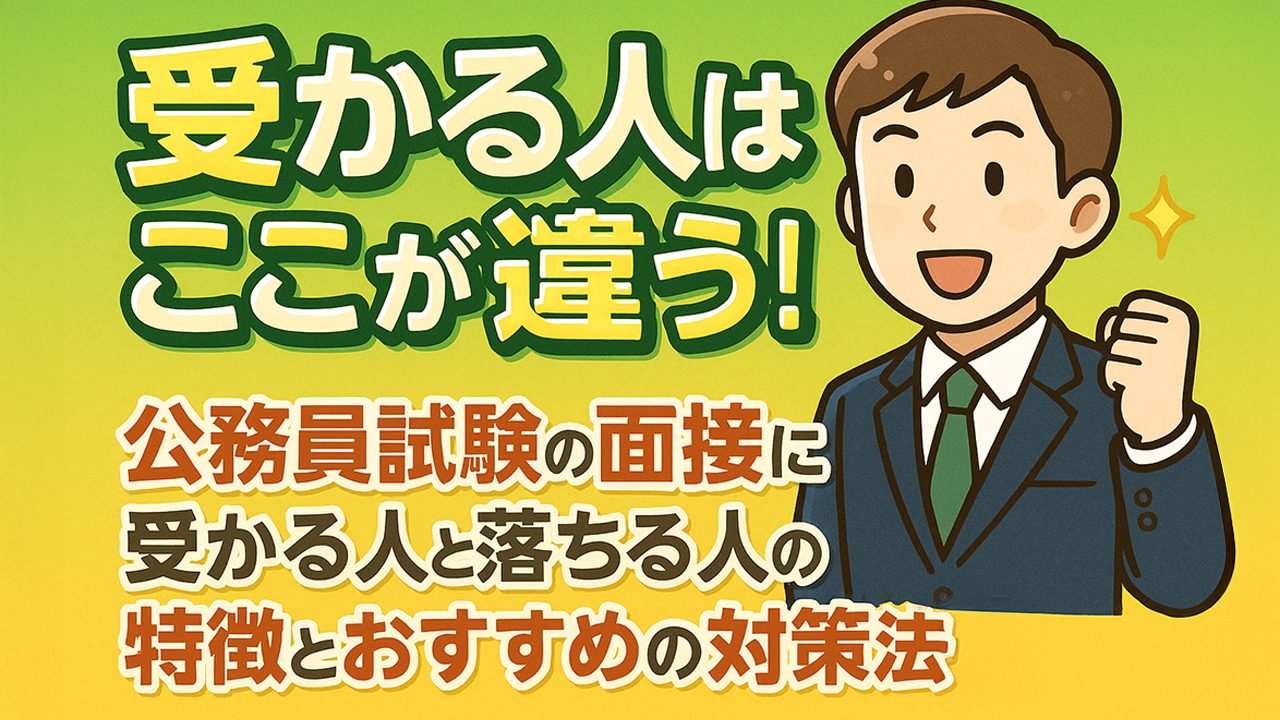
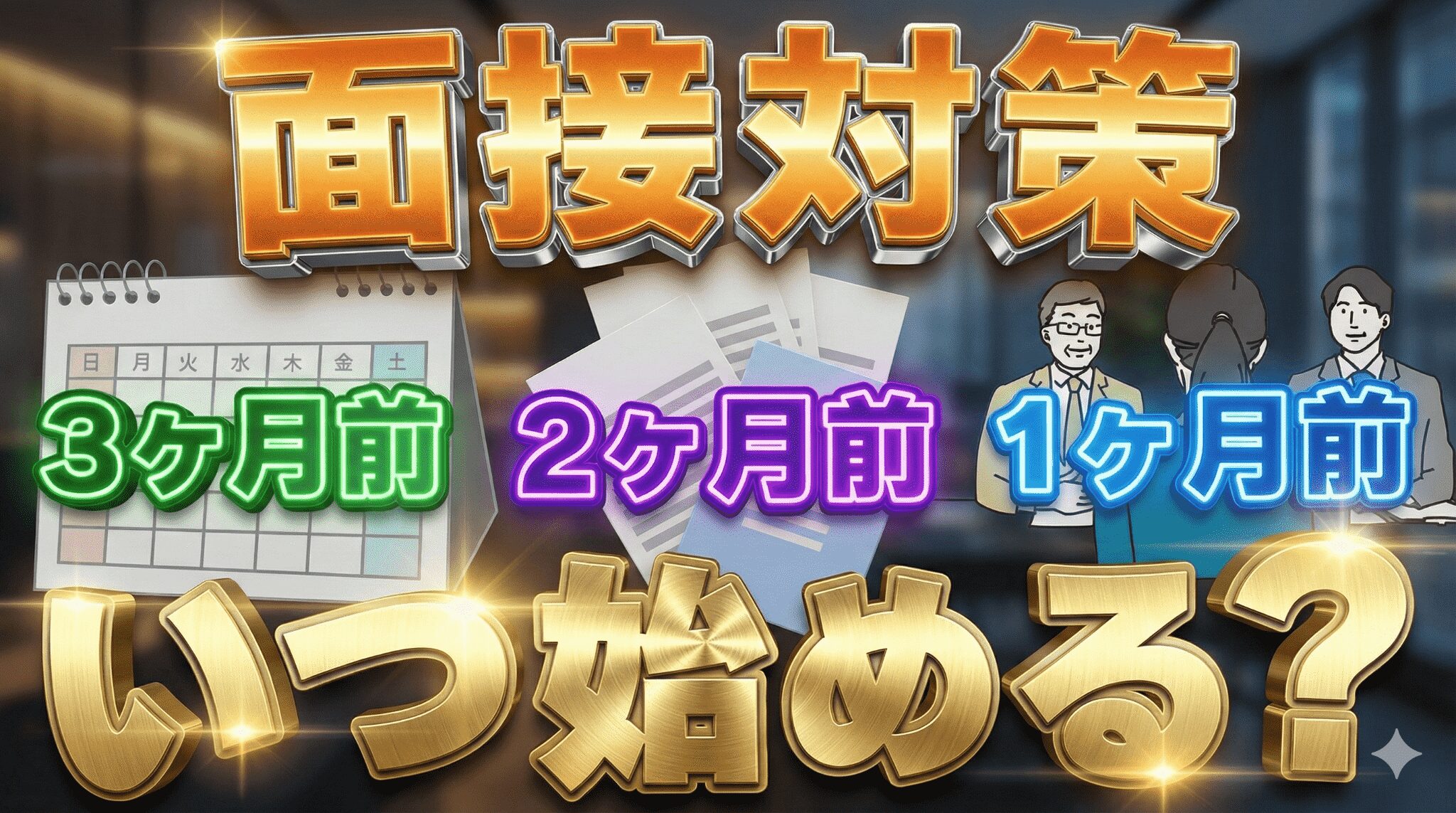

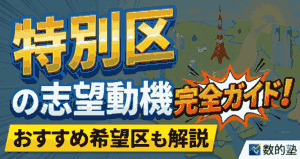
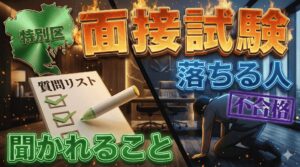
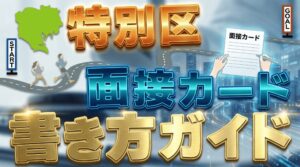
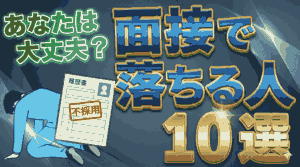
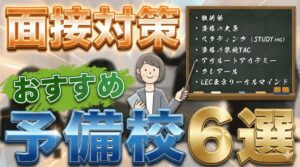

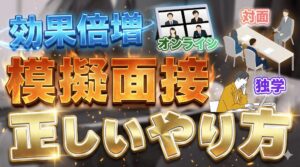
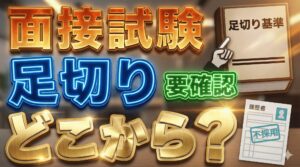
コメント